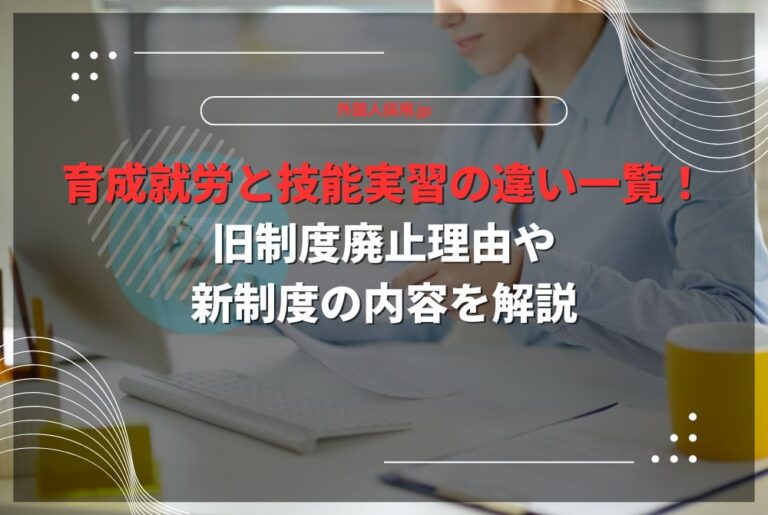「技能実習制度が廃止され、新たに『育成就労制度』が始まると聞いたけれど、具体的に何がどう変わるのかよくわからない」「自社にどのような影響があるのか、メリットやデメリットを知りたい」といったお悩みはありませんか。1993年から続いた制度の大きな変更に、戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、技能実習制度が廃止される理由から、新設される育成就労制度の目的、そして両者の違いを一覧表でわかりやすく解説します。また、企業側にとってのメリット・デメリットや、対象外となる可能性のある分野についても詳しく説明します。
この記事を最後まで読むことで、新制度の全体像を正確に把握でき、2027年の施行に向けて今から何を準備すべきかが明確になります。
技能実習制度廃止の理由

技能実習制度は、国内だけでなく海外からも批判を受け、見直されることになりました。制度の問題点が社会問題となって廃止され、新たな「育成就労制度」が創設されることになりました。廃止の主な理由は以下の2点です。
|
外国人技能実習制度に関する詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。
目的と実態に差があったため
技能実習制度は、もともと開発途上国への技術移転による国際貢献を目的に作られました。しかし、実際には日本国内の人手不足を補う労働力として広く使われ、この目的と実態のずれが問題となっていました。
実質的には労働力として受け入れているのに、制度上はそうではないとされてきたのです。そこで、新たに設けられる育成就労制度では、日本の人手不足分野における「人材育成と人材確保」を明確な目的として掲げ、実態に合った制度へと見直されることになりました。
技能実習生の立場の弱さが浮き彫りになったため
技能実習制度では、実習生の弱い立場が社会問題として認識されていました。一部の受け入れ企業や、実習生を支援するはずの監理団体による人権侵害が報告されており、これが原因とみられる実習生の失踪も多く発生していました。
特に、技能実習制度では原則として職場を変える「転籍」が認められていなかったため、たとえ実習先が劣悪な環境であっても、実習生はそこから抜け出すことが困難でした。こうした問題を考慮し、人権に配慮した適切な雇用制度を新たに作る流れとなり、新制度では外国人の人権保護が重要な点となっています。
育成就労制度とは?

育成就労制度は、これまで国内外から多くの問題点が指摘されてきた技能実習制度に代わる、新しい在留資格制度として創設されました。この制度は、外国人労働者の人権保護とキャリアパスの明確化を図り、外国人にとってより魅力的な制度とすることを目指しています。
2024年6月14日には、技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行に関する改正法が国会で可決・成立しました。育成就労制度は2027年4月に施行される予定です。現在の技能実習制度は、2027年(改正法の公布日である令和6年6月21日から3年以内)までは継続され、その後、新たに設けられた育成就労制度へと完全に移行します。
この制度の主な目的は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保で、3年間の育成期間で特定技能1号の水準にまで育成し、特定技能制度への円滑な移行が図られるように設計されています。詳細については、こちらをご覧ください。
参考:育成就労制度
技能実習生制度廃止による新制度「育成就労制度」とは?内容の違いを解説
育成就労と技能実習の違い一覧!

1993年から続いてきた技能実習制度が廃止され、新しい「育成就労制度」への移行が正式に決定しました。育成就労制度は、これまでの技能実習制度にあった「目的と実態のずれ」や「特定技能制度とのつながりの弱さ」といった問題を解消し、人手不足の分野で「人材を確保」し「人材を育成」することを目指しています。
ここでは、これまでの技能実習制度と新しく始まる育成就労制度の主な違いを表にまとめました。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献・開発途上国への技術移転 | 日本の人手不足分野における人材確保と人材育成(3年間で特定技能1号レベルの人材に育成する) |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則最長3年(試験不合格などの相当な理由があれば最大1年延長可能) |
| 転籍 | 原則として不可 | 一定の条件下で本人の意向による転籍が可能 |
| 対象職種 | 91職種168作業 | 特定技能制度の産業分野と同一 |
| 受入れ人数枠 | 受入れ企業の常勤職員数に応じた上限あり | 技能実習制度に準拠しつつ、分野ごとに受入れ上限数が設定される見込み |
| 就労前の日本語能力 | 特に規定なし | 日本語能力試験N5(A1相当)レベル以上の合格、またはそれに相当する講習の受講が必要 |
| 支援・保護体制 | 監理団体・外国人技能実習機構 | 監理支援機関・外国人育成就労機構(支援・保護機能が強化される) |
不法就労助長罪は、不法滞在者や就労資格のない外国人を雇用したり、その就労をあっせんする事業者などに適用されるものです。新しい育成就労制度では、外国人労働者の権利保護が一層強化されるとともに、受け入れ企業や監理支援機関の責任もより厳格化されます。そのため、制度の適正な運用がこれまで以上に重要になります。
不法就労助長罪に関する基本的な情報については、こちらをご確認ください。
出典:外国人の適正雇用について
【比較表付き】特定技能と技能実習の10個の違いをわかりやすく解説!
育成就労制度施行で対象でなくなる可能性のある分野一覧

新しい育成就労制度では、受け入れ対象の分野が特定技能制度の対象分野に限定される予定です。そのため、現在90職種165作業が対象となっている技能実習制度のうち、育成就労制度への移行時に、対象外となる職種が出てくる可能性があります。
技能実習制度は職種や作業が細分化されているため、技能実習生を受け入れている企業は、自社の職種が特定産業分野に該当するかどうかを確認するようにしましょう。
育成就労制度で対象となる見込みの分野は、以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
- 自動車運送業
育成就労施工による企業へのメリットデメリット

育成就労制度への移行は、外国人材を受け入れる企業にとって、メリットとデメリットの両方をもたらします。制度の目的が「国際貢献」から「人材確保と育成」へと変わることで、企業が外国人材と関わる際の前提が大きく変化するためです。
育成就労施工による企業へのメリットは、以下のとおりです。
- 技能の習得だけでなく、就労を目的とした在留資格で働いてもらえる
- 技能実習制度より高い日本語能力が求められる
育成就労制度の最大のメリットは、制度の目的が日本の人手不足を解消するための「人材確保と人材育成」と明確になったことです。
これにより、これまでの技能実習制度のように「労働力ではない」という建前と実態のずれがなくなり、企業は「就労」を目的とした在留資格を持つ人材を、労働力として育成しながら受け入れることができます。
また、育成就労の在留資格を得るためには、原則として就労開始前に日本語能力試験N5(A1相当)以上の試験に合格するか、同等の講習を受ける必要があります。そのため、技能実習制度よりも高い日本語能力を持つ人材の採用が期待でき、職場でのコミュニケーションがスムーズになる可能性があります。
一方、育成就労施工による企業へのデメリットは、以下のとおりです。
- 以前より費用が高くなる
- 転職や退職までの期間が短くなる可能性がある
- 不法就労助長罪が厳しくなる
デメリットとしてまず挙げられるのは、採用にかかる費用が技能実習制度より高くなる可能性があることです。これは、外国人労働者が来日前に現地の送り出し機関へ支払う手数料などを、受け入れ企業が一部負担する仕組みが検討されているためです。
また、人材の定着に関するリスクもあります。技能実習制度では原則として認められていなかった「転籍」が、育成就労制度では本人の希望で可能になります。
同じ企業で1年以上働くなどの一定の条件を満たせば転職できるため、企業側は育成した人材が、より良い条件を求めて早めに辞めてしまう可能性を考慮し、労働環境の整備に努める必要が出てきます。
さらに、不法就労助長罪が厳罰化される点も企業にとって重要な変更点です。転籍が可能になることで、悪質なブローカーが介入するのを防ぐため、罰則が「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に強化される予定です。
この罪は外国人本人ではなく、受け入れ企業などが対象となり、意図的でなくても過失によって罰せられる場合があるため、これまで以上に適切な雇用管理が求められます。
育成就労と技能実習における違いのまとめ

この記事では、育成就労と技能実習における違いについて解説してきました。
技能実習制度は、「国際貢献」という目的と「国内の人手不足を補う」という実態のずれや、人権侵害問題により廃止され、2027年から育成就労制度が開始されます。育成就労制度は、人手不足分野での人材確保と育成を目的とし、3年間で特定技能1号レベルの人材育成を目指します。
大きな変更点として、原則不可能だった転籍が一定条件下で可能になるほか、就労前の日本語能力としてN5レベルが求められます。企業にとっては、高い日本語能力を持つ人材を確保できるメリットがある一方、人材流出、採用コスト増加、不法就労助長罪の厳罰化といったデメリットも存在します。
外国人材受け入れに関するルールは大きく変わるため、企業は新制度の内容を正確に把握し、労働環境の整備や採用計画の見直しなど、スムーズな対応のための準備が重要です。