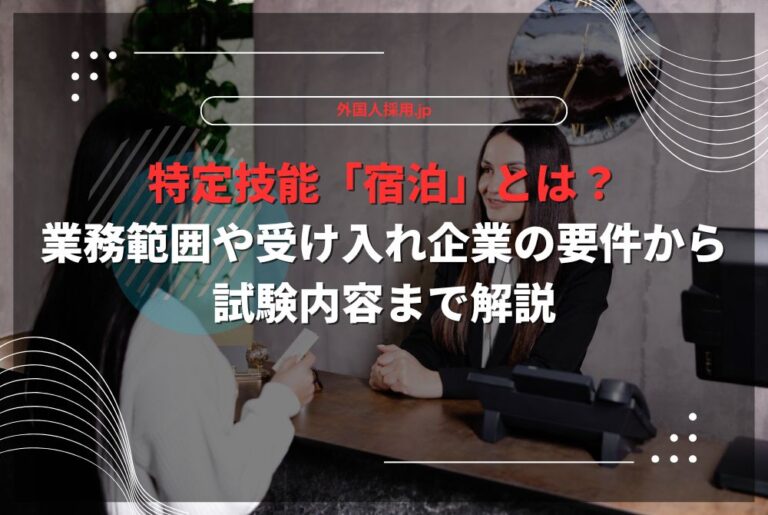人手不足が深刻化する宿泊業界において、即戦力となる外国人材の活用が注目されています。
そのなかでも「特定技能・宿泊」は、フロント業務から館内サービスまで幅広い業務を担えるため、採用企業側にも大きなメリットがある在留資格の一つです。
本記事では、特定技能「宿泊」の業務範囲や受け入れ要件、試験内容など、導入を検討する企業が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能「宿泊」とは?

特定技能「宿泊」は、日本の宿泊業界における深刻な人手不足を背景に、即戦力として勤務できる外国人材を受け入れるために2019年から開始された在留資格の一つです。
在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されており、現時点で広く活用されているのは「1号」です。1号では最長5年間の在留が認められ、家族の帯同は原則として認められていません。
一方、2023年には宿泊分野でも「特定技能2号」が適用対象となり、より高度な能力を有する外国人に対しては在留期間の上限が撤廃され、家族の帯同や永住申請の可能性も開かれるようになりました。
特定技能「宿泊」は単なる労働力の補充にとどまらず、サービス業の質を維持・向上させるための戦略的な制度として位置づけられています。
外国人材の採用にあたっては、制度の内容や要件をしっかりと理解し、適切な支援体制を整える必要があります。
特定技能「宿泊」の業務範囲

特定技能「宿泊」を保有する外国人材は、ホテル・旅館などで「主たる業務」「付随的な単純作業」に分かれた以下の業務に従事できます。
| 区分 | 業務内容 |
|---|---|
| 主たる業務 | ・フロント業務:チェックイン・チェックアウト、観光案内、ツアー手配など
・企画・広報業務:キャンペーン立案、チラシ作成、HP・SNSでの情報発信など ・接客業務:館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応など ・レストランサービス:配膳・片付け、注文対応、簡単な調理補助・盛り付けなど |
| 付随的な単純作業 | 荷物運搬、客室清掃、ベッドメイキング、レストラン配膳、館内販売、備品点検など |
上記の「付随的な単純作業」を主たる業務とすることは認められておらず、必ず主業務とのバランスを保つ必要があります。また、特定技能「宿泊」では、以下の従事できない業務や施設が定められています。
風俗営業法で定められている「接待」行為(例:スナックなどでの歓楽的接客)
- ラブホテルなど、風営法第2条第6項第4号に規定される施設ではの勤務
- 特定技能「宿泊」で外国人材を採用する場合は、上記の業務範囲を正確に把握しておく必要があります。
宿泊分野の特定技能の取得要件

特定技能「宿泊」には1号と2号の区分があり、それぞれで取得要件が異なります。
ここでは、特定技能「宿泊」1号および2号の取得要件について解説します。
|
特定技能1号「宿泊」の取得要件
特定技能「宿泊」分野の1号(特定技能1号)を取得するためには、以下の2つの方法のいずれかを選択する必要があります。
| 【①技能実習2号からの移行ルート(試験・日本語試験が免除)】 技能実習制度を通じて宿泊分野の技能実習2号を良好に修了していれば、その後特定技能1号に移行する際に、技能試験および日本語試験が免除されます。 ただし、実習で携わった職種・作業内容が、特定技能1号で求められる業務と一致している必要があります。 |
| 【②試験合格ルート(技能試験+日本語能力試験)】 実習からの移行が難しい場合、以下の試験を受けて合格すれば1号を取得できます。宿泊分野特定技能1号評価試験 日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic(A2レベル相当)日本語能力試験の概要は以下の通りです。JLPT N4:初歩的な日本語を日常で読み書き・会話できるレベル JFT-Basic(A2相当):生活・業務に必要な基本的日本語能力を測る試験で、合格ライン(A2)に達するには250点満点中およそ200点が必要 |
技能実習2号を良好に終えている場合は、試験不要でスムーズに特定技能1号にステップアップ可能で、余計な負担が軽減されます。
一方で、試験ルートは実習経由ではないルートや外国人にとってはスタンダードな方法で、日本語力と業務知識を示す必要があります。
企業側としては、外国人材の経歴や状況に応じて最適なサポートをする取り組みが大切です。
特定技能2号「宿泊」の取得要件
特定技能2号「宿泊」は、宿泊業における高度な技能とマネジメント経験を備えた外国人材が対象となる上位の在留資格です。
取得にはおもに以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 実務経験の証明 | ・宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験が必要 |
| 評価試験の合格 | 「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格しておく必要がある |
| 受験資格の要件をクリアする | ・試験を受ける時点で満17歳以上(インドネシア籍は18歳以上)でなければならない
・日本国内受験の場合は合法な在留資格を保持している必要がある |
上記に加え、評価試験に合格し、実務経験を証明しても最終的には法務局での許可取得が必要である点にも注意が必要です。
特定技能1号から2号への移行方法を徹底解説!要件や試験内容も紹介
特定技能「宿泊」取得外国人を雇用する時の受け入れ企業の要件

特定技能「宿泊」取得外国人を雇用する時の受け入れ企業の要件は以下の通りです。
ここでは、上記の要件について解説します。
|
旅館・ホテル営業の許可を受けていること
特定技能「宿泊」の在留資格で外国人材を雇用する際、企業(宿泊施設)が満たしておくべき最も基本的な条件が、「旅館・ホテル営業の許可を取得していること」です。
旅館・ホテル営業の許可は、旅館業法第2条第2項に基づく正式な営業許可を指し、単に宿泊業を営んでいるだけでは認められません。
旅館業法第2条第2項の条文は以下の通りです。
この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
上記の条文に明記されているように、簡易宿所および下宿では旅館・ホテル営業の許可は取れないため、特定技能「宿泊」を保有する外国人材は採用できません。
また、風営法第2条第6項第4号に該当するラブホテルのような施設でも同様に採用不可となります。
外国人雇用における所定の基準を満たすこと
特定技能「宿泊」の外国人を雇用する企業は、外国人雇用における以下の所定の基準を満たす必要があります。
| 基準 | 概要 |
|---|---|
| 適正な雇用契約の締結 | 報酬や労働時間、有給休暇の付与などが日本人労働者に比べて不利益な内容であってはならない |
| 法令遵守体制の整備 | ・入管法・労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法・社会保険関連法令などに違反しない体制を整えなければならない
・報酬の支払いは銀行振込など記録が残る方法で行う必要がある |
| 支援体制・計画の適切さ | ・生活・職場・社会適応を支援する体制と計画(義務的支援)の整備が求められる
・自社で実施できない場合は、「登録支援機関」に委託可能 |
上記の要件を確実に遵守すれば、スムーズな在留資格申請とその後の定着促進が期待できます。
「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になること
特定技能「宿泊」の外国人を雇用する際、受け入れ企業(所属機関)および登録支援機関には、「宿泊分野特定技能協議会(以下、協議会)」への加入が義務づけられています。
加入のタイミングは、以前は受け入れ後4か月以内に加入すればよいものと定められていましたが、2024年6月15日以降は宿泊分野へ特定技能外国人を初めて受け入れる場合、在留資格申請の前に協議会加入を完了させることが必須となりました。
また、協議会加入後は以下の義務を遂行する必要があります。
- 制度の適正な運営と情報共有
- 特定技能外国人に関する最新情報の収集・提供
- 協議会からの調査・指導に対する協力義務
協議会加入後に必要な協力を怠ると、将来的に特定技能外国人の受入れ自体ができなくなるリスクもあるため、責任をもって対応する必要があります。
特定技能の協議会とは?加入要件や費用から分野別一覧までを紹介
四半期ごとの支援状況の届出をする
特定技能「宿泊」取得外国人を雇用する際の受け入れ企業は、1年ごとに以下の報告を行う必要があります。
- 支援の実施状況
- 報酬の支払状況
- 外国人の受け入れ状況
上記の報告を行うスケジュールと方法は以下の通りです。
| スケジュール | 対象年の翌年の4月1日~5月31日まで |
| 方法 | 郵送・窓口のほか、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用したオンライン提出も可能 |
この定期報告は2025年4月までは「四半期ごとの届出」が必要でしたが、2026年4月以降は「1年に1回」の年次届出に移行するように制度変更がされました。
詳細は出入国管理庁が公開している以下の資料を参考にしてください。
出典:定期届出 随時届出 – 特定技能外国人を雇用・支援するときは
出典:特定技能制度の定期届出の頻度変更に関する広報・周知用リーフレット(PDF)
特定技能外国人の住居確保ガイド|部屋の広さや責任の所在まで解説
特定技能人材受け入れ時の「事前ガイダンス」とは?内容や実施時間を解説
特定技能「宿泊」の試験内容

特定技能「宿泊」の試験は、1号と2号で内容が異なります。
ここでは、1号と2号の試験内容について解説します。
|
特定技能1号試験
特定技能1号「宿泊」を取得するためには、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。
技能試験と日本語試験の概要は以下の通りです。
| 試験 | 概要 |
|---|---|
| 技能試験(宿泊分野特定技能1号評価試験) | ・学科30問+実技6問によるCBT形式で、試験時間は60分
・業務に直結したフロント、接客、レストランサービス、安全衛生、広報企画などに関する問題が出題がされる |
| 日本語試験 | 以下のいずれかに合格していることが必要。
・日本語能力試験(JLPT)N4以上 ・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT‑Basic)においてA2レベル相当以上 |
また、1号試験には受験資格があり、これを満たしていなければ受験できません。
- 試験日時点で満17歳以上(インドネシア国籍の場合は満18歳以上)である
- 日本国内受験時は有効な在留資格が必要
受験資格を満たした上で、技能試験および日本語試験に合格すれば1号の資格を得られます。
特定技能2号試験
2号の試験の場合、まず受験資格に年齢・在留資格に加えて以下の内容を満たす「実務経験」が追加されます。
- 試験日前日までに、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント・企画・広報・接客・レストランサービスなどの業務に2年以上従事している
受験資格をすべて満たした上で受験できる試験内容は以下の通りです。
| 試験内容 | 概要 |
|---|---|
| 形式 | CBT(Computer Based Testing)方式で実施され、学科50問+実技20問、計70問、所要時間は60分 |
| 基準 | 学科・実技それぞれで65%以上の正答率 |
| 範囲 | ・学科試験では、フロント・企画・広報・接客・レストランサービスに関する知識のほか、安全衛生、マナー(身だしなみ、言葉遣い、立ち居振る舞い)、および管理・マネジメント業務に関する理解について出題
・実技試験では、フロント業務・接客・レストランサービスの現場対応力が問われ、「現場の判断力・応対スキル」が試される |
2号では受験資格に実務経験、試験内容に実技試験も追加されるため、1号よりも難易度の高いものとなっているのが特徴です。
特定技能「宿泊」のまとめ

特定技能「宿泊」は、日本の宿泊業界における深刻な人手不足を背景に、即戦力として活躍できる外国人材の受け入れを可能にする制度です。ホテルや旅館の現場で必要とされるフロント・接客・レストランサービス・企画広報など、幅広い業務を担えるため、現場の即戦力として期待が高まっています。
取得には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2段階があり、それぞれに応じた実務経験と試験への合格が必要です。特に2号においては、現場リーダーとしてのマネジメント力や指導経験が評価対象となるなど、高度な能力が求められます。
また、外国人材を受け入れる企業にとっては、制度の理解だけでなく、以下の所定の受け入れ要件を満たす必要があります。
- 旅館業法第2条第2項に基づく旅館・ホテル営業の許可を取得していること
- 外国人との雇用契約が日本人と同等以上の労働条件であること
- 支援計画を策定し、外国人への生活支援・日本語学習機会の提供を実施すること
- 申請前に「宿泊分野特定技能協議会」に構成員として加入していること
- 支援・活動状況などを年次ごとに届け出ること
上記の条件を満たし制度を適切に活用すれば、外国人材の安定した定着とサービス品質の維持・向上につながります。
今後の人材戦略として特定技能「宿泊」を導入する企業は、本記事を参考に制度の全体像を把握し、早めの準備と体制整備を進めていく必要があります。
制度理解が進めば、国際的な人材との共生を通じて、組織全体の活性化にもつながるでしょう。
本記事へのご質問・お問い合わせは以下のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。