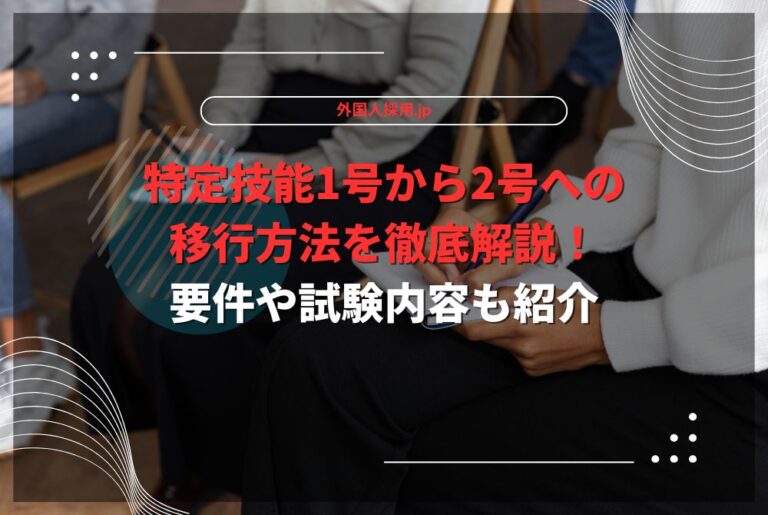特定技能1号から2号への移行を考えている企業や外国人の方々は、手続き、必要な条件、メリットについて多くの疑問や不安を感じていることでしょう。日本で長期的に活躍し、安定した雇用を目指す上で、この移行は非常に重要です。
この記事では、特定技能1号から2号への移行理由や1号との違い、必要な実務経験、技能試験、日本語能力、移行可能な分野について詳しく解説します。
この記事を読むことで、移行の全体像が明確になり、外国人材の日本での長期的な活躍と企業の安定雇用を円滑に進めるための具体的な方法が理解できるでしょう。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能1号から2号への移行を試みる理由

2019年の特定技能制度創設以降、特定技能1号の在留資格を持つ外国人材は増加しています。近年、特定技能1号から2号への移行を目指す企業や外国人材が増えていますが、その主な理由は、日本での長期滞在と企業の安定的な人材確保です。
特定技能1号の在留資格では、日本に滞在できる期間が最長5年と定められているため、それ以上の滞在を希望する場合は、在留期間に上限のない特定技能2号への移行が必要になります。特定技能2号を取得すれば、在留期間の制限なく日本に滞在できるため、大きな魅力となっています。
特定技能制度は2019年に始まったため、制度開始当初に特定技能1号を取得した外国人材は、2025年には在留期間の上限を迎えます。そのため、日本での在留を希望する外国人材と、長期的な人材確保を目指す企業を中心に、特定技能2号への移行を目指す動きが広がっています。
企業が特定技能2号への移行を支援することで、外国人材に長期的に自社で働いてもらうことが期待でき、安定的な人材確保につながります。そのため、雇用している外国人材の特定技能2号の取得を積極的に支援する企業が増えています。
特定技能1号と2号の違い一覧

特定技能は、特定の分野で人手不足を解消するため、すぐに活躍できる外国人を受け入れる制度として作られました。この制度には「1号」と「2号」の2つの区分があります。どちらも特定技能という同じ枠組みですが、在留資格の定義、滞在条件、求められる技能レベルなど、さまざまな点で違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留資格の定義 | ある程度の知識や経験が必要な技能を要する業務に従事するための資格 | 熟練した技能を要する業務に従事するための資格 |
| 2024年12月末時点の在留者数 | 283,634名 | 832名 |
| 在留可能な期間の上限 | 最長5年 | 制限なし |
| 技能水準・実務経験 | 技能試験に合格する必要がある | 1号よりも高度な技能試験の合格と、一定の実務経験が求められる |
| 日本語能力水準 | 日本語能力試験N4レベル相当の試験に合格 | 原則なし |
| 受入れ機関等による支援の要否 | 必要 | 不要 |
| 家族帯同の可否 | 原則として不可 | 配偶者および子どもの帯同が可能 |
| 在留資格「永住者」取得の可能性 | 基本的に不可能 | 取得できる可能性あり |
| 技能試験の実施頻度 | 比較的高い頻度で実施 | 実施頻度は低い |
このように、特定技能2号は在留条件の面で特定技能1号よりも有利な点が多いと言えます。特に、滞在期間に制限がないことは大きなメリットであり、家族を呼び寄せることができる点や、永住権取得の可能性が開ける点も、2号の魅力を高めています。
ただし、特定技能2号の取得は1号に比べて難しいと考えられています。2号の資格を得るには、1号以上の高度な技能試験に合格する必要があり、さらに一定期間の実務経験も必要となるためです。
特定技能1号から2号への移行要件

外国人材が日本で長く活躍しキャリアを積み、企業が安定的に人材を確保することを考えると、特定技能1号から2号への移行は非常に重要です。
特定技能2号は、1号と比較して在留期間に制限がなく、家族を呼び寄せたり、永住権を申請できる可能性が開けるなど、在留資格としてのメリットが大きいです。しかし、2号の取得には、より高度な技能と実務経験が求められ、一定の条件を満たす必要があります。
以下は、特定技能1号から2号への移行に必要な主な条件です。
| 特定技能1号から2号への移行要件 |
|
実務経験が必要
特定技能2号を取得するには、1号で求められる「相当程度の知識または経験」に加え、より高度な熟練した技能が不可欠です。具体的には、現場で自らの判断に基づき専門的な作業を遂行できる能力、または他の作業員を指導・監督する立場での実務経験が求められます。
特定技能2号では「管理者レベルの実務経験」が重視され、現場で自律的に高度な専門的・技術的業務を遂行できる、あるいは監督者として業務全体を統括し、熟練した技能を発揮できるレベルが期待されます。
作業員の指導・監督経験が前提となる点も重要です。通常、特定技能2号の資格取得には2〜3年の実務経験が必要とされますが、必要な期間は分野によって異なります。
例えば、ビルクリーニング分野では、建物の清掃業務において複数の作業員を指導し、現場管理を行う者として2年以上の実務経験が必要です。また、建設分野においては、建設キャリアアップシステム能力評価基準レベル3に相当する班長として、半年から3年程度の就業年数、または同基準がない場合は班長として3年以上の就業経験が要件となります。
技能試験の合格が必要
特定技能2号の資格を得るには、それぞれの分野で定められた技能試験に合格する必要があります。試験の種類は「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級(分野によっては2級)」のいずれかです。
試験では、各分野における専門的な知識や熟練したスキルが問われます。たとえば、建設分野では複数の作業員を指導しながら作業し、工程を管理する能力、自動車整備分野では作業内容を判断し、他の整備士を適切に指導する能力などが評価されます。
技能検定は実務経験の年数が長く必要となるため、2号評価試験の方が現実的な選択肢となる場合が多いでしょう。
分野によっては日本語試験も必要
特定技能2号の資格取得に際し、公式には日本語能力試験のレベルは必須とされていません。しかし、実際の技能評価試験は日本語による記述形式で行われるため、一定以上の日本語運用能力が必要です。
目安としては、日本語能力試験(JLPT)N2レベル相当が望ましいとされています。これは、特定技能2号取得者が責任の重い管理業務を担う可能性があり、業務や日常生活で円滑に日本語でコミュニケーションを取る能力が不可欠だからです。
2025年7月現在で、日本語能力試験(JLPT)N3相当以上の能力が求められるケースは以下のとおりです。
- 水産業界
- 飲食サービス業
業種によっては、上記の他に独自の試験や資格が求められる場合があります。
- 製造業:ビジネス・キャリア検定
- 航空整備:航空従事者技能証明
特定技能2号への移行手続きは煩雑で、準備すべき書類も多岐にわたるため、専門知識を持つ行政書士に相談するのがおすすめです。
特定技能1号から2号への移行方法

特定技能1号から2号への移行は、2号が設けられている職種に限られます。例えば、介護の分野では現在、特定技能2号の制度はありません。移行するには、より高いレベルである2号の基準を満たす必要があります。
移行のルートとしては、主に以下の2つのケースが考えられます。
- 同じ職場でステップアップする場合(転職なし)
- 新しいステージへ挑戦する場合(転職あり)
同じ職場でステップアップする場合、特定技能1号として現在働いている会社で経験を積み、特定技能2号の要件を満たした上で、在留資格変更許可申請を行います。
特定技能の在留資格は技能実習とは異なり、転職が可能です。転職する場合、まず転職先の企業が特定技能外国人を受け入れる準備を行う必要があります。その後、外国籍の方が在留資格変更許可申請を行い、許可を得てから新しい会社で働くことになります。
いずれの場合も、必要な要件を満たして適切な書類を準備し、定められた手順に従って申請を進めることが重要です。
準備する書類は、以下のとおりです。
| 企業が準備する書類 | 外国人が準備する書類 |
|---|---|
|
|
特定技能2号の資格要件を満たした後、出入国在留管理局で在留資格の変更手続きを行います。原則として、本人が住んでいる地域を管轄する入管に申請しますが、場合によっては専門家が代わりに行うことも可能です。
申請のおおまかな流れは、以下の通りです。
- 要件の確認
- 書類の準備
- 入管へ申請
- 審査
- 許可
在留資格変更許可申請の審査には、通常2週間から1ヶ月程度かかると言われています。手続きが複雑なため、スムーズに申請を完了させるためには、在留資格申請に詳しい専門家に相談することも検討すると良いでしょう。
特定技能1号から2号へ移行時の試験内容

特定技能1号から2号へ移行するには、各分野特有のスキルを測る試験に合格することが必要です。特定技能2号は、より高度な専門知識と熟練した技術が求められるため、試験では各分野における深い理解と応用力が評価されます。
試験内容は分野によって異なり、例えば建設分野では現場での指導力や工程管理能力、自動車整備分野では作業判断力や指導力が問われます。飲食料品製造業では、作業員を指導し工程を管理する実務経験が重視されるなど、各分野で求められる経験や役割が試験に反映されます。
試験の詳細については、各分野の実施機関が提供する情報を確認してください。
また、日本語能力に関しては、特定技能2号の資格取得に必須となる公式な日本語能力試験のレベルは設定されていません。しかし、試験自体が日本語の記述式であるため、高度な日本語運用能力が必要です。目安としては、日本語能力試験N2レベル相当の日本語能力が求められると考えられます。
特定技能1号から2号へ移行可能な業界一覧

特定技能1号から2号への移行は、すべての分野で可能なわけではありません。2号への移行が認められているのは、特定された限られた分野のみです。2025年8月現在で特定技能2号の対象となっているのは、以下の11分野です。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能1号では介護分野も対象ですが、2号では対象外となっています。特定技能2号が設けられていない分野があるのは、主に2つの理由からです。
1つは、介護分野のように、他の適切な在留資格が存在する場合です。介護分野では、特定技能1号から介護福祉士の国家資格を取得することで「在留資格『介護』」への移行が可能なため、特定技能2号は不要と判断されています。
もう1つの理由は、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業など、比較的最近追加された分野で、まだ制度が整っていないためです。これらの分野については、政府が公開している情報に詳細が記載されていない場合もあるため、別途確認が必要です。
詳細や各分野の具体的な要件は、こちらをご覧ください。
特定技能外国人は派遣雇用できる?受け入れる時の要件や注意点を解説
特定技能1号から2号への移行のまとめ

この記事では、特定技能1号から2号への移行について解説してきました。
特定技能1号から2号への移行は、外国人材が長期にわたり活躍し、企業が安定的に人材を確保するために重要な機会となります。特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、2号には在留期間の上限がなく、家族を日本に呼んで一緒に暮らすことも可能です。さらに、将来的に永住権を取得できる可能性も開かれるため、外国人材にとって大きなメリットがあります。
企業が2号への移行を支援することは、長期的な人材の確保と雇用の安定につながります。ただし、2号の取得には、1号よりも高い技能と実務経験が求められます。現場で自分で判断して専門的な作業ができる能力や、他の作業員を指導・監督できる能力が必要となり、通常2〜3年の実務経験が目安です。
2号への移行が可能な分野は限られており、ビルクリーニングや建設業など、特定の11分野に限られます。介護分野や、最近追加された自動車運送業などは対象外となるため、注意が必要です。
移行の手続きは、要件の確認から始まり、企業と外国人本人が多くの書類を準備して、出入国在留管理局に申請することが必要です。手続きは複雑であるため、行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
この記事の内容を参考に、必要な要件や手続きを正確に進め、特定技能外国人のスムーズな雇用と、企業の安定的な成長を実現しましょう。