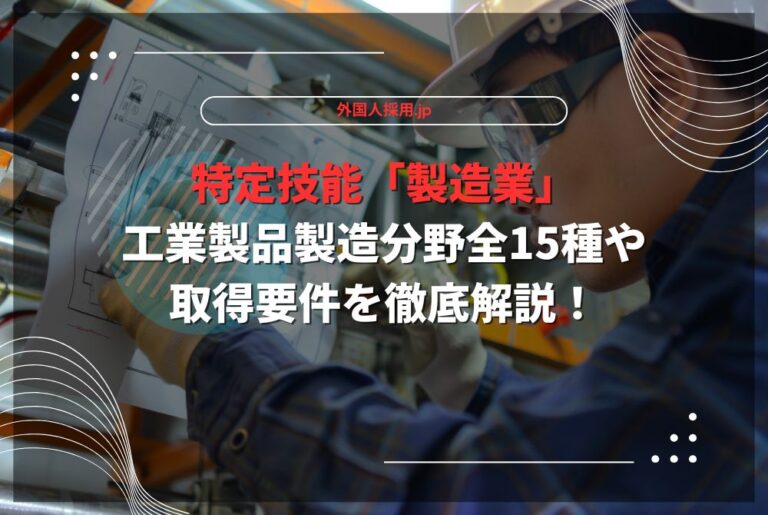日本の製造業で人手不足が深刻化し、優秀な人材の確保は喫緊の経営課題です。複雑な制度や最新の法改正への対応に頭を悩ませていませんか?
この記事では、特定技能「製造業」の中でも特に活用が進む工業製品製造分野に焦点を当て、その概要や受け入れ企業が満たすべき具体的な要件をわかりやすく解説します。特に、令和7年3月11日に閣議決定された運用方針の変更点についても詳述します。
この記事を読むことで、外国人材をスムーズに受け入れ、事業の生産性向上と競争力強化を実現するためのヒントを得られるでしょう。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能「製造業」工業製品製造分野の最新動向

人手不足が深刻な日本において、特定技能制度は外国人材の活用を促進するために導入されました。なかでも工業製品製造業は、その活用が活発な分野の一つとして、企業の戦略上重要な位置を占めています。この分野における特定技能外国人の受け入れ数は、業界全体の約20%に達しており、受入数としては全体で2番目に多い状況です。
受け入れ人数の推移を見ると、令和5年12月末から令和6年12月末にかけて、約4万人から約4.5万人へと増加しています。この数字は、工業製品製造業における特定技能外国人の雇用が拡大傾向にあることを示唆しており、今後もこの傾向が続くと予想されます。
特筆すべき点として、2022年5月に制度の再編が行われました。従来、個別に運用されていた「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野が統合され、「工業製品製造業分野」という新たな枠組みに再編されたのです。この統合によって、対象となる業種や業務範囲が大幅に広がり、制度の適用範囲が拡大しました。
このように規模を拡大し続ける特定技能制度を有効活用することは、工業製品製造業に携わる企業にとって、喫緊の課題と言えるでしょう。企業は、単なる人手不足の解消策として捉えるだけでなく、生産性向上や競争力強化といったより戦略的な視点から、この制度を活用していくことが求められています。
特定技能「製造業」工業製品製造分野全15種

特定技能制度における「工業製品製造分野」は、2022年5月に「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野が統合され、「工業製品製造業分野」へと名称変更されました。
この統合により、新たな業種や業務区分が追加され、対象範囲が大幅に拡大しています。現在、この分野は特定技能外国人受け入れ数で業界全体の約20%を占め、全体で2番目に多い分野となっています。
以下に、工業製品製造分野に含まれる全15業種について解説します。
| 項目 | 系統 |
|---|---|
| 鉄鋼業 | 金属・建材系 |
| 金属製サッシ・ドア製造業 | 金属・建材系 |
| コンクリート製品製造業 | 金属・建材系 |
| 金属製品塗装業 | 金属・建材系 |
| 金属表面処理業 | 金属・建材系 |
| プラスチック製品製造業 | 素材・加工系 |
| 紙製造・紙器・段ボール箱製造業 | 素材・加工系 |
| 梱(こん)包業 | 素材・加工系 |
| RPF製造業 | 素材・加工系 |
| 陶磁器製品製造業 | 素材・加工系 |
| 素形材産業 | 機械・産業系 |
| 産業機械製造業 | 機械・産業系 |
| 電気・電子情報関連産業 | 機械・産業系 |
| 繊維業 | 機械・産業系 |
| 印刷・同関連業 | 機械・産業系 |
主に製造業のこの分野は、以下の3つに分かれることを知っておきましょう。
| 製造業の3つの分野 |
|
1. 鉄鋼業
鉄鋼業は、金属・建材系といった分野に分類されます。具体的には、広幅帯鋼、帯鋼、鋼板といった素材を切断(溶断も含む)する事業が該当します。主な対象業種としては、以下のようなものが挙げられます。
- シャースリット業
- 鉄鋼シャーリング業
- 鉄鋼スリット業
2. 金属製サッシ・ドア製造業
金属製サッシ・ドア製造業は、一般的に金属・建材系の産業に分類されます。具体的には、建築物に使われる金属製のサッシやドアを作る事業のことです。主な対象業種として、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅用・ビル用アルミサッシ製造業
- アルミドア製造業
3. コンクリート製品製造業
コンクリート製品製造業は、金属・建材系の分野に区分されます。具体的には、コンクリート製の管、柱、くい、ブロックなどを製造する事業が該当します。ただし、生コンクリートや気泡コンクリート製品の製造は含まれません。
主な業種には、以下のようなものが挙げられます。
- コンクリートパイル・ポール・管製造業
- 空洞・土木用ブロック製造業
- 道路用・建築用コンクリート製品製造業
- テラゾー製造業
- プレストレストコンクリート製品製造業(まくら木、はり、けたなど)
4. 金属製品塗装業
金属製品塗装業は、金属・建材系の分野に属します。具体的には、金属製品にエナメルやラッカーなどの塗料を施す事業が該当します。ただし、伝統的な漆塗りや看板のペンキ塗装は含まれません。代表例として、金属製品へのエナメル塗装業やラッカー塗装業が挙げられます。
5. 金属表面処理業
金属表面処理業は、金属や建材に関わる事業分野です。具体的には、金属への接着や研磨、アルマイト処理などを手がける事業者が該当します。ただし、表面処理された鋼材そのものを製造する事業は含まれません。例えば、アルミニウムの陽極酸化処理業などが該当します。
6. プラスチック製品製造業
プラスチック製品製造業界は、素材・加工系に大別されます。特定技能外国人材が従事できる職務範囲は法律で厳格に定められており、以下の3つのカテゴリーに限定されます。
- 圧縮成形・射出成形・インフレーション成形・ブロー成形など、成形技能を要する業務
- 手積み積層成形(強化プラスチック成形)の技能を要する業務
- 電気めっき・溶融亜鉛めっき・陽極酸化処理など、金属表面処理の技能を要する業務
これらのカテゴリーに該当しない業務では、特定技能外国人の受け入れは認められないので、注意してください。
7. 紙製造・紙器・段ボール箱製造業
紙の製造、紙器、段ボール箱の製造業は、おおまかに言うと素材や加工に関わる分野に位置づけられます。この分野には、以下の5つのタイプが含まれます。
- 洋紙製造業
- 板紙製造業
- 紙製容器製造業
- 紙製品製造業
- その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
8. 梱(こん)包業
梱包業は、素材・加工系の産業区分におおまかに分類されます。具体的には、物品を運送する際の荷造りや梱包作業を代行する事業が該当します。さらに、船舶輸送に適した設備を用いて、多様な包装資材を加工し、梱包容器を組み立てて工業製品を保護する外装を施す事業も含まれます。
事業の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 荷造業
- 貨物梱包業
- 工業製品組立梱包業
- 輸出梱包業
9. RPF製造業
RPF製造業は、リサイクル素材の活用を目的とした、素材・加工系の分野に位置づけられます。古紙や廃プラスチックを回収し、圧縮成形などの加工を施すことで、再生燃料(RPF)を製造する事業が、この分野の代表的な例です。
10. 陶磁器製品製造業
陶磁器製品製造業は、主に素材や加工に関わる領域に位置づけられ、陶磁器の置物や食卓・厨房用品などを製造する事業です。具体的には、以下のような活動が該当します。
- 陶磁器製の花瓶・ランプ台・食器・厨房器具の製造
- 陶磁器製のこんろや土鍋の製造
11. 素形材産業
素形材産業は、その系統から機械・産業分野に位置づけられます。この領域は、鉄鋼や非鉄金属といった素材を基にした部材の製造・加工を手がける事業者が中心です。主な事業区分として、以下の3つが挙げられます。
- 鉄素形材製造業
- 非鉄金属素形材製造業
- 金属素形材製品製造業
鉄素形材製造業では、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鋼、鍛工品、鍛鋼品などが扱われます。
非鉄金属素形材製造業では、銅・同合金鋳物、非鉄金属鋳物(ダイカストを除く)、アルミニウム・同合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト、非鉄金属鍛造品などが扱われます。金属素形材製品製造業では、アルミニウム・同合金プレス製品、金属プレス製品(アルミニウム・同合金を除く)、粉末冶金製品などが製造されています。
12. 産業機械製造業
産業機械製造業は、広範な機械・産業分野に位置づけられます。この領域は、ボルトやナットなどの部品製造から、各種機械・機器の組立までが対象で、その範囲は以下の通りです。
- 機械刃物製造業
- ボルト・ナット・ねじ製造業
- はん用機械器具製造業(消火器具や素形材産業を除く)
- 生産用機械器具製造業(素形材産業を除く)
- 一部の業務用機械器具製造業
- 事務用・サービス用・娯楽用機械製造業
- 計測器・分析装置・光学機器などの製造業
13. 電気・電子情報関連産業
電気・電子情報関連産業は、分類上、機械・産業系に属します。この領域は、家電から産業機械、医療機器まで広範な電気・電子機器の製造が対象で、具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 発電機・電動機などの回転電気機械製造業
- 変圧器、電力制御装置、配線器具などの製造
- 電気溶接機、電熱装置、民生用機器の製造
- 空調・衣料衛生機器・照明器具・電池製造
- 医療用や産業用の電子応用機器製造
- 電気計測器、工業計器、医療計測器の製造
14. 繊維業
繊維産業は、一般的に機械・産業分野に分類されます。その事業領域は広範に及びますが、代表的なものとして、糸・布・不織布などの繊維製品の製造など、以下の業種が挙げられます。
- 製糸業、化学繊維・炭素繊維の製造
- 織物(綿・麻・細幅織物)製造
- ニット、レースの染色や整理加工
- フェルト、不織布、防水布などの製造
- カーペットやタオル、刺繍品の製造
繊維産業は、新たに設けられた10の業務分野に含まれることになりました。これらの新規追加分野については当面の間、特定技能1号の資格を持つ外国人のみ受け入れが認められています。
さらに、技能実習制度には「繊維・衣服関係等」という職種群(21職種38作業)が存在し、この職種群で技能を習得した人々が、特定技能1号へ移行することも認められています。
15. 印刷・同関連業
印刷・同関連業は、一般的に機械・産業分野に区分されます。この業種は、紙やその他素材への印刷・加工・製本などの業務が対象で、主に以下の7つの事業活動が含まれます。
- 紙へのオフセット印刷業
- その他の紙への印刷業(とっ版・スクリーン印刷など)
- 紙以外への印刷業(プラスチック、金属、布など)
- 製版業(各種版の製造や写真植字など)
- 製本業(印刷と分離された製本作業)
- 印刷物加工業(光沢、裁断、箔押しなど)
- 印刷関連サービス業(校正刷りや刷版研磨などの補助業務)
上記のように、製造業は広範囲にわたる業種で構成されており、労働力不足の解消と並行して、生産性の向上や競争力の強化が企業に求められています。
特定技能外国人は派遣雇用できる?受け入れる時の要件や注意点を解説
特定技能「製造業」工業製品製造分野の取得要件

特定技能「製造業」の在留資格を取得して日本で働くには、外国人の方と受け入れ企業が、それぞれ定められた基準を満たす必要があります。特定技能には「1号」と「2号」の区分があり、求められる技能レベル、在留期間、家族の帯同の可否などが異なります。
特定技能1号は、基礎的な知識や技能が必要な資格で、最長5年在留できますが、原則として家族の帯同は認められていません。
ここでは、以下の見出しで解説します。
| 特定技能「製造業」工業製品製造分野の取得要件 |
|
特定技能1号「製造業」の取得要件
特定技能1号は、製造業で即戦力として働くために必要な基本的な知識や技能、日本語能力を持つ外国人のための在留資格です。特定技能1号の主な要件は以下の通りです。
| 項目 | 特定技能1号の要件 |
|---|---|
| 技能レベル | ある程度の知識・経験 |
| 在留期間 | 1年以内の期間で更新(最長5年まで) |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 |
| 技能試験 | それぞれの分野の特定技能1号評価試験に合格 |
| 日本語能力試験 | 一定レベル以上(日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)、技能実習2号をきちんと修了した場合など) |
| 実務経験 | 不要 |
特定技能1号「製造業」の在留資格を取得するには、「試験ルート」と「技能実習ルート」の2つの方法があります。
試験ルートでは、日本語と専門的な技能の両方について、国が定めた試験に合格する必要があります。日本語能力試験としては、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかに合格する必要があります。
専門技能試験としては、製造分野特定技能1号評価試験(学科と実技)に合格する必要があります。このルートでは、技能評価試験と日本語試験に合格した後、雇用契約を結び、在留資格を申請します。
一方、技能実習制度を利用することも、特定技能1号「製造業」の在留資格を得るための方法の一つです。一定の条件を満たせば、技能試験や日本語試験が免除されるため、より容易に移行できる可能性があります。
その条件としては、技能実習2号をきちんと修了していること、具体的には、実習計画を2年10ヶ月以上終え、技能検定3級またはそれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、そして技能実習生に関する評価調書が提出できることが必要です。
また、技能実習で行った仕事の内容と、特定技能1号で行う業務が関連している必要があります。このルートでは、技能実習2号をきちんと修了した後、雇用契約を結び、在留資格変更を申請します。
特定技能2号「製造業」の取得要件
特定技能2号は、高度なスキルを持つ外国人向けの、より専門的な在留資格です。現在、この資格が認められているのは、機械金属加工、電気電子機器組み立て、金属表面処理の分野に限られています。特定技能2号を取得するための主な条件は以下の通りです。
| 項目 | 特定技能2号の要件 |
|---|---|
| スキルレベル | 熟練レベル |
| 在留期間 | 3年、1年、または6ヶ月ごとに更新可能(更新回数に制限なし) |
| 家族の同伴 | 一定の条件を満たせば、配偶者と子供の同伴が認められる |
| 対象業務分野 | 機械金属加工、電気電子機器組立、金属表面処理 |
| スキル試験 | 次のいずれかの方法で、必要な資格を取得・合格する必要があります。
|
| 日本語能力試験 | 不要 |
| 実務経験 | 日本国内での3年以上の実務経験 |
製造業における特定技能2号の取得ルートは大きく分けて2通りあり、それぞれのルートで定められたすべての条件を満たす必要があります。
1つは、特定技能1号からの移行です。このルートは、まず特定技能1号として製造現場で経験を積み、その後、より高度な専門性を目指す一般的な方法です。このルートでは、日本の企業の製造現場で3年以上の実務経験が必要となり、機械金属加工、電気電子機器組み立て、金属表面処理の分野で定められた特定技能2号の評価試験に合格する必要があります。
加えて、ビジネス・キャリア検定3級の合格も求められます。特定技能1号としての就労経験を経て、特定技能2号試験に合格後、在留資格の変更を申請します。
もう1つは、特定技能1号を経由しない取得ルートです。これは、すでに国内外で高度なスキルと実務経験を持つ人材を対象としており、特定技能1号の資格を経由せずに直接特定技能2号を目指すものです。このルートでも、日本国内の企業の製造現場で3年以上の実務経験が必須です。さらに、日本の国家資格である技能検定1級の合格が必須となります。
これらの条件を満たすことで、外国籍の人材は特定技能「製造業」の在留資格を取得し、日本の製造業の現場で活躍することが可能になります。
特定技能「製造業」取得外国人受け入れ企業の満たすべき要件

特定技能「製造業」の在留資格を持つ外国人材を受け入れる企業は、法令遵守と外国人材の権利保護を徹底し、日本での円滑な社会生活を支援する義務を負います。そのため、経済産業省が定める複数の要件を満たすことが必要です。
まず、企業は経済産業省が公開する「対象産業分類リスト」に掲載された事業所であることが求められます。これは、企業が製造業の特定の分野に属し、継続的に事業を行っていることの証明となります。原則として、受け入れ企業は自社で所有する原材料を用いて製品を製造し、出荷する必要があります。この規定は、企業が主体的に製造プロセスを管理していることを確認するためのものです。
さらに、経済産業省が組織する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入も必須です。協議会への参加は、制度の適切な運用と情報共有に貢献し、業界全体のレベルアップに繋がります。これらの要件を遵守することで、外国人材との良好な関係を築き、長期的な雇用を促進することが期待されます。
特定技能「製造業」の外国人材受入れは、企業の成長戦略に貢献する可能性を秘めています。しかし、そのためには、法令遵守と適切な支援体制の構築が不可欠です。これらの要件をしっかりと理解し、適切な対応を行うことで、企業と外国人材双方にとって有益な関係を築き、持続可能な成長を実現することが可能となります。
令和7年3月|特定技能の制度運用に変更点あり!
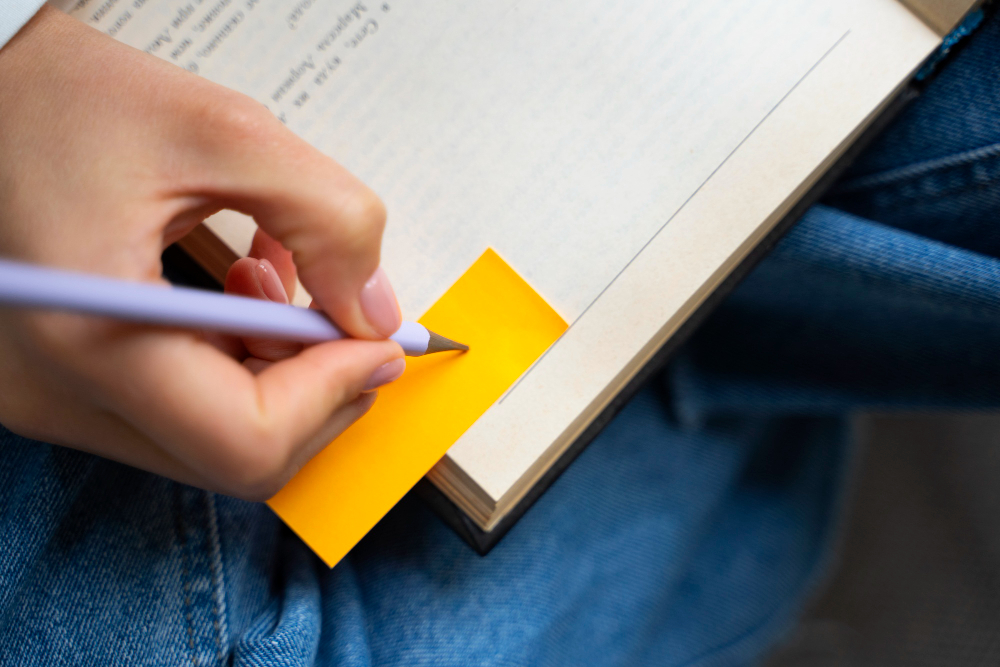
令和7年3月11日の閣議決定により、特定技能制度の既存3分野(介護、工業製品製造業、外食業)の運用方針が改正されました。背景には、人手不足への対応を強化する必要性が高まったことがあります。
工業製品製造業分野では、特定技能外国人の受入れを推進する民間団体が設立され、受入れ機関は加入が必須となります。各企業は、介護分野での訪問サービス対応準備、工業製品製造業分野での団体加入検討、外食業分野での旅館・ホテルでの人材活用検討が必要です。
特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)
特定技能「製造業」工業製品製造分野のまとめ

この記事では、特定技能「製造業」工業製品製造分野について解説してきました。
日本の製造業は深刻な人手不足に直面しており、「特定技能」制度は、貴重な即戦力となる外国人材を確保する上で不可欠な手段です。特に工業製品製造業分野では、特定技能外国人の受け入れが活発で、企業戦略においてその活用が急務となっています。この分野は2022年5月に再編され、「工業製品製造業分野」として鉄鋼業から印刷業まで幅広い業種が対象となりました。
特定技能外国人材を受け入れるには、対象分野での事業継続、自社所有の原材料使用が原則として求められます。また、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への参加が必須です。さらに、令和7年3月11日の制度改正により、受け入れを推進する民間団体への加入も義務付けられます。
特定技能制度の活用は、単なる労働力不足の解消にとどまらず、生産性向上や競争力強化にもつながる可能性があります。そのためには、法令遵守を徹底し、外国人材が安心して働ける環境と適切な支援体制を構築することが不可欠です。最新の制度変更に迅速に対応し、必要な体制を整備することで、企業は外国人材とともに持続的な成長を遂げられるでしょう。