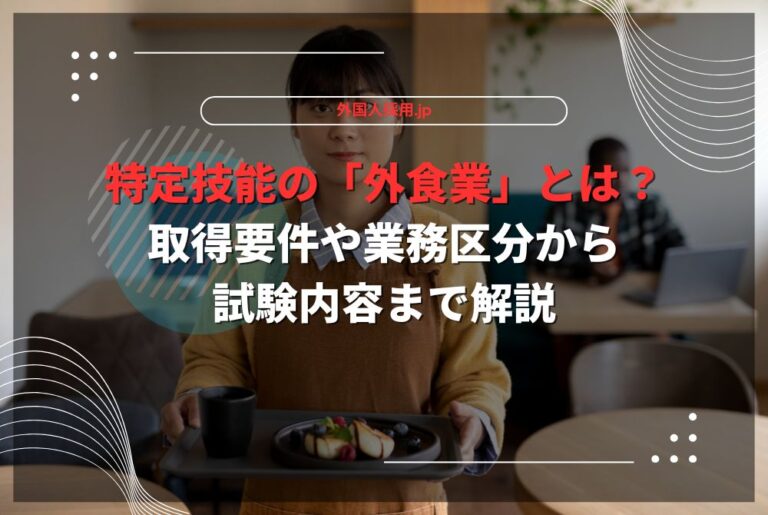日本の外食産業は慢性的な人手不足に悩まされており、新型コロナウイルス感染症の影響でその状況は深刻化しています。求人倍率も高く、人材確保にお困りの企業も多いことでしょう。
この記事では、特定技能「外食業」で外国人が従事できる業務や取得要件、企業が満たすべき基準、雇用までの流れ、注意点などを網羅的に説明します。この記事を通じて、特定技能外国人材を活用し、企業の成長を実現するためのヒントを得てください。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能「外食業」とは?

外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」が必要です。就労ビザにはさまざまな種類がありますが、その一つとして「特定技能」という制度があり、外食業はその対象分野となっています。
「特定技能」は、日本が抱える深刻な労働力不足を解消するために、2019年に設けられた在留資格です。特に外食産業においては、以前から人手不足が課題となっていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う営業時間の短縮などが原因で、さらに労働者が減少しました。
需要が回復するにつれて、その人手不足はより深刻なものとなりました。この状況に対応するため、特定技能制度の対象分野に外食業が加えられたという背景があります。
特定技能「外食業」の在留資格を持つ外国籍の方は、飲食店における業務全般、およびそれに付随する業務に従事することが可能です。具体的には、レストランでの接客や、ラーメン店での調理スタッフなど、食品や飲料の調理、顧客対応、店舗管理といった幅広い業務が対象となります。
出入国在留管理庁|外食業分野における特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能「外食業」の業務範囲

特定技能「外食業」の在留資格を持つ外国籍の方は、外食産業におけるさまざまな業務に従事できます。この資格で認められている活動範囲は、外食業全般と定められています。
具体的には、以下の業務が該当します。
- 飲食物の調理
- 接客
- 店舗管理
特定技能「外食業」は、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比べて、外食業の範囲内であれば業務上の制約が少ない点が特徴です。そのため、日本人従業員が行う業務と近い内容に従事でき、アルバイト雇用とは異なり、継続的な育成や技能向上が見込まれる資格と言えます。
特定技能1号「外食業」の取得要件

特定技能「外食業」の在留資格で外国人を雇用するには、受け入れ企業と外国人本人の双方が、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。
ここでは、以下の見出しで解説します。
| 特定技能1号「外食業」の取得要件 |
|
受け入れ企業が満たすべき要件
外国人労働者を雇用する企業は、定められた要件を満たし、採用後の責任を果たす必要があります。
外国人を受け入れる基準は以下のとおりです。
- 雇用契約の妥当性
- 受け入れ機関の適格性
- 外国人労働者へのサポート体制
- 適切な支援計画の策定
外国人労働者を雇用する際、給与は同等の日本人労働者と同等以上で、労働時間や休日なども労働基準法に準拠した雇用契約が必要です。また、受け入れ機関は過去5年以内に出入国管理法や労働関連法規への重大な違反がないことが求められます。
外国人労働者に対しては、理解できる言語での相談対応や情報提供などのサポート体制を整え、難しい場合は登録支援機関への委託も可能です。さらに、入国後の生活オリエンテーションを含む支援計画を策定し、住居、銀行口座、公共サービス、医療、緊急連絡先などの情報提供を行う必要があります。
受け入れ企業の主な義務は、以下のとおりです。
- 雇用契約の履行
- 外国人労働者への適切な支援
- 出入国在留管理庁への報告
受け入れ企業は外国人労働者の雇用にあたって、雇用契約の履行や外国人労働者への適切な支援、出入国在留管理庁へ報告する義務を負います。これらの義務の遵守は、良好な関係構築と企業の発展に繋がります。
特定技能制度の適切な運用を目指し、各省庁が16分野ごとに協議会を設置しています。協議会は、構成員間の連携を深め、制度や関連情報の周知、法令遵守の推進を目的としています。特定技能ビザの申請を行う前に、2024年6月15日以降は協議会への加入手続きを完了させるようにしましょう。
本人が満たすべき要件
外国籍の方が特定技能「外食業」1号の在留資格を取得するには、以下のいずれかの方法で要件を満たす必要があります。
1つ目は、「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験(N4以上)」の両方に合格する方法です。外食業特定技能1号技能測定試験は、学科試験と実技試験で構成されており、外食分野の業務に必要なスキルと日本語能力が評価されます。日本語能力試験では、N4以上に合格することで、「基本的な日本語を理解できる」レベルに達していると判断されます。
2つ目の方法は、技能実習からの移行です。「技能実習2号を円満に修了」または「技能実習3号の実習計画を完了」した場合、特定技能1号への在留資格変更を申請できます。ただし、外食業への移行が認められるのは、「医療・福祉施設給食製造」の職種に限られます。
特定技能「外食業」の試験内容

外国人が特定技能「外食業」の在留資格を得るためには、原則として以下の2種類の試験に合格する必要があります。
- 外食業特定技能1号評価試験
- 日本語能力の証明
外食業特定技能1号評価試験は、外食産業で働くために必要なスキルを測る試験です。「学科」と「実技」の2つで構成され、試験時間は合計70分です。学科試験では、外食の仕事に関する日本語の理解度が問われ、実技試験では、状況に応じた適切な判断や作業計画を立てる能力が評価されます。
試験は年に3回程度(3月、8月、11月頃)行われ、日本だけでなく、フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、カンボジア、タイ、スリランカなど海外でも受験できます。OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)から申し込みが必要です。
特定技能「外食業」の申請には、技能測定試験に加え、以下のいずれかの日本語能力を証明する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テストで200点以上
日本語能力試験(JLPT)レベルの目安は以下のとおりです。
- N1:広範な場面で使用される日本語を理解できる
- N2:日常的な場面に加え、より広範な場面で使われる日本語をある程度理解できる
- N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる
- N4:基本的な日本語を理解できる
- N5:基本的な日本語をいくらか理解できる
日本の大学に通う留学生の多くはN2の取得を目指しており、最難関であるN1の合格率は国内外で約3割程度です。
特定技能「外食業」における外国人材受け入れのメリット

特定技能「外食業」の外国人材を受け入れることは、人手不足の解消に役立つだけでなく、企業の成長にもつながる多くの利点をもたらします。ここでは、企業が特定技能「外食業」の外国人材を受け入れることで得られる、主な5つのメリットについて解説します。
| 特定技能「外食業」における外国人材受け入れのメリット |
|
慢性的な人手不足の解消に貢献
日本の飲食業界は以前から人材確保に苦労しており、特定技能「外食業」は、多くの飲食店が抱える構造的な労働力不足の緩和に貢献すると考えられています。この制度により、企業は安定した人材を確保し、日々の店舗運営を円滑に進められるでしょう。
特定技能の外国人材は基本的に週30時間以上のフルタイムで直接雇用できるため、労働時間に制限のある留学生アルバイトなどと比較して、勤務シフトの調整が容易になります。
実際、出入国在留管理庁の公開情報によると、特定技能「外食業」での在留外国人材の数は年々増加しており、2023年12月の13,312人から、2024年12月には27,864人と大幅に増加しています。
即戦力としての活躍が期待できる
外食業における特定技能外国人材の活用は、即戦力として期待できます。受け入れにあたっては、技能試験や日本語能力試験の基準を満たす必要があるため、採用後比較的スムーズに業務に適応し、貢献することが見込まれます。
さらに、特定技能には1号と2号があり、2号の外国人材を受け入れることで、より長期的な人材確保が可能です。1号の在留期間には上限がありますが、2号には更新制限がなく、柔軟な対応が可能です。
特定技能の外国人材は基本的に週30時間以上のフルタイムで直接雇用できるため、労働時間に制限のある留学生アルバイトなどと比較して、勤務シフトの調整が容易になります。
日本人スタッフとほぼ同等の業務を任せられる
特定技能「外食業」の外国人材は、日本人スタッフと同等の幅広い業務を担い、その活躍は現場の負担軽減や店舗全体の業務効率向上に貢献すると期待されています。特定技能「外食業」の外国人材が対応できる業務は多岐にわたり、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 調理業務
- 接客業務
- 店舗管理業務
さらに、特定技能2号の外国人材となると、1号の業務に加え、より専門性の高い調理や、高度な接客スキルが求められる業務、さらには店舗全体の経営に関わる業務も任せることができ、将来的に店舗を牽引するリーダーとしての活躍も期待できます。
特定技能「外食業」の外国人材は、単に指示された作業を行うだけでなく、店舗運営を支える重要な戦力として、さまざまな業務に貢献することが期待されています。他の就労ビザと比較しても、外食業の範囲内であれば業務の制約が少なく、日本人スタッフを雇用する場合と変わらない業務遂行能力を持つ点が大きな利点と言えるでしょう。
研修や教育にかかる時間やコストを削減できる
特定技能「外食業」における外国人材の活用は、企業にとって採用と教育の面で効率化をもたらす利点があります。特定技能の外国人材は、採用時点で一定水準の専門知識、技能、日本語能力を有しているため、ゼロから人材を育成する手間が省け、研修や教育に関連する時間と費用を圧縮できます。
具体的には、外食業における基本的な業務知識の習得に要する時間と費用、新人教育の初期段階で発生するOJTなどの負担、専門的な基礎研修のコストを削減することが可能です。例えば、調理の基本、接客マナー、衛生管理といった業務遂行に必要な基本的な知識は既に習得済みであると考えられます。
そのため、企業はより実践的な業務に特化した研修に注力でき、人材育成にかかる時間や費用を抑えつつ、経営資源を他の重要な業務へ割り当てることが可能です。
多様なアイデアが生まれやすくなる
特定技能「外食業」における外国人材の活用は、職場環境に多様な刺激を与え、組織全体の活性化を促します。異文化を背景とする人材が参画することで、業務プロセスや発想に新鮮な視点や独自のアイデアが生まれるかもしれません。
外国人材の雇用は、母国の食文化に関する知識がメニュー開発のきっかけとなったり、外国人材ならではの視点が接客サービスを改善するヒントになったりします。多言語スキルを持つ人材の活躍により、外国人観光客への円滑なサービス提供が可能となり、新たな顧客層の開拓に繋がります。
外国人材の受け入れは、職場内に革新的な変化をもたらし、従業員間の相互理解を深める契機となります。サービス品質の向上や業務効率化に対する意識を高める効果も期待できるでしょう。
特定技能「外食業」取得外国人の雇用までの流れ

特定技能「外食業」の在留資格を持つ外国人を日本で雇用するには、定められた手順に従う必要があります。外国人本人が事前に試験に合格していることが前提ですが、企業が雇用までに行う主な流れは以下のとおりです。
| 特定技能「外食業」取得外国人の雇用までの流れ |
|
1. 採用と契約の締結
企業は、オンライン面接などで採用候補の外国人を選び、「特定技能雇用契約」を結びます。この契約は、外国人材の労働条件を明確にする上で非常に重要です。
2. 1号特定技能外国人支援計画の作成
特定技能1号の外国人労働者を雇用する事業主は、制度上、日本で円滑に業務を行い、快適に生活できるよう支援する責任があります。この支援策を具体的にまとめたものが「1号特定技能外国人支援計画」です。作成した支援計画は、外国人労働者が完全に理解できる言語で丁寧に説明し、計画書のコピーを渡して署名を得る必要があります。
3. 事前ガイダンスの実施と健康診断
特定技能1号の外国人労働者を雇用する事業主は制度上、日本で円滑に業務を行い、快適に生活できるよう支援する責任があり、入国前の段階で、ビデオ会議システムなどを活用した情報提供を行うことが推奨されています。
これは、彼らが日本での生活や仕事にスムーズになじめるよう、企業がさまざまなサポートを行う一環であり、入国直後の健康診断なども含まれます。
4. 在留資格認定証明書の申請
特定技能「外食業」の在留資格を取得するには、まず企業が「在留資格認定証明書」の交付を申請する必要があります。この申請は、申請代理人となる職員の勤務地を管轄する出入国在留管理官署で行います。申請時には、受け入れ予定の外国人の方の健康診断結果を証明する書類も添付してください。
5. 証明書の送付
在留資格認定証明書が審査を経て発行された場合、企業はこの証明書を海外にいる外国人本人宛に郵送します。もし電子メールで証明書が発行された場合は、そのメールを転送しましょう。
6. 査証(ビザ)の申請
在留資格認定証明書を取得した外国籍の方は、お住まいの国にある日本大使館や領事館でその証明書を提示し、ビザの発給を申請して取得することになります。
7. 来日・就労開始
外国籍の方は、ビザと在留資格認定証明書を持って日本へ渡航し、就労を開始します。在留資格認定証明書には有効期限があり、発行日から3ヶ月以内に入国する必要があるので注意が必要です。
事前オリエンテーションといった特定技能外国人のサポート業務は、「登録支援機関」に依頼することも可能です。
特定技能「外食業」分野における優良事例

ここでは、大阪府に本社を置く、餃子・ラーメン・中華料理店を運営する企業を例に解説します。
この企業は大阪と奈良で計7店舗を展開しており、従業員約80名のうち、約30名が外国人材です。さまざまな在留資格を持つ外国人材を採用し、それぞれのキャリアプランを策定しています。
外国人材の配置にあたっては、あえて郊外店に配属することで、日本語や日本の習慣を習得できるように工夫し、中心スタッフとして活躍してもらうことで、モチベーション向上を図っています。また、地方店への外国人材配置は、地域の人材不足の解消にも貢献しています。
特定技能外国人の支援体制については、登録支援機関を利用せず、社内管理部門で構築しています。同じ出身国のマネージャーがアドバイスを行う体制を整え、働きやすい環境づくりに努めています。
ベトナム出身のDさんは努力家として評価されており、日本人スタッフによるOJTを経て、わずか4ヶ月後には厨房で調理を任されるようになりました。接客でも笑顔を絶やさず、お客様から高い評価を得ています。
Dさんは特定技能制度を活用して日本で働き続ける理由として、アルバイトに比べて安定した収入が得られる点を挙げています。お客様から「おいしかった」と直接言われることが非常に嬉しく、やりがいを感じると話しています。将来の夢はベトナムに戻ってレストランを開くことで、日本の生活での悩みは物価が高いことだそうです。
この事例について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
特定技能外国人は派遣雇用できる?受け入れる時の要件や注意点を解説
特定技能「外食業」取得外国人雇用の注意点

特定技能「外食業」で外国人材を雇用する際には、法律に違反しないために、いくつかの重要な注意点があります。知らなかったでは済まされないリスクもあるため、以下のポイントをしっかり確認しましょう。
特定技能「外食業」の外国人材は、必ず企業が直接雇用する必要があります。派遣社員として雇用することは認められていません。また、風俗営業法で定められた店舗では、特定技能「外食業」の外国人材を雇用できません。これは、接待行為が禁止されているだけでなく、調理や接客の仕事もさせることができないためです。
さらに、特定技能外国人材への給与は、日本人と同等以上でなければなりません。同じ仕事内容であるにもかかわらず、「外国人だから」という理由で、日本人より低い給料にすることは許されません。労働契約の時点でこのルールに違反している場合、外国人が在留資格を得られないこともあります。
特定技能「外食業」のまとめ

この記事では、特定技能「外食業」について解説しました。
特定技能「外食業」は、深刻な労働力不足に対応するため2019年に設けられた在留資格です。飲食店での調理、接客、店舗管理を担う人材として期待されており、日本人と同等の業務が可能です。
雇用企業は、適切な雇用契約の締結、法令遵守、サポート体制の整備、支援計画の策定などの要件を満たす必要があります。また2024年6月15日以降は、協議会への加入が必須となります。
外国人材の派遣雇用は認められず、風俗営業法に該当する店舗での雇用もできません。さらに賃金は日本人と同等以上である必要があります。これらの注意点を守り、適切な手続きと支援を行うことで、特定技能外国人は企業の戦力となり、成長に貢献します。また、同じ出身国のマネージャーがアドバイスを行うなど、働きやすい環境づくりも重要になります。