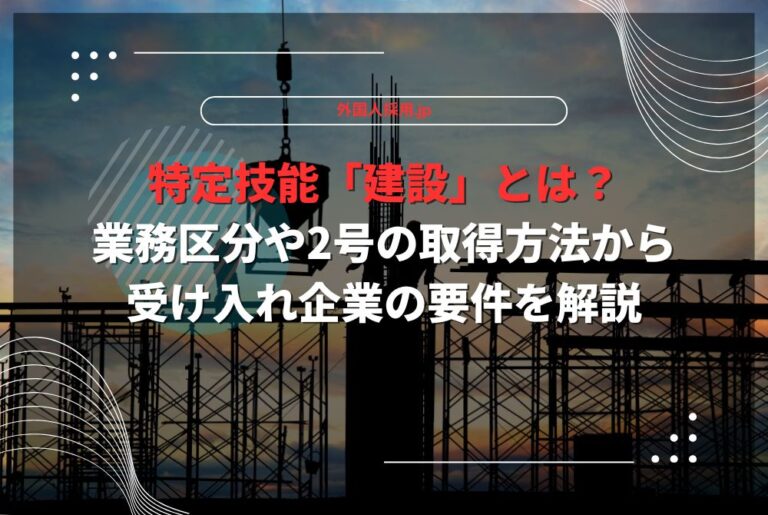日本の建設業界は、深刻な人手不足と高齢化に直面し、優秀な人材の確保にお困りではないでしょうか?この課題を解決するために外国人材の雇用が検討されているかもしれません。
この記事では、人手不足を解消する特定技能「建設」制度について、その概要や外国人の在留資格取得方法を解説します。
特に、貴社が特定技能外国人を雇用するために必要な「受け入れ企業の要件」を網羅的に説明することで、スムーズな雇用実現に向けた具体的なステップを理解し、人手不足解消に貢献します。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能「建設」とは?

日本の建設業界は深刻な人手不足と高齢化に直面しており、2004年から2025年にかけて就業者数は大幅に減少しています。特に、若者の建設業離れが状況を悪化させています。この状況を打開するため、能力のある外国籍人材が建設現場で活躍できるよう、特定技能「建設」が創設されました。2024年12月時点で、約39,000人の外国人がこの制度を利用して建設分野で働いています。
特定技能には、スキルレベルに応じて1号と2号の区分があります。1号では、建設分野で一定の知識や経験が求められる業務に従事し、在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められません。
一方、2号では1号よりも高度なスキルが要求され、作業員の指導や工程管理などを担当します。在留期間の制限はなく、条件を満たせば家族の帯同も可能で、永住権の取得も視野に入れることが可能です。また特定技能2号の対象分野は2023年に拡大されました。
特定技能「建設」で就業可能な業務区分

特定技能「建設」では、外国籍の方が従事できる業務範囲が定められています。以前は11職種で区別されていましたが、2022年8月に3つの業務領域に再編成されました。この変更により、例えば型枠工事の技能実習を終えた外国人は、土木または建築の区分で認定された在留資格の範囲内で、現場の種類を限定されずに作業できます。
特定技能「建設」で外国籍の方が従事できる業務領域は以下の通りです。
| 土木区分 | 道路やダムなどの土木構造物の新設、改修、維持、修繕に関わる作業 |
| 建築区分 | 住宅やビルなどの建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、内装の変更などに関する作業 |
| ライフライン・設備区分 | 電気、ガス、水道などのライフライン設備や、空調設備の設置、修理、変更などに関する作業 |
これらの業務領域への再編により、特定技能の資格を持つ外国籍の方が、より多様な建設現場で活躍できる制度設計となっています。
特定技能外国人は派遣雇用できる?受け入れる時の要件や注意点を解説
特定技能1号、2号「建設」の取得方法

外国人材が特定技能「建設」の在留資格を取得するためには、その技能レベルに応じて「特定技能1号」または「特定技能2号」のいずれかの要件を満たす必要があります。それぞれの取得方法は以下の通りです。
| 特定技能1号、2号「建設」の取得方法 |
|
特定技能1号「建設」の取得方法
特定技能1号(建設)の在留資格を得るには、主に2つの方法があります。
1つは、技能評価試験と日本語試験に合格することです。この方法では、建設分野の技能評価試験(「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」)と日本語試験の両方に合格する必要があります。
技能評価試験では、初級技能者が持っているべき技能や知識が問われ、試験区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つです。希望する業務区分に合わせて試験を受けます。
日本語試験は、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で250点満点中200点以上を取る必要があります。
JLPT N4レベルでは、基本的な語彙や漢字を使って書かれた文章を読み、日常会話を理解できる程度の能力が求められます。JFT-Basicは、日本での生活に必要な日本語能力を測るテストで、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がないレベルかどうかを判定します。JFT-BasicはJLPTに比べて試験の実施回数が多いため、受験しやすいという利点があります。
もう1つの方法は、建設分野の技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号への移行を申請することです。技能実習2号をきちんと修了していれば、特定技能1号への移行が可能です。この方法では、技能実習2号を「良好に修了」していることと、技能実習で経験した職種や作業内容が、特定技能1号で従事する業務区分と一致していることが条件となります。この場合、日本語試験は免除されます。
特定技能2号「建設」の取得方法
特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。建設分野でこの資格を取得するには、特定の要件を満たす必要があります。
建設分野の特定技能2号では、日本語試験は免除されており、「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」のいずれかに合格することが主なルートです。これらの試験は、熟練した技能労働者が通常備えているべき技能と知識を評価するもので、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の区分があります。業務に応じて適切な区分を選択し、受験することが必要です。
加えて、建設現場での実務経験も不可欠です。複数の技能者を指導しながら作業を遂行し、工程を管理する経験が求められます。この実務経験は、建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積された就業日数と就業履歴で確認されるため、事前にCCUSへの登録が推奨されます。
CCUSで能力評価基準が定められた職種に従事しており、レベル3の評価を取得している場合は、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出することで、実務経験の要件を満たすことが可能です。
特定技能「建設」技能評価試験の内容

外国人の方が特定技能1号「建設」の資格を得るためには、特定の技能レベルと日本語能力が求められます。具体的には、「特定技能評価試験」と「日本語試験」という2つの試験で、定められた基準を超える成績を収めることが必要です。
「特定技能評価試験」の「建設」分野では、知識を問う「学科試験」と、実際の作業能力を評価する「実技試験」の2種類が実施されます。これは特定技能2号の場合も同様です。
特定技能1号「建設」技能評価試験は、建設分野における初級レベルの技能者が持つべき知識とスキルを測ることを目的としています。試験は「土木」「建築」「ライフライン・設備」という3つの専門分野に分かれており、希望する業務内容に応じて、いずれか1つの分野を選択して受験します。技能検定3級に相当するとも言われています。
試験の概要は以下の通りです。
| 項目 | 学科試験 | 実技試験 |
|---|---|---|
| 問題数 | 30問 | 20問 |
| 試験時間 | 60分 | 40分 |
| 出題形式 | ○×形式や選択式 | ○×形式や選択式 |
| 実施方法 | コンピューターを使った試験(CBT方式) | コンピューターを使った試験(CBT方式) |
| 合格基準 | 合計点の65%以上 | 合計点の65%以上 |
特定技能2号「建設」技能評価試験は、建設分野における上級レベルの技能者が持つべき知識とスキルを測るための試験です。特定技能1号と同様に、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3分野に分かれており、それぞれの業務内容に応じた分野を受験する必要があります。
合格することで、より高度な業務に携わることが可能になります。技能検定1級に相当するとも言われています。
試験の概要は以下の通りです。
| 項目 | 学科試験 | 実技試験 |
|---|---|---|
| 問題数 | 40問 | 25問 |
| 試験時間 | 60分 | 40分 |
| 出題形式 | 4択式 | 4択式 |
| 実施方法 | コンピューターを使った試験(CBT方式) | コンピューターを使った試験(CBT方式) |
| 合格基準 | 合計点の75%以上 | 合計点の75%以上 |
受け入れ企業が特定技能「建設」取得外国人を雇用するための要件

特定技能外国人労働者を雇用する企業は「特定技能所属機関(受入れ機関)」と呼ばれます。建設業で特定技能外国人を受け入れるには、いくつかの特別な基準を満たす必要があり、これは建設分野における特定技能制度が円滑に運用され、外国人材が安心して日本で働き生活できる環境を確保するためです。
ここでは、受け入れ企業が特定技能「建設」取得外国人を雇用するための要件について、以下の見出しで解説します。
| 受け入れ企業が特定技能「建設」取得外国人を雇用するための要件 |
|
建設特定技能受入計画の認定を受ける
建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、「特定技能所属機関」は「建設特定技能受入計画」の策定が求められます。この計画には、外国人に支払う報酬額等の詳細を記載し、その内容が国土交通大臣によって適正と認められる必要があります。
審査の主なポイントは以下の通りです。
- 同一の技能を持つ日本人労働者と同等以上の給与水準を保証すること(同一労働同一賃金の原則に準拠)
- 特定技能外国人への報酬は、月給制で安定的に支払うこと
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必須であること
- 1号特定技能外国人(および外国人建設就労者)の合計人数が、常勤職員数を超えないこと
なお、特定技能外国人を受け入れる機関は、建設業の許可を得ていることが前提条件となります。
JAC(建設技能人材機構)関連団体に加入する
建設分野で特定技能外国人労働者を受け入れる企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)、またはJACの正規会員である建設関連団体への参加が必須です。この手続きは、特定技能ビザを申請する前に済ませる必要があります。
会員になるには、以下の費用が発生する場合があります。
| 正規会員(建設技能人材機構(JAC)に加入している建設業者団体)の場合 | 年間36万円 |
| 所属団体が建設業者団体の正規会員である場合 | 年間約5〜12万円 |
| 賛助会員(所属団体が正規会員ではない場合、または団体に所属していない場合) | 年間24万円 |
上記の会費とは別に、1号特定技能外国人1名につき、毎月12,500円の受入れ関連費用がかかります。
外国人支援体制の整備をする
特定技能外国人の方が日本で安心して働き生活できるよう、受け入れ機関は、さまざまなサポートを行う責任があります。これらのサポート業務は、「登録支援機関」へ委託することも可能です。
具体的な支援内容の例としては、以下のようなものがあります。
- 来日前のガイダンス
- 入国時・出国時の送迎
- 住居の手配、生活に必要な契約のサポート
- 日本での生活に関する情報提供
- 行政手続きへの同行
- 日本語学習機会の情報提供
- 相談窓口の設置、苦情対応
- 日本人との交流促進
- 受け入れ機関の都合による雇用契約解除時の転職支援
- 定期的な面談の実施、必要に応じた行政機関への連絡
このように多岐にわたる支援を通じて、特定技能外国人の方々が日本社会に円滑に適応できるよう、受け入れ機関は努める必要があります。
特定技能「建設」のまとめ

この記事では、特定技能「建設」について解説してきました。
特定技能「建設」は、日本の建設業界における労働力不足と高齢化に対処するために設けられた在留資格です。この制度には、技能レベルに応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があります。
1号では、一定の知識や経験が求められる業務に従事し、最長5年の在留期間が認められますが、家族の帯同はできません。2号は、より高度なスキルが要求され、在留期間の制限はなく、条件を満たせば家族の帯同も可能となり、永住権の取得も視野に入ります。
2022年8月には、業務区分が「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに再編され、より多様な現場で活躍できるようになりました。資格を取得するには、1号の場合、「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格するか、「技能実習2号」を良好に修了する必要があります。2号の場合は、「特定技能2号評価試験」に合格することが主なルートとなり、日本語試験は免除されます。
外国人を受け入れる企業は、「建設特定技能受入計画」の認定を受け、JAC関連団体に加入し、外国人に対する支援体制を整える必要があります。受入計画では、同一技能を持つ日本人と同額以上の賃金、CCUSへの登録などが審査されます。JACへの加入には、年会費や受入れ負担金が発生します。また、来日前のガイダンスや住居の確保、生活オリエンテーションなど、さまざまな支援が義務付けられています。
これらの要件を満たすことで、外国人材の安定した就労と生活を支え、建設業界の発展に貢献することができます。