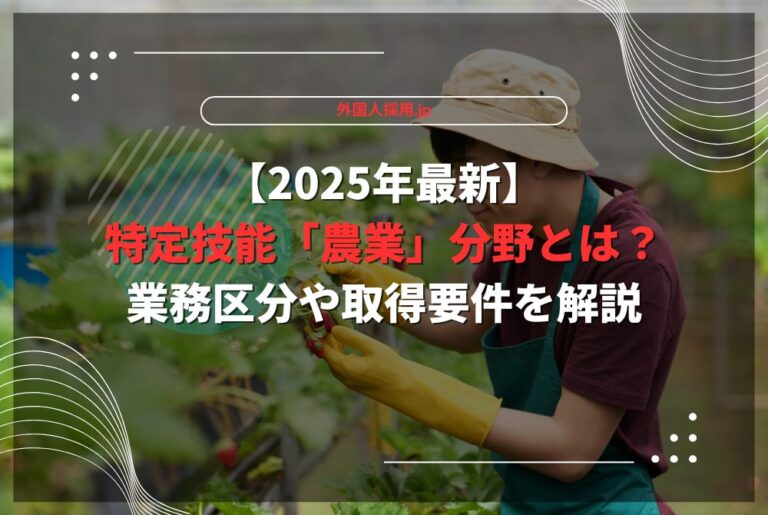日本の農業界は、深刻な人手不足と農業従事者の高齢化という喫緊の課題に直面し、安定した労働力の確保が急務となっています。特定技能外国人材の活用を検討しても、制度の複雑さや、文化・生活習慣の違いから生じるトラブルへの不安を感じていませんか?
これは多くの農業経営者が抱える共通の悩みではないでしょうか。
この記事では、特定技能「農業」制度の概要から受け入れのメリット、必要な手続き、特に注意すべきコミュニケーション、生活習慣、人間関係に関するトラブルと対策まで、網羅的に解説します。これを読めば、外国人材をスムーズかつトラブルなく雇用し、自社の農業経営を安定させ、持続的な成長を実現するための具体的なヒントが得られるでしょう。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能「農業」分野とは?

国内で生産性向上や日本人材の確保に努めても人材不足が解消されない分野において、一定の専門知識と技能を持つ外国人を受け入れることを目的として、特定技能制度が2019年4月に始まりました。特に日本の農業界は深刻な労働力不足に直面しており、この制度を活用することで、即戦力となる外国人材の受け入れを増やしています。
当初、農業分野では特定技能1号のみが適用されていましたが、2023年8月には、農業分野の人材不足緩和のため、特定技能2号も対象分野に追加されました。特定技能「農業」では、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」、およびそれらに関連する業務に従事できます。特定技能2号では、これらの業務に加え、関連業務の管理も担当可能です。
特定技能1号と特定技能2号の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 5年まで | 上限なし |
| 更新頻度 | 4ヶ月、6ヶ月、1年ごと | 6ヶ月、1年、3年ごと |
| 対応業務 |
|
特定技能1号の業務、およびその管理業務 |
| 家族の帯同 | 不可 | 一定条件で可能 |
| 永住可能性 | 原則不可 | 一定条件で可能 |
| 支援の有無 | 受入れ機関または登録支援機関による支援 | 原則不要 |
特定技能「農業」分野の業務区分

特定技能「農業」では、以下の業務に従事できます。
さらに、特定技能2号の場合は、これらの業務に加えて、関連業務の管理業務にも従事可能です。以下に、それぞれの業務範囲について詳しく説明します。
| 特定技能「農業」分野の業務区分 |
|
耕種農業
耕種農業は、植物を育てる農業の一分野で、例えば、野菜、果樹、穀物などの作物を栽培することです。具体的な作業内容としては、以下のようなものがあります。
- 種をまく
- 水やりをする
- 種や苗の状態をよく観察する
- 収穫した農産物を集めて、出荷の準備をする
- 雑草を取り除く
- 作物が育ちやすいように土を作る
- 肥料をあげる
- ビニールハウスの中の環境を調整する
- 安全に作業するための衛生管理をする
畜産農業
畜産農業とは、家畜を育て、食肉や鶏卵といった生産物を得ることを目的とする農業の一形態です。その作業内容は多岐にわたり、例えば下記のようなものが挙げられます。
- 家畜に対する給餌や給水
- 畜産物の収集と出荷
- 家畜が生活する場所の清掃
- 家畜の健康状態の把握と管理
- 衛生管理に関する作業全般
その他関連業務
特定技能「農業」の外国人材は、農畜産物の製造・加工、運搬・販売といった業務や、冬季の除雪作業といった関連業務にも携わることが可能です。ただし、主となる業務はあくまで農業であり、これらの関連業務のみを行うことは認められていません。
特定技能「農業」分野の取得要件

特定技能「農業」の在留資格を得るには、外国人材は定められた要件を満たす必要があります。これらの要件は、特定技能1号と2号で異なり、それぞれ求められる技能レベルや経験が異なります。ここでは、各号の取得要件について詳しく解説します。
| 特定技能「農業」分野の取得要件 |
|
特定技能1号「農業」分野
特定技能1号「農業」の資格を取得する方法は、主に2つあります。
1つは、農業分野の技能実習2号を良好に修了することです。この場合、技能実習計画に基づいて2年10ヶ月以上の実習を終え、技能検定3級またはそれに準ずる技能実習評価試験の実技に合格するか、実習先から勤務状況や技能の習得度、生活態度が詳しく書かれた「評価調書」を受け取る必要があります。この条件を満たせば、通常必要な日本語試験と特定技能評価試験が免除されます。
もう1つは、技能実習2号を修了していない場合に、技能試験である1号農業技能測定試験と、日本語試験である日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストのいずれかに合格することです。
ただし、技能実習1号を修了しただけでは特定技能1号には移行できません。技能実習3号から特定技能1号への移行を希望する場合は、技能実習2号を良好に修了していても、技能実習3号の修了が必須となる点に注意が必要です。
特定技能2号「農業」分野
特定技能2号「農業」の取得には、1号に比べてより高度な専門知識と実務経験が必要です。具体的には、学科試験と実技試験からなる2号農業技能測定試験に合格しなければなりません。
2号農業技能測定試験では、知識だけでなく、管理能力や指導力も評価されます。実務経験としては、2年以上の作業工程管理や作業員の指導経験、または3年以上の農作業の実務経験が必須です。ただし、指導・管理経験が十分でなくても、3年以上の農業の実務経験があれば、特定技能2号の取得要件を満たせます。
特定技能「農業」で外国人を雇用する企業の主な5つの要件

特定技能「農業」の外国人を受け入れる企業は、法律を守ることはもちろん、外国人が安心して働けるように、いくつかの大切な条件を満たす必要があります。ここでは、企業が満たすべき主な5つの条件について説明します。
| 特定技能「農業」で外国人を雇用する企業の主な5つの要件 |
|
1. 雇用実績
特定技能の外国人を受け入れる企業は、原則として、6ヶ月以上継続して同じ労働者(技能実習生を含む)を雇用した実績、またはそれに相当する経験が必要です。
ここで言う「相当する経験」とは、少なくとも6ヶ月間、労務管理の業務に携わった経験を指します。具体的には、労働関連の法律を守りながら従業員の給与計算や勤務時間の管理、社会保険の手続きなど、労働条件や職場環境に関わる業務全般を担当した経験が当てはまります。なお、この経験は過去5年以内のものが条件となります。
2. 労働条件の保証
特定技能外国人材の待遇について、法律では、日本人の従業員と同等以上となる給与や労働環境を提供することが義務付けられています。この規定を守らなかった場合、労働基準法に違反する可能性があり、その際は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
3. 支援体制の整備
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、以下の10項目のサポート体制を構築する必要があります。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居・契約サポート
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流支援
- 転職支援(雇止め等)
- 定期面談・法令違反の通報
外国人材が日本語を十分に理解できない場合は、母国語の通訳を手配するなど、必要なサポートを受けやすい環境を整えることが重要です。自社のみでこれらの支援が難しい場合は、登録支援機関への委託も検討してください。
4. 法令遵守体制の整備
特定技能の外国人を受け入れる企業は、入管法や労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、社会保険関連法などの関連法規を遵守できる組織体制を構築する必要があります。
5. 農業特定技能協議会への加入
農業特定技能協議会は、特定技能制度における農業分野が円滑に進むように設立されました。特定技能「農業」の資格を持つ外国人労働者を雇用する事業者は、この協議会への参加が義務付けられています。
協議会への参加をご希望の場合は、こちらからお申し込みください。
特定技能「農業」分野における派遣事業者の主な要件

特定技能「農業」分野では、直接雇用に加えて、派遣という形での雇用も認められています。これは、農業の仕事の性質上、時期によって仕事量に大きな差が出るため、必要な時に必要な人数を効率的に確保することが目的です。
ただし、特定技能外国人材を派遣できる事業者には条件があり、法務大臣が農林水産大臣と協議し、適切と認めた事業者に限られます。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 農業、または農業に関連する事業を実際に行っている事業者
- 地方公共団体、または地方公共団体が出資している法人
- 業務執行に地方公共団体の職員などが実質的に関与している事業者
- 国家戦略特区における特定の機関
なお、派遣事業者として認められた場合でも、3年後には再度、適格性が審査されます。
特定技能外国人は派遣雇用できる?受け入れる時の要件や注意点を解説
特定技能「農業」分野における外国人材受け入れのメリット

日本の農業分野では人手不足が深刻になっており、特定技能「農業」の外国人を受け入れることで、多くの利点が期待されています。ここでは、主な3つのメリットについて説明します。
| 特定技能「農業」分野における外国人材受け入れのメリット |
|
労働力不足への対応
日本の農業は、長年の人手不足という問題を抱えており、特に地方では、農業者の高齢化が深刻です。このような状況で、特定技能制度の「農業」分野で外国人を受け入れることは、多くの農家にとって人手不足を解消する有効な手段となります。
特定技能外国人材は、受け入れ人数の上限がないため、各企業はそれぞれの必要に応じて必要な労働力を柔軟に確保できます。
フレッシュな即戦力の確保
特定技能の外国人材は、ある程度の知識や技術を持つ20代から30代が中心です。そのため、現場ですぐに活躍できる若い人材を受け入れることは、急務である農業分野の労働力不足、特に高齢化を改善する有効な方法となるでしょう。
経営効率の改善および生産力強化
特定技能1号の資格で日本に滞在できる期間は、最長で累計5年です。特定技能を持つ外国人材を一定期間雇用することで、作業手順や専門知識を教えるためのコストを削減でき、生産性向上につながることが期待されます。
さらに、安定した労働力を確保できるため、農業の作業を計画的に進められ、経営の安定にもつながると考えられます。
特定技能「農業」分野における外国人材受け入れ手続きの流れ

特定技能「農業」の分野で外国人材を雇用する場合、円滑な受け入れのために、段階的な手続きと準備が不可欠です。ここでは、一般的な雇用プロセスに沿って説明します。
| 特定技能「農業」分野における外国人材受け入れ手続きの流れ |
|
1. 雇用計画の立案
外国人材の雇用を考える際、まず受け入れ人数と、担当させる仕事が特定技能「農業」の対象範囲に含まれるかをはっきりさせることが大切です。次に、給与や労働時間といった労働条件を詳しく決めておくことで、その後の手続きがスムーズに進みます。
2. 求人方法の選定
求人募集は、必ずしも自社だけで行う必要はありません。登録支援機関を通じて、海外の送り出し機関に人材紹介を依頼することも可能です。自社の状況を考慮し、最適な募集方法を慎重にご検討ください。
3. 外国人労働者の選考・採用
外国人材の採用プロセスでは、書類選考と面接が通常行われます。選考では、農業に関する知識や技能に加え、日本語でのコミュニケーション能力や日本での生活への適応力も評価されます。さらに、簡単な農作業の実技テストを実施することで、採用後のミスマッチを防ぐことが期待できます。
4. 労働契約の締結手続き
採用候補者の内定後、雇用契約の手続きに移ります。その際、労働条件を記載した書面を、日本語に加えて外国人材の母国語でも準備し、内容を十分に理解してもらえるよう努めることが大切です。
5. 在留資格取得の申請
雇用契約成立後、入国管理局でビザを申請する必要があります。書類に不備があると、ビザの発給が遅れたり、再提出が必要になることがあるので、十分に準備してください。
6. 受入れ体制の整備
在留資格の取得期間を利用して、外国人労働者の受け入れ準備をしましょう。具体的には、住居の準備、日本の習慣やマナー、公共サービスの使い方、連絡先一覧の作成、災害時の対応など、生活オリエンテーションを行います。これにより、外国人労働者がスムーズに日本での生活に慣れ、仕事に専念できる環境を目指します。
7. 入社後定着支援の実施
外国人材を受け入れた後も、丁寧なフォローアップが重要です。例えば、日本語能力向上のための学習機会の提供、仕事や生活における悩みや不満の相談窓口の設置、日本人従業員とのコミュニケーションを促進する施策の実施、必要に応じた行政手続きのサポート、少なくとも四半期に一度の定期的な面談などが考えられます。
これらのサポートを適切に行うことで、外国人材がストレスなく能力を発揮できる環境が整い、結果として長く活躍してもらうことにつながるでしょう。もし自社のみで十分な支援体制を構築することが難しい場合は、登録支援機関への委託を検討すると良いでしょう。
特定技能「農業」分野における優良事例

ここでは、特定技能「農業」分野で外国人材を受け入れている優良事例として、株式会社三木田様と有限会社タカハシファーム様の取り組みをご紹介します。
| 特定技能「農業」分野における優良事例 |
|
株式会社三木田様
株式会社三木田は、55ヘクタールという広大な農地を活かし、長ネギ、スイートコーン、ブロッコリー、トマト、小麦、大豆など多岐にわたる農作物を生産する農業法人です。野菜の生産に加え、玉ねぎ、カボチャ、ごぼうといった農産物の一次加工、農家民宿の運営、農作業の請負も手掛けるなど、多角的な事業展開を行っています。2023年度の売上高は4億円に達し、その成長を支えているのが、多様な人材構成だと言えます。
従業員は、日本人従業員20名(正社員8名、パート12名)に加え、外国人従業員22名(男性14名、女性8名)で構成されています。人手不足の解消を最優先課題として外国人材の受け入れを開始し、特定技能外国人として中国、モンゴル、インドネシア出身の5名を、技能実習生としてベトナム、モンゴル、インドネシアから17名を受け入れています。外国人材のサポートは、登録支援機関である合同会社竹原に委託している状況です。
株式会社三木田の支援には、以下のようなものがあります。
- 技能実習3号を修了した人材の特定技能制度への移行を支援し、継続雇用につなげることで、安定的な人材確保を実現
- 入国前の説明会には会社も参加し、給与からの差し引き項目を丁寧に説明
- 宿舎は出身国ごとに分け、通勤には自転車を貸与
- 社員の働きやすさにも配慮し、生活に必要な物の希望を聞き、残業時間は本人の希望を考慮して調整
- 機械作業などの際に日本人リーダーが注意を促し、事故防止に努める
- 自動車運転免許の取得費用や日本語能力試験の受験費用を全額補助する
- 地域のお祭りへの参加を勧めたり、食事会や社員旅行を実施するなど、福利厚生も充実
給与は月給制で18万5,467円、労働時間は7.5時間、休憩時間は合計90分です。賞与は最大62,000円で、成果に応じて金額が変動します。特定技能外国人および一部の技能実習生には月額20,000円の住宅手当を支給し、夏の繁忙期には安価で社食を提供するなど、生活を支援しています。給料の昇給は年に1回の評価によって決定されます。
外国人材の受け入れ開始後、売上高は2倍に増加し、一年を通して作業できる体制を構築したことで、事業規模を拡大できました。また、職場全体が活気づき、年齢層の異なる日本人従業員と外国人材の間で良好なコミュニケーションが生まれるなど、組織全体の活性化に繋がっています。
農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集 令和6年度版
有限会社タカハシファーム様
有限会社タカハシファームは、養豚と酪農を主要な事業とする農業法人です。肥育豚の生産に力を入れており、循環型農業を実践しています。事業内容は養豚(肥育豚)、酪農、飼料用トウモロコシ・牧草の生産(37ha)で、飼育規模は乳用牛約520頭、肥育豚約14,000頭、母豚約1,250頭(育成豚約450頭を含む)です。
従業員数は日本人従業員10名、外国人従業員22名で、特定技能外国人1号を14名(ベトナム出身8名、フィリピン出身6名、男性11名、女性3名)、技能実習生を5名(2号)、3名(1号)雇用しています。外国人従業員の内、女性は3名で、フィリピン出身が2名、ベトナム出身が1名です。I&T協同組合と国際共生事業協同組合が登録支援機関としてサポートしています。
有限会社タカハシファームは人手不足を背景に、即戦力となる特定技能外国人の採用を開始しました。技能実習生と比べて、日本での生活経験が豊富で日本語能力が高いことが決め手となりました。外国人従業員側も、より高い賃金を得ながら日本の農業に関する知識や技術を習得したいという意欲がありました。
有限会社タカハシファームの支援には、以下のようなものがあります。
- 登録支援機関と連携し、給与や納税義務に関する説明に加え、生活面や各種手続きに関するサポート、相談体制の整備に力を入れる
- 従業員寮は農場の近くにあり、リフォーム済みの2人部屋(14〜21㎡程度)を提供(個人負担:月額25,500円)
- Wi-Fi環境を完備し、通勤用の自転車の貸与や自動車による送迎
- ゴミの分別に関しては、市が作成した外国語対応の案内を活用して丁寧に説明
- 従業員のキャリアアップを支援する制度を整備
- 業務に必要な自動車運転免許の取得費用を全額会社負担
- リーダー制度を導入し、技能実習生の指導
- 外部機関による研修費用の一部補助
給与は時給制で1,000円〜1,200円です。リーダー手当や運転免許手当なども支給され、月給換算で30万円を超える従業員もいます。特定技能外国人には、群馬県の最低賃金(985円)を上回る給与を支給しています。
労働時間は8〜9時間と長めですが、労働基準法を遵守し、適切な休日と残業手当を支給しています。賃金の見直しは年1回(10月)行われ、農場長との面談を通じて査定されます。資格手当や能力手当の他、作業着や作業に必要な物品は全て会社が支給しています。夏季には、熱中症対策として会社負担で飲料を提供しています。
外国人材の雇用により、労働力が大幅に向上し、事業の継続に不可欠な存在となっています。
農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集 令和6年度版
特定技能「農業」分野における注意点

特定技能外国人材を雇用する際、文化や習慣の違いからトラブルが起こることがあります。しかし、原因を理解し、適切な対策をすれば、トラブルを未然に防ぎ、外国人材が安心して働ける環境を作れます。
特定技能「農業」分野において、以下の3点に注意しましょう。
| 特定技能「農業」分野における注意点 |
|
コミュニケーション関連のトラブル
農業の現場では、言葉やコミュニケーションの課題から、さまざまなトラブルが起こりやすい状況です。農作業では専門用語がよく使われるため、日本語能力試験N4レベル程度の日本語力では、現場での指示を十分に理解できないことがあります。その結果、作業上のミスが起こったり、安全面でリスクが生じる可能性もあります。
また、トラブルやミスを報告すると「叱られるのではないか」という不安から、報告をためらうこともあります。特に農業現場では指導者と作業員の距離が近いことが多いため、信頼関係が十分に築けていないと、この問題が顕在化しやすい傾向があります。
これらの課題への対策として、日々のコミュニケーションを大切にし、作業員が「気軽に話しかけられる」と思えるような雰囲気づくりが、報告の遅れや誤解を防ぐことにつながります。普段から積極的にコミュニケーションを取ることで、信頼関係を築きやすくなります。
さらに、写真やイラストを多く使ったマニュアルを作成したり、翻訳アプリを活用することも有効です。加えて、トラブル対応に不安がある場合や、深刻な問題が発生した場合には、登録支援機関や農林水産省が運営する「農業分野 特定技能 支援サイト」、地方農政局、公益社団法人日本農業法人協会などの相談窓口を利用することが効果的です。
生活習慣の違い
外国人材が日本の生活習慣に慣れる過程で、さまざまな問題が起こりがちです。例えば、日本のゴミの分別は複雑で、不慣れな外国人にとっては地域のルールを守るのが難しく、近隣住民とのトラブルになることもあります。
また、母国の交通ルールとの違いから、交通違反や事故の危険性が高まることや、食生活の違いがストレスになることも考えられます。これらの問題を防ぐために、外国人材が入国する前に、日本の生活ルールをわかりやすく伝えることが大切です。
登録支援機関に依頼して、対面やオンラインで事前にガイダンスや生活オリエンテーションをしっかり行うことで、早い段階で不安を解消し、スムーズに日本での生活を始められるようにすることが期待できます。
人間関係における問題
外国人材を受け入れる際、職場環境や人間関係に起因する問題は、特に注意すべき点です。信頼関係が十分に築けていない場合、外国人材は「怒られたくない」という気持ちから、問題を報告しない傾向があります。
また、農業の現場では言葉遣いがきつくなりがちで、外国人材がそれを威圧的に感じ、ハラスメントと受け止めることもあります。さらに、休日の過ごし方など、外国人材の私生活に干渉することは、ストレスや離職につながる可能性があります。
これらの問題を未然に防ぐためには、日頃からコミュニケーションを密にすることが大切です。「話しかけやすい雰囲気」を作り、信頼関係を築くことが、問題の早期発見と解決につながります。
また、外国人材の文化的な背景や習慣を尊重することも、受け入れ側の大切な役割です。丁寧なコミュニケーションを通じて相互理解を深めるとともに、日本のマナーやルールもきちんと伝えることが重要です。
問題への対応に不安がある場合や、深刻な問題が発生した場合は、登録支援機関や農林水産省の支援サイト、地方農政局、日本農業法人協会などの相談窓口を活用すると良いでしょう。
特定技能「農業」分野のまとめ

この記事では、特定技能の「農業」分野について解説してきました。
日本の農業は、深刻な人手不足と従事者の高齢化という課題に直面しており、その解決策として特定技能制度による外国人材の受け入れが積極的に進められています。2019年の制度開始に加え、2023年には特定技能2号も対象となり、より長期的な人材確保が可能となりました。
外国人材の受け入れは、労働力不足の解消や若手人材の確保による高齢化対策、経営効率の改善など、農業界に多くのメリットをもたらします。実際に、外国人材の雇用により売上増加や事業拡大、職場活性化につながった事例も存在します。
しかし、文化や習慣の違いから生じるコミュニケーション不足、生活習慣の違い、人間関係の問題といった課題にも注意が必要です。これらの課題を未然に防ぐためには、日常的なコミュニケーションの強化や視覚的なマニュアルの活用、入国前のオリエンテーションの徹底、信頼関係の構築が重要となります。
また、登録支援機関や農林水産省の支援サイトなど、外部の相談窓口を積極的に活用することも有効です。雇用計画の立案から入社後の定着支援まで、段階的な手続きと手厚いサポートを行うことで、外国人材が安心して働き、日本の農業の持続的な発展に貢献できる環境を築くことが可能となります。