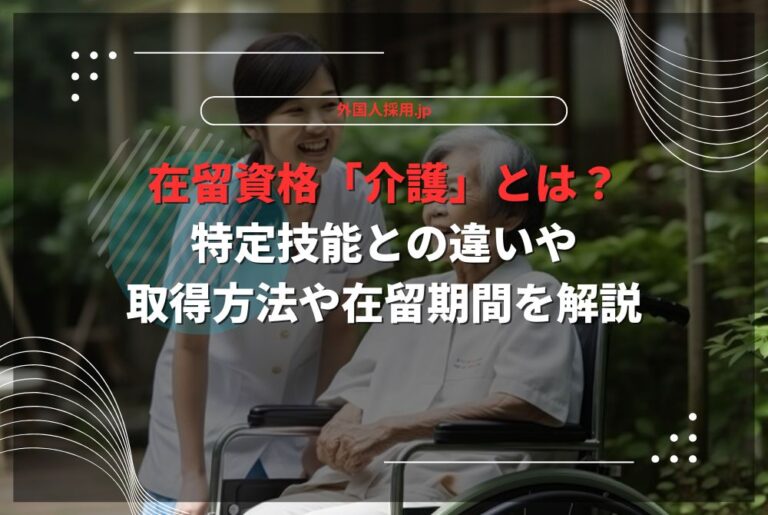日本の高齢化が加速する中で、介護現場における人手不足は年々深刻さを増しています。介護職の人手不足に対応するため、日本政府は外国人材の受け入れを拡大し、特に介護分野においては「在留資格『介護』」を設けて、専門的な技能と日本語能力を備えた外国人の就労を可能にしました。
本記事では、在留資格「介護」とは何かをわかりやすく解説するとともに、「特定技能」との違い、取得要件、在留期間、実際の就労までの流れなどを詳しく紹介します。
外国人雇用を検討する企業担当者や、介護職として日本で働きたいと考える外国人にとって、制度の理解は非常に重要です。制度の全体像を正しく把握し、円滑な受け入れと就労につなげましょう。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
介護における在留資格の4つの種類

介護における在留資格はおもに以下の4つに区分されています。
ここでは、下記の区分について解説します。
|
在留資格(介護)
在留資格「介護」とは、日本の国家資格である「介護福祉士」を取得した外国人が、日本国内の介護施設などで働くために認められる在留資格です。
2017年の制度導入以降、外国人材の定着を目的とした中長期的な就労制度として注目されています。在留資格「介護」を取得するためには、厚生労働省が認定する専門学校などでの学習を経て、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
在留資格「介護」の特徴は以下の通りです。
- 在留期間は更新可能で、長期的な就労が可能(最長5年・更新に上限なし)
- 家族(配偶者・子)を帯同できる「家族滞在ビザ」の対象
- 職場の変更が可能
在留資格「介護」は就労・生活面での自由度が高く、日本に中長期的な滞在がしやすい点がメリットといえます。また、在留資格「介護」は、すでに国家資格を取得していることが前提のため、就労先にとっても即戦力としての期待が持てやすくなるのも特徴の一つです。
専門的な知識と技術を持ち、一定の日本語力も有している点から、現場へのスムーズな適応が期待できます。
特定活動(EPA介護福祉士候補者)
「特定活動(EPA介護福祉士候補者)」とは、日本がインドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国と締結している「経済連携協定(EPA)」に基づいて導入された在留資格制度です。
各国で選抜された候補者が日本へ渡航し、日本語研修や介護施設での実務経験を積みながら、国家資格「介護福祉士」取得を目指す長期育成型のプログラムとなっています。
EPAに基づく特定活動は国際的な信頼関係の下で運営されており、介護人材を中長期的に確保するための重要な受け入れ枠として位置づけられています。
特定活動(EPA介護福祉士候補者)の基本的なステップは以下の通りです。
- 母国で候補者選抜と日本語研修
- 日本入国後の研修・就労開始
- 国家資格「介護福祉士」を受験
特定活動(EPA介護福祉士候補者)は、「介護福祉士」を取得すれば在留資格「介護」を取得できるようになりますが、それまでは以下の条件での在留となります。
| 在留期間 | 最大4年 |
| 家族帯同 | 原則不可 |
| 転職 | 原則不可 |
特定活動(EPA介護福祉士候補者)はあくまで候補者の育成期間とされているため、就労の自由度は制限される点には注意が必要です。
ただし、国家試験に合格し在留資格「介護」へ移行すれば、ほかの施設への転職や家族の帯同も可能になります。特定活動(EPA介護福祉士候補者)は、即戦力よりも将来の戦力を育てる制度として設計されています。
国家資格取得を前提とした制度であるため、単なる労働力の受け入れではなく、専門性のある外国人介護人材を中長期的に確保したい施設にとって非常に有効です。
参考:在留資格「特定活動」(EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者) | 出入国在留管理庁
技能実習(介護)
技能実習(介護)は、日本が推進する外国人技能実習制度の一環として、2017年11月に新たに追加された職種です。技能実習(介護)は、開発途上国の若者が日本の介護技術や知識を学び、母国に持ち帰ることを目的とした「人材育成型の国際貢献制度」と位置づけられています。
就労ではなく「実習(研修)」が目的である点がほかの在留資格との大きな違いで、日本で介護の現場を体験し、最大で5年間の実習を通じてスキルを習得するのが基本的な流れです。
技能実習は1、2、3号の3つの区分に分かれており、介護に関しては以下の内容となっています。
| 区分 | 実習期間 | 対象施設 |
|---|---|---|
| 1号 | 1年 | 介護老人福祉施設・特別養護老人ホームなど |
| 2号 | 最大2年(合計3年) | 優良な受入機関で継続可能 |
| 3号 | さらに2年(合計最長5年) | 認定監理団体の下でのみ実施可 |
技能実習(介護)は、最長5年間日本の介護現場で実習を重ねられるため、介護職を目指す外国人にとって貴重な経験が積める制度です。
一方で、制度はあくまで「帰国前提」であり、日本での定住や長期雇用を目指す場合には特定技能や在留資格「介護」へのステップアップが必要です。
受け入れる介護施設側は、制度の趣旨と役割をしっかり理解した上での支援体制の構築が求められます。
特定技能1号(介護)
特定技能1号(介護)は、日本の慢性的な介護人材不足に対応するために創設された在留資格の一つです。特定技能1号は、即戦力となる外国人介護職を受け入れる制度であり、最長5年間就労できます。
また、一定の条件を満たせば、将来的に国家資格を取得し、在留資格「介護」への移行も可能です。
特定技能1号(介護)を取得するには、以下の2つの試験に合格する必要があります。
- 介護技能評価試験
- JLPT(日本語能力試験)N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)
なお、過去に技能実習2号(介護)を良好に修了した者や、EPA介護福祉士候補者として一定期間研修を受けた者は、試験の一部が免除される場合があります。
特定技能1号は就労を前提とした在留資格であり、現場で即戦力として勤務できるのが事業者側の大きなメリットですが、雇い入れる場合は「義務的支援」と呼ばれる以下の項目への支援を行う必要があります。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の際)
- 定期的な面談・行政機関への通報
出典:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁
特定技能1号(介護)は、日本の介護人材不足を補う即戦力人材の受け入れ制度として非常に有効ですが、長期的なキャリアを築くには「介護」資格への移行を見据えたプランが欠かせません。
さらに、義務的支援への対応も求められるため、法令に則った支援体制を整備し、外国人介護人材の定着と戦力化を図る必要があります。
参考:介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省
特定技能人材受け入れ時の「事前ガイダンス」とは?内容や実施時間を解説
特定技能外国人の住居確保ガイド|部屋の広さや責任の所在まで解説
在留資格「介護」と特定技能との在留期間などの違い一覧

在留資格「介護」と特定技能1号(介護)は、さまざまな項目で違いのある在留資格であるため、その違いを事前に理解しておくことが大切です。
在留資格「介護」と特定技能1号(介護)のおもな違いは以下の通りです。
| 項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号(介護) |
|---|---|---|
| 取得要件 | 国家資格「介護福祉士」の取得が必須 | 介護技能評価試験と日本語試験(N4以上)に合格 |
| 在留期間 | 無期限 | 最大5年(延長不可) |
| 家族帯同 | 可 | 原則不可 |
| 転職の可否 | 可 | 転職可能だが制限あり |
| 支援義務(企業) | 一般的な雇用管理義務のみ | 義務的支援が必要 |
上記のなかでも特に特徴的な違いが、取得要件のハードルと在留期間です。
まず取得要件のハードルでは、在留資格「介護」は、国家資格「介護福祉士」の取得が前提です。外国人が取得するには、養成施設に通って課程を修了し、国家試験に合格する必要があります。
一方で、特定技能1号(介護)は試験合格によって直接在留資格を取得できる制度です。介護技能評価試験と日本語能力試験(N4相当以上)に合格すれば、国家資格がなくても介護職に従事できます。
また、在留期間では在留資格「介護」は、更新によって長期在留が可能であり、在留期限に上限がなく、将来的には永住権の取得や家族の呼び寄せも可能です。対して、特定技能1号は最長5年までの在留に制限されており、期間満了後に継続して働くには在留資格「介護」資格への移行が求められます。
企業側にとっても、受け入れ制度によって支援義務や採用戦略が異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで制度を選ぶ必要があります。
在留資格「介護」の取得方法
在留資格「介護」の取得に必須となる条件が「介護福祉士」の合格です。
外国人材が介護福祉士に合格するための方法としては、おもに以下の3つがあります。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| ①日本の介護福祉士養成施設を卒業する | 外国人留学生が日本国内の介護福祉士養成校(専門学校・短大・大学など)に入学し、所定の課程を修了後、国家試験に合格して介護福祉士資格を取得する |
| ②介護施設で3年以上の実務経験+実務者研修を修了する | 日本の介護施設などで3年以上の実務経験を積み、あわせて実務者研修を修了することで、国家試験の受験資格を得る |
| ③EPA枠で来日→研修・実務経験を積む | 日本とEPAを結ぶ国の出身者は、EPA制度を利用して「介護福祉士候補者」として来日し、所定の研修と実務を経て国家試験に挑戦できる |
上記の3つが外国人による代表的な取得ルートですが、そのほかにも「福祉系高校ルート」などのルートも存在します。ただし、外国人の場合は在留資格や就学要件などの制限があるため、上記の3ルートが最も現実的となります。
在留資格「介護」取得外国人を企業が雇用する4つのメリット

在留資格「介護」取得外国人を企業が雇用するメリットはおもに以下の4つです。
ここでは、下記のメリットについて解説します。
|
1. 安定雇用ができる
在留資格「介護」を取得した外国人は、更新回数の制限がなく、在留期間の上限もないため、長期的な雇用が可能です。特定技能1号などのほかの在留資格では制限がありますが、在留資格「介護」はこのような年限がなく、本人が希望し企業が雇用を継続すれば、制限なく働き続けられます。
外国人材が長く職場に定着すれば、現場の業務が安定し、利用者との信頼関係やサービスの質向上にもつながる点が大きなメリットです。
2. 専門性のある人材確保ができる
在留資格「介護」を取得している外国人は、国家資格「介護福祉士」を保有しているのが前提なため、介護に関する専門知識と実務スキルを兼ね備えた即戦力として、採用後すぐに現場で活躍できます。
また、介護福祉士を持つ人材は、認知症ケア・重度介護・終末期ケアなど、より専門性の高い業務にも柔軟に対応可能です。多様化する介護現場のニーズに応じて、即戦力かつ専門性のある人材を確保できる点は、在留資格「介護」取得者を採用する大きなメリットといえるでしょう。
3. 人手不足の解消ができる
現在の日本の介護業界は、高齢者の増加に対して介護職に就く若年層が年々減少しており、多くの介護施設が人手確保に苦心しています。
人手不足が進む現状において、在留資格「介護」を持つ外国人は国家資格を取得した即戦力として現場に加われる貴重な人材です。また、一定の日本語力と専門スキルを持ち、就労に制限がないため、フルタイムで安定的に働いてもらえる点も大きなメリットです。
さらに慢性的な人手不足が解消されれば、夜勤体制やシフトの安定、サービス提供の継続性が確保され、利用者へのケアの質も維持しやすくなります。
在留資格「介護」の外国人材は、単なる人手補充ではなく、介護現場全体の生産性とサービスの安定性を支える戦力として、今後ますます重要な存在になるといえます。
4. 多様性のある職場づくりができる
在留資格「介護」を取得した外国人の受け入れは、単なる人手確保にとどまらず、多様性のある職場づくりを実現する大きなチャンスとなります。
多様な背景を持つスタッフの視点は、これまでにない柔軟な発想や新しいケアの工夫を生み出し、利用者に寄り添ったサービスの質向上にもつながります。
また、外国人スタッフと日本人スタッフが協働するなかで、互いに異文化への理解が深まり、コミュニケーション・チームワークの質も高められるのもメリットの一つです。
特定技能で「訪問介護」が4/21から解禁!受け入れ要件について解説
在留資格「介護」取得外国人を企業が雇用する3つのデメリット

在留資格「介護」取得外国人を雇用する際には、以下のデメリットに注意しておく必要があります。
ここでは、下記のデメリットについて解説します。
|
1. 採用・教育コストが高い
在留資格「介護」を取得した外国人を雇用する場合、採用から就労開始までにかかるコストが高くなりやすいのがデメリットの一つです。
外国人雇用でかかる特有のコストはおもに以下の通りです。
- 渡航費
- 在留資格申請
- 日本語教育
- 生活支援
- 導入研修 など
また、言語や文化の違いに配慮した教育が求められるため、教育にかかる手間と時間も増加する可能性がある点にも注意が必要です。
2.意思疎通に課題がある
在留資格「介護」を取得した外国人は、国家資格「介護福祉士」を保有しているため、一定の日本語能力を有していますが、実際の職場では日本語力に個人差があるのが実情です。
介護現場では、利用者との丁寧な会話、職員間での細かな情報共有、緊急時の的確な対応など、高いレベルでのコミュニケーションが求められますが、場合によっては意思疎通が難しい可能性があります。
可能な限り外国人材と円滑にコミュニケーションを取るために、やさしい日本語の使用や、図解・マニュアルの活用など、理解しやすい伝達方法を検討する必要があります。
3.文化・習慣の違いによるトラブルがある
在留資格「介護」を取得した外国人は、日本語や介護技術の研修を経て国家資格を取得していますが、母国との文化や価値観の違いが原因で、職場における誤解やトラブルが生じる場合があります。
特に、日本の介護現場では「時間厳守」や「報連相(報告・連絡・相談)」といった、集団行動や職場内の暗黙のルールが重視されがちです。
しかし、母国の価値観では時間に対する考え方や上下関係の捉え方が異なる場合があり、そこで無意識のうちに認識のズレが生じてしまうことがあります。
文化・習慣の違いによるギャップは、双方の理解不足から摩擦の原因になりやすいため、定期的な相互理解の場や、異文化研修の導入により解消を目指す必要があります。
在留資格「介護」のまとめ

在留資格「介護」は、国家資格「介護福祉士」を取得した外国人が、日本の介護施設で長期的かつ安定的に就労できる制度です。特定技能や技能実習などと比べて在留期間の制限がなく、家族帯同も可能なため、定着率の高い優秀な人材を確保したい企業にとって、非常に有望な選択肢となっています。
取得方法には、日本の養成校を卒業して国家試験に合格するルート、実務経験と実務者研修を経て合格するルート、EPA制度を活用するルートの3つがあり、自社の受け入れ体制に応じて適切な人材確保が可能です。
企業側が在留資格「介護」を持つ外国人を雇用するメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
上記のメリット・デメリットを理解し、事前の準備や支援体制を整えられれば、在留資格「介護」の外国人材をより効果的に活用できるでしょう。