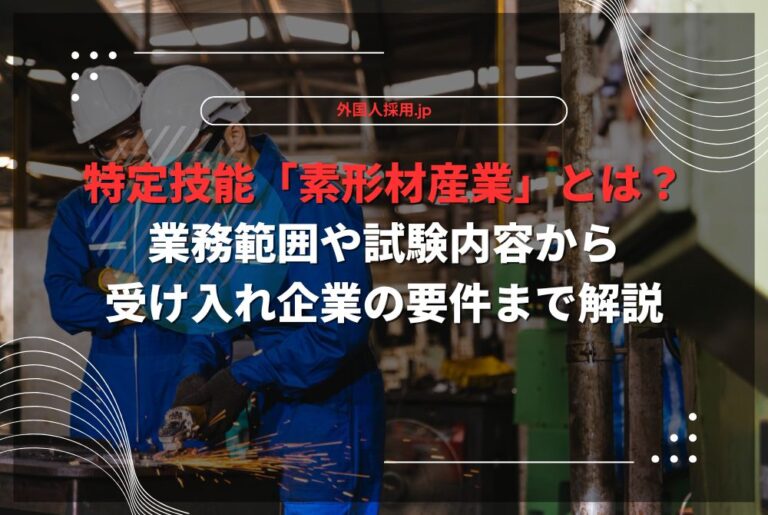日本の製造業を支える重要な分野の一つが「素形材産業」です。鋳造や鍛造、金属プレス、工業炉製造など、多岐にわたる工程を担い、自動車や機械部品の基盤を築いています。
そんな素形材産業でも深刻な人手不足が進んでおり、これを解消するために外国人材の受け入れを目的とした特定技能の「素形材産業」が導入されました。
本記事では、特定技能「素形材産業」の業務範囲や試験制度、受け入れ企業が満たすべき要件まで、わかりやすく解説します。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能「素形材産業」とは?

特定技能「素形材産業」とは、製造業を支える金属やプラスチックの成形・加工・表面処理などを担う分野で、2019年4月に新設された在留資格「特定技能」の対象の一つです。
制度スタート当初は「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」が個別に存在していました。しかし、2022年5月に一括して「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と変更されたため、手続きも制度の運用もよりシンプルになりました。
雇用形態は直接雇用のみで派遣は認められておらず、最大で5年の在留が可能です。
なお、制度の詳しい概要や最新情報は経済産業省の以下のページをご確認ください。
出典:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野) (METI/経済産業省)
特定技能「素形材産業」の業務範囲
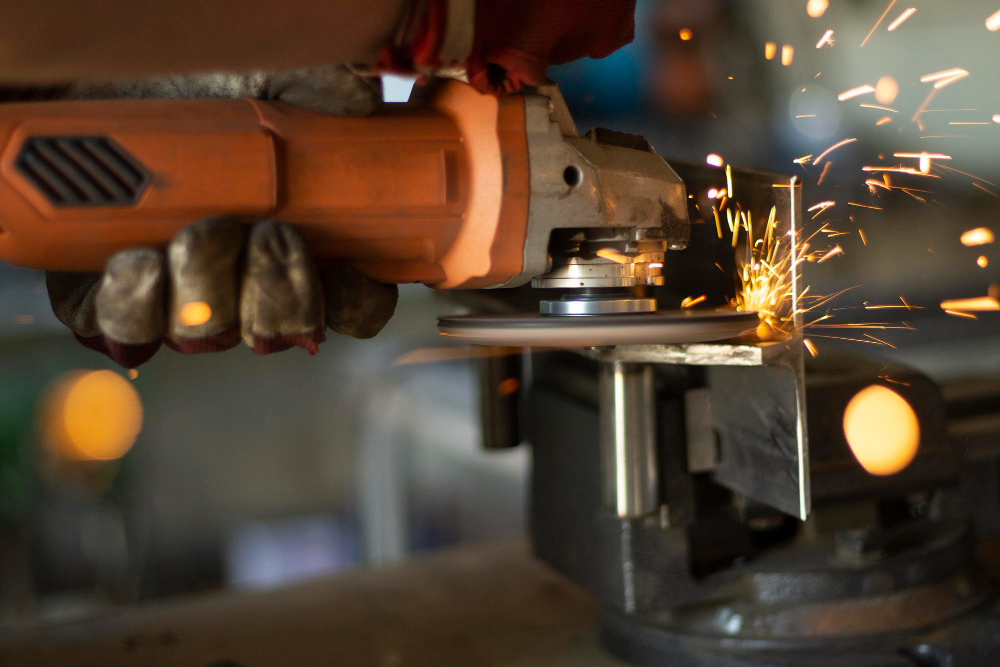
特定技能「素形材産業」は3つの区分に分かれており、受け入れ可能な業種が幅広いのが特徴の一つです。
区分ごとの特徴と受け入れ可能な業種は以下の通りです。
| 区分 | 特徴 | 業種 |
|---|---|---|
| 機械金属加工 | 金属素材の成形・加工・組立などを担う工程で、おもに機械や工具を用いて製品部品を加工する業務が該当 | 鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、鉄工、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、溶接、塗装、機械検査、機械保全、工業包装、電気機器組立て など |
| 電気・電子機器組立て | 家電や電子機器などの部品を組み立てる業務が該当 | 機械加工、仕上げ、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造、機械検査、機械保全、工業包装、プラスチック成形 など |
| 金属表面処理 | 金属製品の耐久性や外観を向上させる処理作業が中心 | めっき、アルミニウム陽極酸化処理など、金属製品の表面を耐久性や装飾性の向上を目的に処理する作業 など |
なお、上記の区分は完全に独立しているわけではなく、「機械加工」や「仕上げ」「プラスチック成形」など、複数の区分に共通する業務も存在します。
作業内容によってはラインの前後工程や運搬、メンテナンス、清掃作業なども含まれるため、柔軟な人材配置が可能です。
受け入れを検討する企業は、自社の業務が素形材産業の区分に該当するかを事前に確認しておくことが重要です。
特定技能「素形材産業」の取得方法

特定技能「素形材産業」の取得方法は以下の通りです。
|
指定の試験に合格する
技能実習を実施していない外国人材が特定技能「素形材産業」を取得するためには、以下の「技能試験」と「日本語試験」の試験に合格する必要があります。
また、日本語試験はJLPT(N4以上)またはJFT‑Basic(A2以上)に合格しなければなりません。受験は国内外で可能で、申し込みは特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイトから行えます。
試験の詳細につきましては以下の特定技能外国人材制度ポータルサイトをご確認ください。
技能実習2号を「良好に修了」する
技能実習2号を良好に修了した外国人材は、特定技能取得に必要な技能試験および日本語試験が免除されます。
「良好な修了」は以下の条件をクリアした際に認定されます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 実習期間 | 技能実習1号:1年+技能実習2号:1年10ヶ月以上(合計2年10ヶ月以上) |
| 技能評価 | 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格または実習実施者による評価調書(出勤状況・技能習得・生活態度などが「良好」) |
技能実習2号を「良好に修了」するルートなら試験の準備・費用・手間が不要で、採用後の定着もスムーズに進みやすいため、メリットの大きい方法といえます。
特定技能1号から2号への移行方法を徹底解説!要件や試験内容も紹介
特定技能「素形材産業」技能評価試験の内容

特定技能「素形材産業」技能試験の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験区分 | 学科試験(30問)+実技試験(10問) |
| 出題形式 | CBT方式またはペーパーテスト方式 |
| 試験時間 | 合計80分(学科+実技) |
| 合格基準 | 学科:正答率65%以上
実技:正答率60%以上 |
| 試験内容 | 共通問題+業務区分ごとの専門問題/日本語で出題、ふりがな付き |
| 試験会場 | 国内:仙台・水戸・東京・金沢・浜松・名古屋・岐阜・大阪・広島・福岡など
海外:インドネシア・フィリピン・タイなど |
| 開催日程 | 国内:年3回(例:6月下旬・10月中旬・12月下旬)
海外:年1回(例:9月上旬) |
| 申込方法 | ポータルサイトから申し込み(試験の約1か月前から受付、先着順・会場ごとに定員あり)
申し込みURL:製造分野特定技能評価試験 |
なお、受験会場ごとに定員があり、150名~400名程度の場合もあるため、早めの申し込みが大切です。
企業の特定技能「素形材産業」取得外国人の受け入れ要件

企業の特定技能「素形材産業」取得外国人を受け入れるために満たすべき要件は以下の通りです。
ここでは、下記の要件について解説します。
|
日本標準産業分類で定められた業種に該当する
特定技能「素形材産業」の受け入れ対象企業となるには、経済産業省が定めた日本標準産業分類で30種類以上ある製造業種に該当している必要があります。
日本標準産業分類で定められた業種の例は以下の通りです。
- 鋳型製造業(中子を含む)
- 鉄素形材製造業・非鉄金属素形材製造業
- 金属熱処理業・電気めっき業・溶融めっき業
- 機械刃物・作業工具製造業
- 配管工事用附属品製造業(バルブ・コック除く)
- ボルト・ナット・リベット等製造業
- 電子部品・デバイス・電子回路製造業
- 電気機械器具製造業
- 情報通信機械器具製造業
- 工業用模型製造業 など
また、重要なポイントとして、判定は「会社全体」ではなく「事業所単位」で行われます。例えば、本社が非該当でも、製造拠点や支社が対象業種に該当する場合、その事業所では外国人の受け入れが可能です。
そして、受け入れを行う事業所では、直近1年間に製造品の出荷実績などの経済活動が行われている実態も求められます。
認定には以下のいずれかの実績が必要です。
- 製造品出荷額
- 他社からの加工賃収入
- 製品修理や補修に関する収入
- 製造工程で発生したくずや副産物の売却収入 など
上記の実績は、単なる業種該当性だけでなく、実態として製造活動が継続されているかを確認するための重要な判断材料となっています。
外国人雇用を検討している企業は、まずは該当業種かどうかを明確にした上で、必要な証明資料の準備を進めるのがスムーズな申請につながります。
特定技能協議会に加入する
特定技能制度では、分野ごとに設置されている特定技能協議会に企業(所属機関)が加入することが義務付けられています。申請には必要書類の提出と審査があり、在留資格の申請前までに加入が完了している必要があります。
協議会への加入は以下の特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイトから可能です。
出典:特定技能外国人材制度
特定技能の協議会とは?加入要件や費用から分野別一覧までを紹介
適切な支援体制を整備する
企業は、採用後には外国人材の生活支援や業務管理などについて責任を持って対応しなければなりません。ただし、自社でこうした支援の実施が難しい場合は、外部の登録支援機関への委託が可能です。
登録支援機関は、法務省に登録された専門機関で、外国人材の住居探しや日本語学習支援、生活ガイダンスの実施など、制度上必要とされる支援業務を代行する機関です。
企業は、自社で全ての支援を行うか、一部または全部を登録支援機関に委託するかを選択できますが、以下に該当する場合は企業が自ら支援を行えず、支援業務のすべてを登録支援機関に委託する必要があります。
- 過去2年以内に外国人材の受け入れ実績がない場合
- 社内に適任の支援責任者または支援担当者がいない場合
なお、実際のケースでは企業が自社ですべての支援業務を担うのは難しい場合が多いため、一部もしくは全部を委託するのが一般的です。
支援体制の整備は、外国人材の定着とトラブル防止にも直結する重要なポイントの一つです。
特定技能外国人の住居確保ガイド|部屋の広さや責任の所在まで解説
特定技能人材受け入れ時の「事前ガイダンス」とは?内容や実施時間を解説
特定技能「素形材産業」取得外国人採用の流れ

特定技能「素形材産業」取得外国人採用の流れは、外国人材が採用時点で国外在住か国内在住かで異なります。
ここでは、国外・国内それぞれのケースでの流れについて解説します。
|
国外在住の場合
国外在住の外国人材を採用する場合の一般的なフローは以下の通りです。
1.人材を募集し、面接を行う
海外在住の候補者は、現地の人材紹介会社や派遣・エージェントを通じて募集されるケースが多く、遠隔面接(オンライン形式)での選考も一般的です。
特に特定技能制度では、該当分野の試験に合格していることが必須条件となるため、面接の際にはその資格についての確認が大切です。
2.特定技能の雇用契約を結ぶ
選考を通過したら、雇用条件(仕事内容・賃金・労働時間・福利厚生など)を明示した正式な雇用契約を結びます。特定技能では、日本人同様の労働条件が求められるため、契約内容は制度要件に準拠する必要があります。
3.外国人支援の計画を立てる
「1号特定技能支援計画」と呼ばれる、外国人が安心して生活し働けるようさまざまな支援を体系的に計画します。支援には、住居の確保、公的手続きのサポート、日本語学習機会の提供、定期面談など多岐に渡る支援項目が含まれます。
4.「特定技能」の在留資格を申請
在留資格の申請には、国外在住者の場合「在留資格認定証明書交付申請」が該当します。申請書類一式を出入国在留管理庁に提出し、審査・許可を得るまでにはおおよそ1〜2ヶ月かかるケースもある点には注意が必要です。
5.許可が出たらビザを取得
在留資格認定証明書が発行されたら、現地の日本大使館や領事館へ持参し、ビザの取得手続きを行います。
6.日本へ渡航し、勤務開始
ビザが発給されたら渡航可能なため、入国後すぐに勤務が始められる準備を整えておくことが大切です。雇用主は、受け入れ後も支援計画に沿ったサポートを継続する必要があります。
上記のフローを事前に把握し、各ステップで漏れなく対応するように心がけましょう。
国内在住の場合
国外在住の外国人材を採用する場合の一般的なフローは以下の通りです。
1.人材を募集し、面接を行う
まず、日本在住の外国人で「技能評価試験・日本語試験に合格済」または「技能実習2号を良好に修了した方(試験免除適用)」など、特定技能の要件を満たす人材を対象に、募集・面接を行います。
募集の際は試験の状況や在留ステータスの確認がポイントです。
2.特定技能の雇用契約を結ぶ
面接に合格したら、法令に準拠した「特定技能雇用契約」を締結します。雇用条件や業務内容は特定技能制度の基準をクリアしている必要があり、書類は後の申請で提出します。
3.外国人支援の計画を立てる
「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、生活・業務両面の支援を計画的に整えます。支援体制が不足していれば、登録支援機関への委託も可能です。
4.在留資格の変更を申請する
制度要件をクリアしたら、該当する入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。通常、審査にかかる期間は1~3ヶ月程度です。
5.許可が下りたら勤務開始
在留資格変更が許可されると、新しい在留カードが発行され、特定技能1号としての就労が正式に始められます。就労後は支援計画に基づいて継続的なサポートや報告義務があります。
「国内在住ルート」は、在留資格認定証明書の交付手続き(国外在住者用)よりもスムーズです。特に、日本にいる留学生や技能実習経験者を採用する企業にとっては、迅速なスタートが可能な方法といえます。
特定技能「素形材産業」のまとめ

特定技能「素形材産業」分野は、日本の製造業を支える重要な人材確保の手段として注目されています。
鋳造・鍛造・機械加工・電子部品組立てなど、幅広い製造業務に対応したこの制度を活用することで、企業は即戦力となる外国人材を雇用できます。
採用の流れは、国内在住者と国外在住者とで手続きが異なりますが、以下のようなプロセスで進むのが一般的です。
- 人材の募集と面接を実施
- 特定技能の雇用契約を締結
- 外国人支援計画の策定(または登録支援機関へ委託)
- 在留資格の「取得」または「変更」を申請
- 許可後にビザ発給(国外)または勤務開始(国内)
採用の際は、単に労働力を確保するという観点だけでなく、制度に即した適正な受け入れ体制の整備が必要不可欠です。
また、受け入れ時に満たす必要のある要件は以下の通りです。
- 日本標準産業分類における、鋳型製造・金属表面処理・電子部品製造などの対象業種に該当していること(事業所単位で判断)
- 直近1年間に製造品出荷額などの実績があること
- 特定技能協議会への加入が完了していること
- 外国人材に対する支援体制の整備(支援責任者の配置 or 登録支援機関への委託)
特に、初めて外国人材を採用する企業は、支援の委託が義務付けられる場合があるため、事前に自社の体制を確認し、必要に応じて登録支援機関との連携も検討するようにしましょう。
特定技能制度は「外国人雇用のハードルを下げる制度」である一方、法令に基づいた正確な運用が求められます。本記事を参考に、特定技能「素形材産業」分野の採用を進めていただければ幸いです。
ご質問・お問い合わせは以下のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。