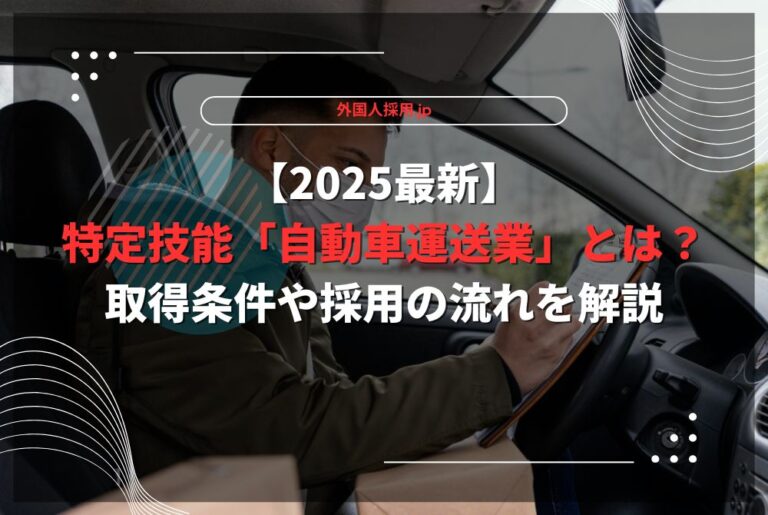2024年3月より新たに対象分野となった特定技能「自動車運送業」は、深刻な人手不足に直面する物流業界を支えるために導入されました。外国人材が長距離・中距離輸送や配送、旅客運送業務に従事できる道を開き、安定した人材確保につながると注目されています。
本記事では、特定技能「自動車運送業」の取得条件や求められる技能水準、企業側が知っておくべき採用の流れをわかりやすく解説します。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能「自動車運送業」とは?

特定技能「自動車運送業」とは、深刻な人材不足に直面しているトラック・バス・タクシー業界において、一定の技能と日本語力を持つ外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。
2019年に創設された特定技能制度において、2024年3月に新たに追加され、同年12月から本格運用が始まりました。対象となるのは、貨物自動車運送事業(トラックドライバー)、旅客自動車運送事業(バスドライバー・タクシードライバー)の3分野です。
業務には単に運転だけでなく、運行前後の点検、安全記録の作成、乗客対応なども含まれます。また、雇用形態は派遣や短時間雇用は認められておらず、直接雇用・フルタイムでの就労が原則です。
特定技能「自動車運送業」は、人手不足を補うための即戦力となる制度でありつつ、労働環境や安全対策を重視した仕組みとして運用されています。
特定技能とは?技能実習との違いや1号・2号の特徴、採用方法を解説
特定技能1号から2号への移行方法を徹底解説!要件や試験内容も紹介
自動車運送業分野が特定技能に追加された背景

自動車運送業分野が特定技能に追加された背景には、おもに以下の3つが挙げられます。
ここでは、下記の背景について解説します。
|
人手不足のさらなる深刻化
自動車運送業界では、慢性的な人手不足が大きな課題となっています。2024年10月時点の自動車運転従事者の有効求人倍率は2.67と全産業平均の1.27を大きく上回って推移しており、人材確保が極めて困難な状況であるのを示しています。
そのため、外国人材の雇用が可能になるように規制緩和が進むようになりました。
ドライバー高齢化の進行
自動車運送業界では、ドライバーの年齢構成に偏りが見られます。国土交通省などの調査によると、40歳以上の中高年層が多数を占めており、特に40~54歳のドライバーが約45%に達しています。
一方で、29歳以下の若年層は全体の1割に満たない水準にとどまっており、若手の担い手不足が深刻化しているのが現状です。また、トラック運転手の平均年齢は全産業の平均よりも4~6歳ほど高いとされており、この点からも業界全体が高齢化に傾いている傾向が示されています。
大型・中型を問わずこの傾向は共通しており、若手ドライバーの採用・定着が大きな課題です。
物流を揺るがす「2024年問題」
物流業界における「2024年問題」は、2024年4月から「自動車運転業務における時間外労働の上限が年間960時間に設定された」改正を指します。この制度改正は、働き方改革の一環として労働環境の改善を目指すものであり、ドライバーの過労防止や定着率向上などの効果が期待されている点が特徴です。
一方で、稼働時間の制限により輸送能力が大幅に低下する懸念も指摘されており、2030年度には輸送力が最大34%にまで低下するおそれがあるとの試算もあります。EC市場の拡大や高齢化社会に伴う物流需要の増加が続くなか、ドライバー不足と輸送力不足が同時進行で進んでいるのが現状です。
特定技能「自動車運送業」の業務区分

特定技能「自動車運送業」の業務区分は、以下の3つとなっています。
|
1. トラック運送業(貨物輸送)
特定技能「自動車運送業」におけるトラック運送業(貨物輸送)は、以下のような主業務と関連業務に分けられます。
| 区分 | 概要 | 該当する業務 |
|---|---|---|
| 主業務 | おもに従事する業務 | ・出発前・到着後の車両点検
・指定先までの貨物輸送の運転 ・フォークリフト等による・荷役作業(積み下ろし・固定など) ・乗務記録の作成・管理 |
| 関連業務 | 主たる運行業務や荷役業務の「付帯的な範囲」に限定して行える業務 | ・車両清掃
・営業所内清掃 ・洗車作業 |
トラック運送業における特定技能1号人材は、安全な車両運行と貨物輸送、荷役、乗務記録など、運転者としてのコア業務への従事が求められます。
付帯作業として清掃や準備作業などに部分的に携わるのは認められますが、それらのみを担うのは制度趣旨から外れるため禁止されています。
2. バス運送業(路線・観光・高速バス)
特定技能「自動車運送業」におけるバス運送業では、以下のような主業務と関連業務に分けられます。
| 区分 | 概要 | 該当する業務 |
|---|---|---|
| 主業務 | おもに従事する業務 | ・出発前後の車両点検と安全運行の確保
・乗降時の声かけ・案内・運賃対応 ・定時運行の遵守 ・乗務記録の作成 |
| 関連業務 | 主たる運行業務や荷役業務の「付帯的な範囲」に限定して行える業務 | ・車内清掃
・営業所内清掃 ・運賃精算や管理等の業務 |
バス運送業もトラック運送業と同じく清掃業務だけを主業務として行うのは禁止されており、さらにそれに加えて精算や管理業務も禁止項目に含まれている点には注意が必要です。
3. タクシー運送業(旅客輸送)
特定技能「自動車運送業」におけるタクシー運送業では、以下のような主業務と関連業務に分けられます。
| 区分 | 概要 | 該当する業務 |
|---|---|---|
| 主業務 | おもに従事する業務 | ・運行前後の車両点検と安全な運転
・丁寧な接遇(ドアサービス含む)要望対応などの接客業務 ・営業記録の作成・管理 |
| 関連業務 | 主たる運行業務や荷役業務の「付帯的な範囲」に限定して行える業務 | ・車内清掃
・営業所内清掃 ・運賃精算や管理等の業務 |
タクシー運送業でもバス運送業と同様に清掃および精算、管理業務のみを専任で行うのは禁止されています。
自動車運送業における特定技能外国人受け入れの条件

自動車運送業における特定技能外国人受け入れの条件は、企業側と人材側で異なる点があります。
ここでは、それぞれの立場からの条件について解説します。
|
企業側の要件
企業側の要件は、以下のように共通要件と業種ごとの要件で分かれています。
【共通要件】
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 協議会への加入 | 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入が必要 |
| 行政調査への協力 | 国土交通省や委託機関による調査・指導に応じる義務がある |
| 直接雇用の義務 | 自動車運送業における特定技能人材は必ず直接雇用でなければならない |
| 登録支援機関の条件 | 外国人の生活支援などを登録支援機関に委託する場合、その支援機関も協議会の構成員である必要がある |
【業種ごとの要件】
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| トラック運送業 | ・一般貨物自動車運送事業の許可を取得
・以下いずれかの認証が必要 「働きやすい職場認証(運転者職場環境良好度認証)」 「Gマーク(安全性優良事業所)」 |
| バス運送業 | ・一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得
・「働きやすい職場認証」の取得が必須(Gマークのみでは不可) ・新任運転者研修の実施 |
| タクシー運送業 | ・乗合・貸切・特定旅客自動車運送事業のいずれかの許可を取得
・「働きやすい職場認証」の取得が必須(Gマークのみでは不可) ・新任運転者研修の実施 |
企業が特定技能外国人を受け入れるには、制度の趣旨に基づいた雇用体制と、安全・安心な就労環境の整備が不可欠です。
特に、「働きやすい職場認証」や「Gマーク」の取得、新任研修の実施など、外部評価や社内教育体制の充実が求められる点には注意が必要です。
本人の要件
特定技能「自動車運送業」で働くには、外国人本人にもクリアすべき条件があり、共通要件と業種ごとの要件に分かれています。
【共通要件】
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 技能評価試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格する必要がある |
| 日本語能力 | トラック:JLPT N4以上またはJFT-Basic
タクシー・バス:JLPT N3以上 |
| 運転免許 | ・日本国内で有効な運転免許取得(区分ごとの車種に応じた種別)
・トラック運送業の場合、外国免許からの切替も可能 |
【業種ごとの要件】
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| トラック運送業 | 技能評価試験(トラック区分)の合格 |
| バス運送業 | ・技能評価試験(タクシー区分)に合格
・新任運転者研修の修了証提出 |
| タクシー運送業 | ・技能評価試験(バス区分)に合格
・新任運転者研修の修了証提出 |
本人側の要件を満たすためには、業種に応じた免許と技能評価試験の合格が必要で、一定水準以上の日本語能力も求められます。
特定技能「自動車運送業」保有外国人の採用までの流れ

特定技能「自動車運送業」保有外国人の採用までの流れは一般的に以下の通りになります。
ここでは、下記の流れについて解説します。
|
1. 企業が受け入れ要件を満たしているか確認する
特定技能「自動車運送業」保有の外国人を採用する際には、まず自社が受け入れ要件を満たしているかの確認を行う必要があります。
一つでも要件を満たしていない場合は、雇用は認められずビザの申請も許可されません。採用のスタート地点として、まずは制度に適合した企業体制が整っているかを客観的に見直すことが、スムーズな受け入れ・中長期的な人材の活躍につながります。
2. 採用したい外国人材が条件を満たしているか確認
特定技能「自動車運送業」では、採用を希望する外国人材が制度上の要件を満たしているかを事前に確認する必要があります。特に、タクシー運送業やバス運送業では旅客を扱うため、日本語レベルや第二種免許の取得、新任研修の修了が厳しくチェックされます。
一方で、トラック運送業では第一種免許の取得が要件となりますが、外国免許の切り替えにも対応しており、日本語の基準がやや緩やかなため比較的受け入れがしやすい傾向にあります。
3. 候補者を探して、面接で適性を見極める
自社の受け入れ体制が整い、採用要件を満たす人材像が明確になったら、実際の候補者探しと面接のフェーズに移ります。特定技能人材は、一般的な採用と比べて確認すべきポイントが多いため、事前準備と慎重な見極めが重要になります。
候補者を探す際におすすめの方法は以下の通りです。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 登録支援機関を活用 | ・特定技能制度に精通している支援機関を通じて、国内外の人材を紹介してもらう方法
・面談設定や通訳対応、採用後の支援も一括して依頼できる点がメリット |
| 人材紹介会社を活用 | ・外国人材の採用に実績のある人材会社を活用する方法
・求職者とのマッチングや、書類の確認・調整業務まで一貫して依頼できる |
| ハローワークで募集 | 費用を抑えたい場合や、制度を利用して雇用を進めたい中小企業に向いている |
上記の方法で応募者が集まれば書類選考を行い、通過者には面接を行うのが一般的なフローです。
面接の際に確認すべき項目は以下の通りです。
- 運転経験・技能の有無
- 日本語でのコミュニケーション力
- 日本の交通ルール・マナーの理解
- 安全意識と責任感
候補者探しと面接は、特定技能外国人の採用において非常に重要な工程です。適切な人材を見極めるためには、制度や業務内容を正しく理解した上で、ポイントを押さえた選考を行う必要があります。
また、面接ではスキルだけでなく、文化・価値観への適応力や真摯な姿勢も見逃さずに評価するようにしましょう。
4. 外国人材との雇用契約を正式に結ぶ
面接を経て採用が決定したら、次に行うのが「雇用契約の締結」です。特定技能制度に基づく雇用契約は、一般的な労働契約よりも詳細な規定が求められます。
特定技能での雇用契約で求められるおもなポイントは以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 日本人と同等以上の待遇 | 同等の業務を行う日本人と比較して、同等以上の給与・手当・労働条件であることが求められる |
| 健康診断の実施 | 雇用前に健康診断を実施し、結果を保存しておく必要がある |
| 契約内容および事前ガイダンスを母国語で説明 | ・雇用契約の内容を外国人本人の母語で説明することが義務付けられている
・業務内容・報酬・労働条件・支援体制・注意事項などを含めた「事前ガイダンス」も、本人が理解できる言語で実施する必要がある |
上記の項目を遵守した雇用契約を結ぶと、外国人材に適切な待遇を保証でき、安心して働ける環境が整います。
また、制度に沿った手続きを確実に行うのは、企業側にとってもビザ申請の承認率向上やトラブル回避につながる大切なポイントになります。
5. 必要な試験(技能・日本語)に合格しているか確認する
特定技能での採用を進めるうえで、技能試験と日本語試験の合格は欠かせない条件です。採用候補者が両方に合格済みであるか、または確実に受験・合格予定であるかを早い段階で確認しましょう。
6. 日本の運転免許を取得する
特定技能「自動車運送業」の在留資格で就労するには、日本国内で有効な運転免許を取得していなければなりません。外国人材が免許を未取得の場合は、日本の教習所に通うか、母国の運転免許を日本のものに切り替える必要があります。
免許取得・切り替えに対して企業側が以下のようなサポートを行える体制を整えると、スムーズな採用・就労につながります。
- 教習所や運転免許センターとの連絡・調整
- 学科・実技対策の教材提供や学習サポート
- 申請書類の翻訳や通訳の手配
- 試験費用や交通費の一部補助
- 外免切替のための必要書類(免許証の翻訳、公的証明等)の準備支援 など
免許取得は、採用後の実務に直結する重要な要素の一つであるため、在留資格申請や実際の乗務に向けて準備を整えておく必要があります。
7. タクシー・バスの場合は乗務前に研修を実施
旅客を扱うタクシーやバスでは、安全・接遇の観点から「新任運転者研修」の受講と修了が法的に義務づけられています。
新任運転者研修の内容は以下の通りです。
- 座学研修
- 実技・路上走行研修
- 適性診断
上記の内容の法令に基づいた安全教育と接遇研修を修了しておくと、乗務前の準備が整い、現場でのトラブルを未然に防止できます。
8. 特定技能「自動車運送業」を申請する
条件が整い次第、特定技能「自動車運送業」を申請します。
日本にすでに滞在している方と、海外から来日する方で以下のように手続き方法が異なります。
| ケース | 手続き方法 |
|---|---|
| 日本にすでに滞在している | 現在の在留資格から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を出入国在留管理局へ提出 |
| 海外から来日する | ・雇用契約が成立した段階で、「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理局で行う
・認定証を取得した後、現地の日本大使館や領事館で査証(ビザ)を取得すれば来日可能となる |
上記にあるように、国内在住か海外在住かで手続きが異なり、特に海外在住の場合は取得できなければ来日することすらできないため、対象者の状況に応じて正しい申請方法で進めるようにしましょう。
9. 入社に向けた生活サポートと職場準備を行う
在留資格の許可が下り、外国人材の入社日が決定したら、企業が行うべき次のステップは「生活立ち上げの支援」と「職場環境の整備」です。安心して働き始めてもらうためには、仕事だけでなく日本での暮らし全体を支える視点が求められます。
特定技能制度では、受け入れ企業(または登録支援機関)が「義務的支援」として以下のような入社前後の生活支援を行うことが法律で義務付けられています。
- 事前ガイダンス
- 空港送迎
- 住居の確保支援
- 役所手続きへの同行
- 日常生活のオリエンテーション
- 日本語学習の機会提供
- 相談窓口の設置
- 地域交流の機会提供
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
特に登録支援機関に委託せず自社で全て手続きを進めている場合は、上記の義務的支援を過不足なく行えるように整備する必要があります。
特定技能外国人は派遣雇用できる?受け入れる時の要件や注意点を解説
特定技能「自動車運送業」のまとめ

自動車運送業界は現在、かつてない人手不足に直面しており、その解決策の一つとして2024年に「自動車運送業」が新たに特定技能の対象分野に追加されました。ただ、外国人ドライバーを雇用するには企業側にも明確な要件があります。
企業には、協議会への加入、職場認証の取得、許可された運送事業の運営、待遇面での日本人との平等、さらには登録支援体制の構築などが求められます。一方で、採用される外国人材にも、技能試験や日本語試験の合格、日本の運転免許の取得、新任運転者研修の修了など、厳格な条件が課されている点には注意が必要です。
特定技能制度は、単に人を雇う制度ではなく、文化や生活も含めた「受け入れ体制」の構築が求められる制度です。制度への正しい理解と準備がなければ、スムーズな申請や職場定着にはつながりません。外国人ドライバーの受け入れを本格的に進めたい企業は、特定技能制度の全体像と採用フローをしっかり把握した上で、計画的に準備を進めましょう。
なお、厚生労働省が特定技能に関するQ&Aをまとめた資料を公開していますので、疑問点があれば参考にしてください。
本記事へのご質問・疑問点がございましたら、以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。