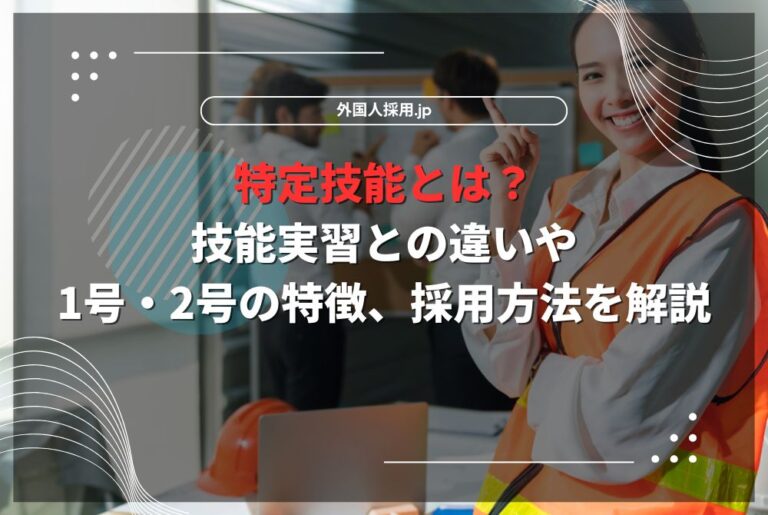人手不足が深刻化するなか、外国人材の雇用手段として注目されているのが「特定技能」です。従来の技能実習制度とは異なり、即戦力となる人材の受け入れを目的とした制度であり、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」に分かれています。
本記事では、特定技能の基本的な仕組みや技能実習との違い、1号・2号それぞれの特徴、企業が採用する際の流れやポイントについて、わかりやすく解説します。今後外国人材の雇用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能とは?

特定技能とは、日本国内における人手不足の解消を目的として、2019年に導入された新たな在留資格制度です。これまでの「技能実習制度」がおもに国際貢献を目的とし、技能の習得と帰国を前提としていたのに対し、「特定技能」は即戦力となる外国人材を受け入れるのがおもな目的です。
企業が特定技能の外国人を雇用するためには、出入国在留管理庁への届け出や支援計画の策定、生活支援体制の整備など、いくつかの要件を満たす必要があります。また、受け入れ後も継続的なサポートが求められ、言語や生活面の支援、相談体制の整備などが義務づけられています。
特定技能は、今後ますます広がる外国人材の活用において、企業にとっても重要な選択肢となる制度です。
特定技能と育成就労制度の関係

特定技能に深く関係する制度が「育成就労制度」です。育成就労制度は、技能実習制度の構造上の問題が引き起こしていた人権侵害や不適切運用への批判を受けて、厚生労働省が2024年に技能実習法を改正して創設された制度で、2027年施行予定です。
従来の研修・技能実習が国際貢献を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成と人材確保」を目的に設計され、在留期間は原則3年間、転籍制度の柔軟化、日本語基準の導入などを特徴としています。
さらに詳しい内容・運用の方針などは、厚労省から公開されている以下の資料を参考にしてください。
第1回育成就労懇談会資料|厚生労働省
育成就労制度により、技能実習制度の課題を解消しつつ、特定技能へのシームレスなキャリアパスが描かれる設計へと進化しました。特定技能制度は当初より即戦力育成が主眼でしたが、育成就労制度の導入により、特定技能へのスムーズな移行が前提となります。また育成就労で得た経験や技能を基に、一定要件を満たせば特定技能1号への移行が可能です。
さらに特定技能制度では、従来12分野だった受け入れ領域が、鉄道・林業・木材産業・自動車運送業などを加え16分野に拡大され、キャリア形成の自由度が高まりつつあります。
特定技能1号、2号のそれぞれの特徴

特定技能制度は、就労可能な分野や在留条件などに応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分類されています。どちらも即戦力としての就労が前提ですが、それぞれ在留期間、求められる技能水準、家族の帯同可否などに明確な違いがある点に注意が必要です。
ここでは、特定技能1号と2号の具体的な特徴について解説します。
- 特定技能1号と2号の具体的な特徴
-
- 特定技能1号の特徴
- 特定技能2号の特徴
特定技能1号の特徴
特定技能1号は、日本で即戦力として働くのを目的とした在留資格で、特定産業16分野に従事する外国人向けに設計されています。
特定技能1号のおもな特徴は以下の通りです。
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 在留期間 | 通算で最長5年、更新は1年・6か月・4か月ごと |
| 家族の帯同 | ・原則不可
・ただし、留学中の方の妻や子供がすでに「家族滞在」の資格を有している場合、在留資格を「特定活動」への変更が認められる場合あり |
| 支援体制の義務化 | 受け入れ企業や登録支援機関による、生活・就労に関する10項目を含む支援が義務 |
| 雇用形態 | ・基本は直接雇用
・ただし農業・漁業分野では派遣雇用も可 |
| 業務範囲 | 単純労働を含む、幅広い業務に従事可能(特定産業16分野) |
| 在留資格の移行 | 技能実習を修了した者は、試験免除などで移行可能 |
| 日本語能力要件 | 以下のいずれかの試験合格が必要
・JLPT N4以上 ・JFT‑Basic 200点以上(A2レベル相当) |
この特定技能と技能実習・外国人雇用との関係は以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 技能実習との連続性 | 特定技能1号は、技能実習2号を良好に修了した外国人がそのまま日本で働き続けられるステップアップ制度で、試験免除や在留資格の移行手続きがスムーズになるメリットがある |
| 外国人雇用の新たな選択肢 | 単純労働も含めた幅広い人材確保が可能となり、日本語能力・支援体制が制度上求められるため、安心して雇用できる仕組みになっている |
| 支援義務の強化 | 生活支援の義務化により、外国人が安定して定着しやすく、企業側も定着率向上やリスク管理に役立つ |
特定技能1号は、技能実習制度を土台に、より実用的・長期的な外国人雇用の仕組みを構築した制度といえます。
特定技能2号の特徴
特定技能制度では、「即戦力」を求める特定技能1号からさらにステップアップし、より高度な技能を持つ人材に門戸を開く「特定技能2号」が用意されています。
特定技能2号のおもな特徴は以下の通りです。
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 在留期間 | 更新回数に上限なし(3年・1年・6カ月ごとに更新)で、実質無期限の滞在が可能 |
| 家族の帯同 | 一定の条件(収入・住居など)を満たせば、配偶者・子(未成年)の帯同が可能 |
| 日本語能力要件 | 原則不要だが、外食業・漁業分野ではJLPT N3以上が必要となる場合あり |
| 永住権取得 | 長期在留と安定収入により将来的に永住申請の可能性あり |
| 雇用形態 | 原則直接雇用で、農業・漁業では派遣雇用も可 |
| 申請要件 | 対象分野で2年以上の実務・指導経験が必要(分野ごとに異なる) |
| 支援体制 | 1号のような支援義務なし |
特定技能1号とのおもな違いは以下の通りです。
- 在留期間:1号は最大通算5年、2号は更新制限なしで滞在可能
- 家族帯同:1号は原則不可、2号では配偶者・子の帯同可
- 日本語要件:1号はJLPT N4など必須、2号は原則不要(分野特例あり)
- 支援義務:1号では支援計画が義務付けられる一方、2号では不要
当初、2号は建設業と造船・舶用工業(溶接区分)の2分野に限定されていましたが、2023年以降、農業・漁業・外食業・宿泊・飲食料品製造・自動車整備など、計11分野と大幅に拡大されました。1号で培った技能をさらに高め、2号へシームレスに移行できるキャリアパスが一層充実し、企業にとっても長期雇用のポテンシャルを持つ人材を確保しやすくなっています。
特定技能1号、2号取得のそれぞれの要件

特定技能制度を活用して外国人を雇用するには、それぞれの在留資格に応じた取得要件を満たさなければなりません。特定技能1号と2号では、求められる日本語能力や技能レベル、実務経験の有無などに明確な違いがあります。
ここでは、特定技能1号と2号の取得に必要な要件をそれぞれ解説します。
- 特定技能1号と2号の取得に必要な要件
-
- 特定技能1号の要件
- 特定技能2号の要件
特定技能1号の要件
特定技能1号の取得には、主に以下の2つのルートがあります。
| 【① 試験による取得】 |
| 外国人が新たに特定技能1号を申請する場合、技能試験と日本語試験への合格が必須。 ・技能試験:各分野ごとに実施され、業務遂行に必要な基礎的技能があることを証明する試験。国外からでも受験可能。 ・日本語試験:JLPT N4以上またはJFT‑Basicで200点以上の合格が必要 |
| 【② 技能実習2号からの移行】 |
| 技能実習2号を良好に修了している場合は、以下の条件を満たすことで試験免除による移行が可能 ・特定技能1号の業務と関連性があること ・ 実習分野と特定技能1号で従事する業務に関連性がある場合、技能試験・日本語試験の全免除。 ・ 異なる業務分野への移行の場合、日本語試験のみ免除され、技能試験は必要になる |
1号の取得は上記の2ルートから選べますが、技能実習からの移行は申請者や企業にとって非常にメリットが大きく、スムーズな雇用継続が可能な点が大きなメリットです。一方、新規申請者向けには試験対策(技能+日本語)が必要となり、しっかりとした準備が重要です。
特定技能2号の要件
特定技能2号は、より高度な技能を活かして日本で長期的に働くための在留資格です。取得には、熟練度を示す技能試験への合格と、一定の実務経験および日本語能力が求められます。
詳しい内容は以下の通りです。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 技能レベル | 特定技能2号評価試験(各分野)または技能検定1級合格が必須 |
| 実務経験 | 対象分野で2年以上の管理・指導経験が必要 |
| 日本語能力 | ・原則不要だが、漁業・外食業ではJLPT N3以上が必要
・ただし、試験はすべて日本語、ルビなしで実施されるため、現場運用に耐える言語力が実質求められる |
特定技能2号の取得には、高度な専門技能、実務経験、そして一定レベルの日本語力が不可欠です。より専門的かつ責任ある役割を担う人材として、日本企業に深く定着するために設計された資格といえます。
特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習の違いは以下の通りです。
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 労働力不足の解消 | 国際協力 |
| 人数制限 | 原則なし(※介護・建設を除く) | 企業ごとに上限あり |
| 永住権取得の可能性 | 特に2号は永住申請の道あり | 基本目的が帰国のため低い |
| 外食業への従事 | 16分野で従事可能(単純労働含む) | 職種・作業内容が限定され単純作業不可 |
| 転職の可否 | 特定技能では可能 | 原則不可 |
| 家族の帯同 | 1号は原則不可、2号は配偶者・子可 | 不可 |
| 関与する主体 | 登録支援機関または企業・外国人が直接やりとりする | 監理団体・技能実習機構・送り出し機関など |
| 支援団体 | 登録支援機関または自社支援で可 | 監理団体必須 |
特定技能と技能実習には上記にあるようにさまざまな相違点がありますが、多くの項目に影響を及ぼしているのが「制度の目的」です。技能実習制度は、日本の技術・技能を発展途上国に移転し、相手国の経済発展を支援するという国際貢献が主目的です。
一方、特定技能制度の目的は、日本国内での人手不足を補うための即戦力人材の受け入れにあります。この技能実習制度と特定技能制度の目的の違いが、許可される職種や在留条件など多くの側面に影響しています。
特定技能外国人を採用する2つの方法

特定技能外国人を採用するためには、以下のいずれかの方法を選択する必要があります。
ここでは、下記の方法について解説します。
- 留学から在留資格を変更して採用する方法
-
- 「技能実習」から移行した外国人を採用する
- 留学から在留資格を変更して採用する
「技能実習」から移行した外国人を採用する
特定技能外国人を採用する方法の一つが、すでに日本国内で働いていた「技能実習2号修了者」を、特定技能1号へと在留資格を変更して受け入れる方法です。技能実習2号を「良好に修了」した外国人については、日本語試験および技能評価試験の両方が免除されるため、企業はすぐに特定技能1号の申請手続きに進めます。
在留資格を変更して受け入れる方法は、出入国在留管理庁の公式資料(特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合) | 出入国在留管理庁)でも明示されており、対象分野での技能実習修了者であれば、在留資格変更の際に新たな試験を受ける必要はありません。特に建設、介護、外食、宿泊など多くの分野において、技能実習からのスムーズな移行が実現されています。
さらに重要なのは、2027年に技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度が施行される予定である点です。育成就労制度では、一定の技能や日本語能力を満たした外国人が育成段階を経て試験を受けて合格してはじめて特定技能へと移行できる仕組みが導入されるため、時間・コストがかかります。
そのため、現在の技能実習2号からの移行ルートは、非常にメリットの大きい選択肢といえるでしょう。
留学から在留資格を変更して採用する
特定技能外国人を採用するもう一つの方法の「留学生からの在留資格変更による雇用」は、比較的ハードルが低く、実務面でも柔軟な採用手段として注目されています。特に、従来主流だった「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」に比べて、学歴や専門性の要件が緩和されている点が大きな特徴です。
技人国では、大学や専門学校の卒業資格が必要であり、従事する業務との高度な関連性も求められます。一方で、特定技能1号では学歴要件は問われず、日本語能力試験と対象分野の技能試験に合格すれば就労が可能です。
ただし、企業側には以下の特定技能制度に対応するための明確な受け入れ要件が課されています。
| 受け入れ要件 | 概要 |
|---|---|
| 特定産業分野での事業実施 | 受け入れ業種は特定技能1号の対象分野に該当している必要がある |
| 分野別協議会への加入義務 | 受け入れ企業は該当分野の協議会に加入しなければならない |
| 支援計画の策定と実施 | 特定技能1号の外国人に対して、生活・就労支援計画の作成・実施が必要 |
| 直接雇用が原則 | 派遣雇用は原則不可だが、農業・漁業分野に限り派遣が可能 |
留学生から特定技能への在留資格変更は、企業にとっても採用の幅を広げる有効な手段であると同時に、制度上の責任をしっかり果たす必要があります。採用のチャンスを活かしつつ、制度に沿った受け入れ体制を整備するのが、安定した雇用と外国人材の定着につながります。
外国人採用の流れは?メリットから雇用の手順や注意点までを徹底解説
特定技能外国人材の採用が企業にもたらすメリット

特定技能制度を活用することで、企業は以下のような大きなメリットを得られます。
| メリット | 概要 |
|---|---|
| 単純労働を含む幅広い業務が可能 | 飲食店の接客、工場のライン作業、建設現場など、これまで外国人に難しかった分野でも即戦力として活躍できる |
| 採用母数が多い | 学歴や経験を問わず、日本語試験と技能試験の合格ができれば特定技能1号資格を得られるため、留学生や技能実習修了者なども対象となる |
| 就労希望者の増加 | 献身的に働く意欲の高い人材を確保しやすい |
| 長期雇用を前提とした採用が可能 | 特定技能2号に移行すれば、更新回数の制限なし、家族帯同可能、さらに永住権へつながる可能性もあるため、長期雇用を前提としやすい |
| 制度移行の後押しがある | 育成就労制度からの移行で採用チャネルが増える |
上記のメリットにより、企業は「多様な人材の確保」「長期雇用の実現」「制度安定による安心感」を享受しつつ、深刻な人手不足を戦略的に解消できる力強い手段として特定技能制度を活用できます。
特定技能で就労可能な分野一覧

特定技能で就労可能な分野は以下の通りです。
| 分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 介護 | 〇 | × |
| ビルクリーニング | 〇 | 〇 |
| 工業製品製造業 | 〇 | 〇 |
| 建設 | 〇 | 〇 |
| 造船・舶用工業 | 〇 | 〇 |
| 航空 | 〇 | 〇 |
| 宿泊 | 〇 | 〇 |
| 農業 | 〇 | 〇 |
| 漁業 | 〇 | 〇 |
| 飲食料品製造業 | 〇 | 〇 |
| 外食業 | 〇 | 〇 |
| 自動車運送業 | 〇 | × |
| 鉄道 | 〇 | × |
| 林業 | 〇 | × |
| 木材産業 | 〇 | × |
詳しい各分野の業務内容については以下のページを参考にしてください。
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
特定技能のまとめ

特定技能制度は、日本の人手不足が深刻化するなかで、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた実務的な在留資格制度です。技能実習制度とは異なり、労働力確保を目的としており、単純労働を含む幅広い業務への従事が可能です。
企業側にとっては、学歴・職歴を問わない柔軟な採用が可能となるほか、制度の整備やキャリアパスの明確化により、長期雇用や定着も期待できます。特に、技能実習2号からの移行や留学生の在留資格変更を活用すれば、コストや手間を抑えた効率的な採用も可能です。
採用にあたっては、特定産業分野での事業実施、分野別協議会への加入、支援計画の策定・実施、直接雇用の原則など、いくつかの要件を満たす必要がありますが、それらを整えれば安定的な外国人雇用が実現できます。外国人材の採用を検討している企業にとって、特定技能制度は非常に実用的かつ戦略的な選択肢です。
ご不明点やご相談がありましたら、下のコメント欄よりお気軽にご連絡ください。