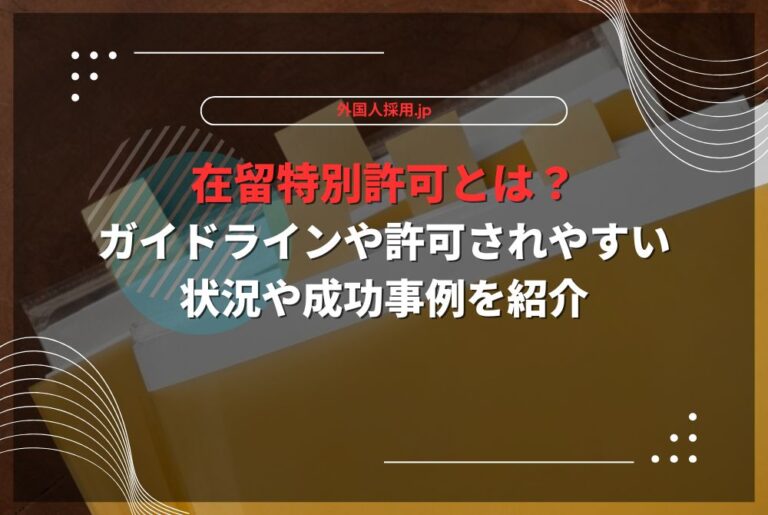外国人材採用を検討する経営者の皆様、在留資格の複雑さや不法就労リスクに不安を感じませんか? 在留資格を持たない方の雇用は原則できません。知らずに雇用すれば、企業も法的責任を問われる可能性があります。
本記事では、不法滞在の外国人が日本での在留を認められる「在留特別許可」の制度概要、許可条件、申請プロセス、成功事例を詳細に解説します。この記事を通じ、申請中の外国人雇用が原則不可であり、許可後に適切な在留資格で雇用が可能になる点を理解し、貴社が安心して外国人材を活用できるよう支援します。
外国人採用の流れは?メリットから雇用の手順や注意点までを徹底解説
在留特別許可とは?

在留特別許可とは、正規の在留資格を持たない外国人、または不法滞在などで退去強制の対象となる外国人に対して、法務大臣が特別な事情を考慮し、日本での居住を認める制度です。
これは退去強制の手続きの中で検討され、最終的な決定は法務省によってなされます。この許可がない場合、退去強制の対象となる外国人は日本に滞在を続けることができません。
在留特別許可の可否は、法務大臣の裁量に委ねられています。以前は法務省の行政指導として運用されていましたが、2024年6月10日に「在留特別許可に係るガイドライン」が制定され、法的根拠を持つものとして位置づけられました。しかし、このガイドラインの制定によって、個々のケースに対する基本的な考え方が大きく変わったわけではありません。
許可の判断においては個々の事案ごとに、申請者の状況や人間関係、日本社会への適応度、過去の違法行為の有無、人道的な配慮といった要素が総合的に考慮されます。重要なのは、単に日本にいるという事実だけでなく、日本での生活が安定し、日本国民と同様に積極的に社会に貢献しているかどうかという点です。
在留特別許可に関する詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。
在留特別許可が下りやすい状態

在留特別許可は法務大臣の広範な裁量に委ねられており、申請した全ての人が許可されるわけではありませんが、以下の事情がある場合に許可が認められやすくなる傾向があります。
- 在留特別許可が下りやすい状態
-
- 日本で長く暮らし、地域にもなじんでいる場合
- 日本に家族がおり、生活の拠点となっている場合
- 日本で就労し、社会に貢献している場合
- 過去に問題行為がなく、まじめに生活している場合
- 人道的な事情で帰国が難しい場合
日本で長く暮らし、地域にもなじんでいる場合
在留特別許可の取得において、日本での長期的な居住実績と日本社会への貢献度は重視されるポイントです。これは一時的な滞在ではなく、申請者が日本に生活の基盤を置き、将来にわたって居住する意思があることを示す上で不可欠であり、許可の可否を判断する際に有利な要素として考慮されやすくなります。
具体的には、以下の点が考慮されます。
- 継続して10年以上の長期間にわたり、安定した在留資格を保持していること
- 地域社会への貢献活動への参加や、日本国内での就労経験、納税義務の履行実績があること
- 日本語能力に優れていること(学歴も判断材料となります)
- 地域社会の活動に積極的に関わっていること
- 生活の拠点となる住居が確保されていること
これらの要素は申請者が「日本での生活基盤を確立し、日本人と同様に積極的に社会の一員として活動している」という状況を示す上で、非常に重要となります。
外国人採用について、詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
日本に家族がおり、生活の拠点となっている場合
在留特別許可の可否を判断する上で、日本に家族がいる状況は極めて重要な考慮事項となります。特に、日本国内での安定した生活基盤を示す家族構成は、許可を得やすい状況につながる可能性があります。
以下に、具体的な例をいくつか挙げます。
- 配偶者が日本人である、または日本国籍を持つ子供がいる場合
- 病気などの理由により、日本人の親族を経済的に支援している場合
- 日本人と婚姻関係を結んだ、あるいは在留資格を有する外国人と結婚した場合
- 日本に居住する日本人配偶者と、実質的な夫婦・親子関係を築いている外国人
- 日本人の親から生まれた日本国籍を持つ子供の親である外国人
人道的な観点から、親子関係などを考慮し、在留を認めることが妥当と判断される場合には、在留許可の必要性が強く主張されることがあります。しかし、日本人配偶者がいるという事実のみで必ず許可されるわけではなく、個々の具体的な状況に応じて総合的に判断されます。
日本で就労し、社会に貢献している場合
在留特別許可の審査においては、日本国内での就労を通じた社会への貢献度も重視されます。
例えば、地域社会への積極的な関与や日本における就労および納税の実績などが評価の対象となります。さらに、生活保護などに頼らず、経済的に自立している状況も社会貢献の一つの側面として捉えられ、許可の判断において有利に働く可能性があります。
過去に問題行為がなく、まじめに生活している場合
在留特別許可の可否は、過去の法規違反や現在の生活状況によって大きく左右されます。審査において、特に考慮される事項は以下の通りです。
- 過去に不法入国や重大な犯罪を犯した経歴がないこと
- 強制退去の処分を受けたことがないこと
- 現在の不法滞在状態を除き、その他の法令違反がないこと
- 行状が善良であると認められること
- 日々の生活において誠実な態度が見られること
過去の在留資格申請における問題がないことや犯罪歴がないことは、許可を得る上で有利に働きます。
人道的な事情で帰国が難しい場合
在留特別許可の可否は法務大臣の判断に委ねられていますが、その決定には申請者の人道的な状況が深く関わってきます。具体的には、本国への帰還が人道上、著しい困難をもたらす場合に考慮されるべき事情が存在します。
例えば、以下のような状況は、法務大臣が許可を与えるか否かを判断する上で、重要な考慮事項となります。
- 帰国した場合に拷問を受ける危険性がある、あるいは生命に関わるような人道上の配慮が必要な場合
- 日本国内でしか治療できない深刻な病状を抱えている場合
- 日本の義務教育を受けている子供がおり、すでに日本の文化に深く馴染んでいる場合
- その他、人道的な見地から見て、看過できない重大な事情がある場合
在留特別許可取得のガイドライン

在留特別許可を得るための主な流れは、以下の表の通りです。
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 入管への出頭と説明 | 退去強制の手続き中、法務大臣の裁量によって在留特別許可が与えられることがあります。許可を求める場合、申請者は入国管理官署に出頭し、日本での継続的な滞在が不可欠であることを詳細に述べることが必要です。その際、滞在期間の長さや地域社会への貢献度、日本人家族との繋がり、日本での生活状況、納税の履行状況、日本語の習熟度などを示す書類を添付します。 |
| 入国警備官による調査 | 入国管理官署へ出頭後、担当官は申請者に対し、過去の法令違反や日本における滞在状況、現在の生計状況などを綿密に調査します。このプロセスを通じて、提出された書類や申告された情報が真正であるかが検証されます。 |
| 入国審査官による審査 | 入国警備官の調査報告や申請者から提出されたさまざまな書類を元に、入国審査官が初期的な判断を下します。この過程において、在留特別許可が与えられる見込みや、退去強制の理由に当てはまるかどうかが審議されます。 |
| 口頭審理 | 入国審査官の決定に納得できない場合や、在留特別許可を得たいと希望する際には、口頭審問という手続きが設けられています。この審問は当事者本人、またはその代理人が自身の置かれた状況や詳細を詳しく述べ、主張を展開する場となります。特に、在留を許可されるべきであるという人道的な観点からの配慮を求める事情などを訴える、非常に重要な機会と言えるでしょう。 |
| 法務大臣による最終裁決 | 法務大臣はこれまでの調査で得られた知見や提出された書類、口頭審理における意見表明といった要素を包括的に検討し、最終的な決定を行います。その決定は対象者を国外に退去させるか、特例として日本での滞在を許可するかの二択となります。この判断は個々の具体的な状況を鑑み、法務大臣の広い裁量権限に基づいて行われます。 |
在留特別許可の処理にかかる期間は、平均でおよそ8ヶ月です。しかし、事案の難易度によっては2年から3年を要することもあります。さらに、日本人の配偶者がいる場合でも許可が確実に下りるわけではありません。それぞれの具体的な状況を踏まえ、総合的な判断がなされます。
在留特別許可取得の成功事例

在留特別許可は、法務大臣の広範な裁量権に基づき与えられる特例的な措置で、その可否は個々の状況を鑑みて総合的に判断されます。したがって、どのような状況が許可につながるか理解することは、申請を検討する上で非常に有益です。
以下に、在留特別許可を得た事例の一部を抜粋してご紹介します。これらの事例は、多種多様な境遇にある外国人が、いかにして日本での滞在を認められたかを示す具体的な実例です。
| 性別 | 国籍 | 申請理由 |
|---|---|---|
| 女性 | タイ | 留学ビザで来日後、その後オーバーステイ状態となるも、日本人男性と結婚し自主出頭した |
| 女性 | ベトナム | 留学ビザの更新ができずにオーバーステイとなったが、日本人男性と結婚し自主出頭した |
| 男性 | ネパール | 技能実習後、脱走しオーバーステイ状態だったが、日本人女性と結婚し家族全員で出頭した |
| 女性 | タイ | 留学ビザで来日後、その後オーバーステイとなったが、日本人男性と8年間交際し結婚後出頭した |
| 女性 | スリランカ | 留学ビザの更新ができずオーバーステイとなったが、日本人男性と1年ほど交際し結婚後出頭した |
| 男性 | ベトナム | 技能実習後に脱走しオーバーステイ状態だったが、日本人女性と結婚し3人全員で出頭した |
| 女性 | スリランカ | 来日当初から不法滞在であったが、専門家(行政書士)の熱意あるサポートを受け、在留特別許可を得た |
| 男性 | スリランカ | ザ取得の可能性が低いとされていたが、専門家の熱心なサポートを受け、諦めずに在留特別許可を得た |
| 女性 | 中国 | 長年の不法滞在で一度は諦めかけたものの、専門家の励ましと支援により自主出頭し、在留特別許可を得た |
在留特別許可の事例を検討すると、日本人配偶者との婚姻関係や日本での長期にわたる居住歴、良好な行状などが許可を得る上で有利な要素となる傾向が見られます。加えて、専門家の助けを借りながら、自身の状況を隠さず説明し続ける姿勢も重要です。
とりわけ、不法滞在という状況から新たな在留資格を得るためには、個々の状況を考慮したきめ細やかな対応が不可欠であると考えられます。
在留特別許可のまとめ

この記事では、在留特別許可について解説してきました。
在留特別許可は正規の在留資格を持たない外国人や退去強制対象者に対し、法務大臣が特別な事情を考慮し、日本での居住を認める制度です。2024年6月にガイドラインが制定され法的な根拠が明確化されましたが、基本的な考え方は以前と変わりません。
許可の可否は申請者の状況や人間関係、日本社会への適応度、過去の違法行為などを総合的に考慮して判断されます。具体的には長期居住や日本に家族がいること、就労による社会貢献、問題行動の有無、人道的な事情などが重要な要素となります。
申請の流れは、入管への出頭・説明、入国警備官による調査、入国審査官による審査、必要に応じて口頭審理が行われ、最終的に法務大臣が裁決を下します。処理期間は平均8ヶ月ですが、事案によっては長期化することもあります。雇用主は、在留特別許可申請中の外国人を原則として雇用できません。許可取得後、適切な在留資格を取得した場合にのみ、合法的な雇用が可能です。雇用に際しては、在留カードを確認し、就労の可否を確認する必要があります。