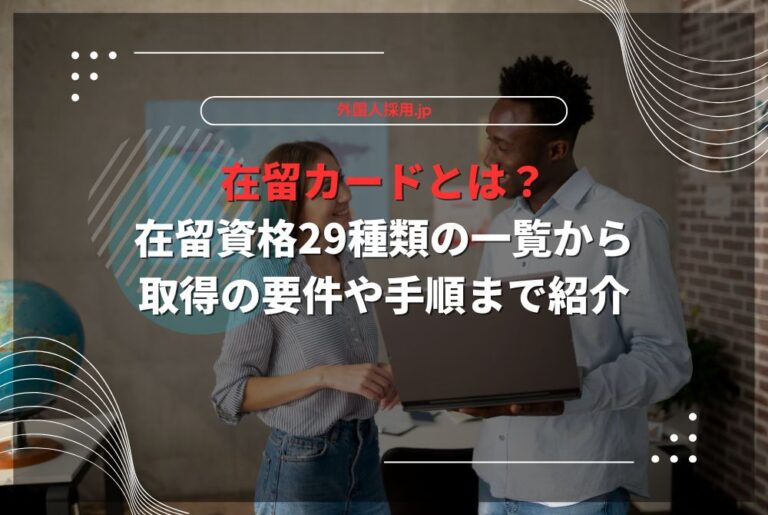在留カードには29種類の在留資格があり、それぞれ就労可否や活動範囲が異なります。企業は紛失時の対応や期限管理、偽造カード防止など8つのポイントを押さえることで適切な雇用管理が可能です。
本記事では在留カードの基本情報から取得要件、確認方法について解説します。29種類の在留資格一覧や企業が気をつける管理ポイントもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
在留カードとは?

在留カードは、日本国内に3か月を超えて滞在する中長期在留者に対して発行される身分証明書です。氏名や国籍、在留資格などが掲載されており、本人確認や在留資格の証明として利用されます。
一方、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付され、在日コリアンなど戦後特例で日本に残る方々が該当します。以下の表で主な違いをまとめました。
| 比較項目 | 在留カード | 特別永住者証明書 |
|---|---|---|
| 交付対象 | 中長期在留者(特別永住者除く) | 特別永住者 |
| 法的根拠 | 出入国管理及び難民認定法 | 入管特例法 |
| 就労制限 | 在留資格ごとに制限あり | 制限なし(日本人と同様) |
| 有効期間 | 在留期間満了日まで(永住者は7年) | 原則7年ごとの更新 |
| カード名称 | 在留カード | 特別永住者証明書 |
特別永住者証明書は、歴史的な背景を持つ方やその子孫を対象とし、一般の在留カードとは条件や扱いが異なります。詳細は以下のページをご確認ください。
在留カードの情報項目

在留カードの情報項目は以下の通りです。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労の可否
- カード番号
- 顔写真(16歳以上)
住居地に変更があった場合は、変更後14日以内に市区町村役場または入国管理局で必ず手続きを行う義務があります。手続きを怠ると、罰則や行政手続き上の不利益が生じるため、速やかな対応が必要です。
在留カードの確認方法

在留カードの確認は、有効期限内での使用が法律で義務付けられており、期限を超えての使用は違法行為となります。確認作業では目視による基本チェックに加えて、オンラインシステムを活用して真偽を確認しましょう。
確認すべき主要項目は以下の通りです。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 目視確認 | 有効期限・氏名・在留資格・顔写真・住所・就労可否の記載内容 |
| 物理的特徴 | ICチップ・ホログラム・印字品質・カード番号の正確性 |
| オンライン確認 | 入管庁「在留カード等番号失効情報照会」での番号照会 |
| アプリ確認 | 「在留カード等読取アプリケーション」でのICチップ読み取り |
目視とオンライン両方の確認を徹底することで、偽造カードや失効カードの使用を防止できます。住所変更や資格更新などの情報更新漏れがないか必ずチェックし、常に最新情報がカードに反映されているか正確に管理することが大切です。
在留カードの取得要件

在留カードは、日本で3か月を超えて適法に生活する外国人へ交付される公的身分証です。一方、在留目的や滞在日数によっては交付対象から除外されるケースがあります。
交付対象外の条件は以下の通りです。
| 除外される在留資格・条件 | 具体例 |
|---|---|
| 在留期間が3か月以下と決定された人 | 90日以内の観光・業務連絡など |
| 「短期滞在」の在留資格を持つ人 | 親族訪問や講習参加など |
| 「外交」または「公用」の在留資格を持つ人 | 大使館職員や国際機関職員 |
| 上記1〜3に準ずると法務省令で定められた人 | 特定の政府派遣者など |
| 「特別永住者」の人 | 戦前からの在日韓国・朝鮮人等 |
| 有効な在留資格を持たない人(不法滞在中) | 在留資格取消手続中や不法残留者 |
表に該当しない中長期在留者は、入国審査時や住居地届出後に所定の手続きを経て在留カードを受け取れます。企業と本人は交付対象の可否を確認し、要件を満たさない場合の手続き漏れを防ぐことが重要です。
在留カード取得までの手順

在留カードは日本への中長期在留を許可された外国人に交付される公式な身分証です。取得は空港での上陸許可と、市区町村の住居地届出を経て行われます。
申請時に不備があると審査が遅れるため、下記の3点をそろえておきましょう。
- 申請書(所定の様式に記入)
- 写真2枚(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)
- 在留資格を証明する書類(雇用契約書、在学証明書など)
在留カードの受け取り方法は次の2通りです。
| 受け取り方法 | 詳細 |
|---|---|
| 主要7空港で即日交付 | 成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡空港で、入国審査後にその場で在留カードを受領する方式 |
| 後日郵送で受領 | 上記以外の空港から入国した際、入国後14日以内に市区町村で住居地届出を行い、数日~2週間後に簡易書留で郵送 |
どちらの方法でも、受け取り後14日以内に住民登録を済ませ、在留カード裏面に住所を記載してもらう必要があります。手続きの遅延は在留資格更新や社会生活に影響するため、スケジュール管理を徹底してください。
在留資格29種類一覧

在留資格は、日本での活動目的によって「就労目的」「家族・交流目的」「就労・学業以外」の3つに大別されます。具体的な内容をまとめると、以下の通りです。
| 区分 | 在留資格名 | 主な特徴・就労可否 |
|---|---|---|
| 就労目的 | 技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行、技能実習、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 | 特定分野での就労が可能 |
| 家族・交流目的 | 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者 | 原則就労不可(資格外活動で一部可) |
| 就労・学業以外 | 留学、短期滞在、研修、文化活動、特定活動 | 限定された活動のみ可能 |
就労目的の資格では「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などがあり、特定分野で働くことが認められています。
家族や交流を目的とした資格には、「家族滞在」「日本人の配偶者等」などが含まれます。原則として就労は認められていませんが、資格外活動許可を取得すれば一定範囲でアルバイト等が可能です。
学業や短期滞在を目的とした「留学」「短期滞在」「研修」などの資格では、活動内容が厳格に限定されており、原則として就労はできません。それぞれの在留資格は活動内容や就労可否が異なり、目的に合った資格を選択する必要があります。
在留カードの取り扱いで企業が気をつける8つのポイント

企業が外国人従業員の在留カードを適切に管理しなければ、法令違反や不法就労のリスクが高まります。従業員本人だけでなく、企業側にも確認義務と管理責任があるため、以下の8つの観点を徹底することが必要です。
企業はポイントを日常的に意識し、従業員への周知とサポート体制を整えることが求められます。詳しく見ていきましょう。
- 8つのポイント
-
- 紛失時は速やかに再交付申請を促す
- 常に在留カード原本の携帯を指導する
- みなし再入国許可の期限管理を行う
- 在留期限切れを防ぎ更新を促す
- 住所変更などの届出を忘れさせない
- 偽造カードや無効カードを見抜く
- 就労資格の有効性を厳重にチェック
- 不法就労助長罪のリスクを認識する
1. 紛失時は速やかに再交付申請を促す
在留カードが紛失・盗難・破損に遭った場合、本人は警察にその場で遺失届を提出した後、14日以内に入管へ再交付申請が必要です。 申請時には紛失届出証明書やパスポートなど、複数の書類が必要となり、企業は書類の準備や手続き内容についてサポートします。
手続き中もパスポートの携帯をすすめれば、不測の本人確認にも対応できます。申請手続きが遅れると在留資格の更新などに響くケースもあるため、定期的なフォローと情報共有が欠かせません。
企業として従業員の紛失リスクを最小限に抑えるため、カードケースの配布や携帯方法の指導を行うことも重要です。再交付手続きが完了するまでの期間、業務に支障をきたさないよう代替の身分証明方法も事前に確認しておきましょう。
2. 常に在留カード原本の携帯を指導する
在留カードの原本は法律で義務付けられており、提示できない場合には罰則の対象となります。企業は外国人従業員に対して、常に原本を持ち歩くよう繰り返し指導し、コピーや写真では代用できないと明確に伝えることが重要です。
職場や外出先での本人確認や警察官からの提示要求に即応できるよう、携帯義務の重要性を徹底しましょう。定期的な研修や注意喚起を実施し、違反によるトラブルを未然に防ぐ体制を整えます。
携帯を忘れた場合の対応策として、すぐに取りに帰るか業務を一時中断するなどのルールも社内で明確化することも大切です。従業員の安全と法令遵守の両面から、携帯義務の徹底が企業の責任として求められます。
3. みなし再入国許可の期限管理を行う
みなし再入国許可を利用して出国した場合、1年以内に再入国しなければ在留資格を失います。企業は従業員の出国・帰国予定を正確に把握し、1年を超えそうな場合は事前に正式な再入国許可を取得するよう促しましょう。
スケジュール管理を怠ると、再入国できず就労継続が困難になるリスクがあるため、出入国日や許可期限の管理が重要です。定期的に出入国予定を確認し、必要な手続きが漏れないようサポートします。
海外出張や一時帰国の際は、出国前に必ず期限を確認し、延長が必要な場合は適切な手続きを案内することが必要です。管理台帳やシステムを活用して、複数の従業員の出入国スケジュールを一元的に把握する体制を整えましょう。
4. 在留期限切れを防ぎ更新を促す
在留カードの有効期限が切れると不法滞在となり、本人・企業ともに重大な法的リスクを負います。企業は従業員の在留期限をリスト化し、期限が近づいたら早めに更新手続きを案内します。
永住者であっても7年ごとのカード更新が必要なため、全従業員の期限を一元管理することが不可欠です。更新手続きの進捗を定期的に確認し、申請漏れや遅延を防ぎます。
更新申請は期限の3か月前から可能なため、余裕を持ったスケジュールで手続きを促すことが大切です。申請中は一時的に就労に影響が出る場合もあるため、業務調整や代替要員の確保も視野に入れて管理しましょう。
5. 住所変更などの届出を忘れさせない
在留カード記載の住所や氏名が変わった場合、14日以内に市区町村または入国管理局に届け出ることが義務です。企業は従業員に対し、引越しや結婚など変更が生じた際は速やかに手続きを行うよう周知します。
届出を怠ると罰則や行政手続きの遅延につながるため、変更時の流れや必要書類を事前に案内します。手続きのサポートやリマインドを通じて、従業員が確実に届け出できる環境を整えることが大切です。
外国人従業員が日本の行政手続きに不慣れな場合、同行支援や書類作成のサポートを行うことも重要です。変更届が完了したら、在留カード裏面の記載も更新されているか必ず確認し、手続きの完了を確実に把握しましょう。
6. 偽造カードや無効カードを見抜く
不正な在留カードの利用は、企業にも罰則が及びます。 ICチップ・ホログラム・フォント不備・カード番号など、細かい部分をチェックして偽造カードや無効カードを使ってないか確認しましょう。
法務省のオンラインシステムや専用アプリを利用し、カード番号やIC情報を照合して不審な点があれば入管へ速やかに相談してください。本人以外によるカード利用や失効カードの使用が見つかった場合、即時に雇用契約を見直すなどの対応が必要です。
従業員教育やマニュアル作成を通じ、不正カードのリスクと防止ポイントを全社で共有することも大切です。疑わしいカードを発見した際の対応フローを事前に整備し、適切な判断ができるよう準備することが求められます。
7. 就労資格の有効性を厳重にチェック
採用時には在留カード原本と就労資格証明書を必ず確認し、就労可能な資格かどうかを厳密に見極めます。期限切れや就労不可の資格で働かせると不法就労となり、企業も処罰対象となります。
在留資格の範囲や資格外活動許可の有無も確認し、疑義があれば入国管理局に照会しましょう。定期的な資格確認を行い、雇用継続中も有効性を維持できるよう管理します。
就労できる職種や時間に制限がある場合は、業務内容との整合性を常に確認することが必要です。資格変更や更新のタイミングで就労条件が変わる可能性もあるため、継続的な監視体制を構築しましょう。
8. 不法就労助長罪のリスクを認識する
在留カードや資格の確認を怠った場合、雇用企業も不法就労助長罪の対象となり、刑事罰や社会的な信用失墜につながります。在留資格を偽っての雇用や期限切れカードでの勤務継続は、原因を問われる重大な違反です。
企業は担当者だけでなく経営層を含め、「在留カードの確認義務」「更新期限の徹底管理」など、ルールを全社で共有・徹底する必要があります。トラブル時や不正の疑いが生じた場合の連絡先や対応手順も、あらかじめマニュアル化しておくと安心です。
法令違反が発覚した場合の企業への影響は計り知れないため、予防策を講じることが最重要課題となります。定期的な社内研修や外部専門家による監査を通じて、コンプライアンス体制を継続的に強化していくことが大切です。
不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。|厚生労働省
在留カードや在留資格の種類のまとめ

在留カードは、日本で中長期間生活する外国人の身分証として、本人確認や労働権の証明に欠かせない存在です。記載項目や有効期限、手続きの流れなど、各ポイントを正確に押さえておくことがトラブルを防ぐコツです。
在留資格は目的別に29種類が定められており、許される活動範囲や就労可否に明確な違いがあります。採用時や雇用後の管理では、資格ごとの制限内容や更新時期を的確に把握し、企業側で日々確認とフォローを行いましょう。
また最新のルールや確認手順を全従業員と共有し、適正な運用を心がけることが、外国人雇用の安心とコンプライアンスの確保につながります。
ぜひ本記事を参考にして、在留カードの正しい知識と管理方法を実践してください。