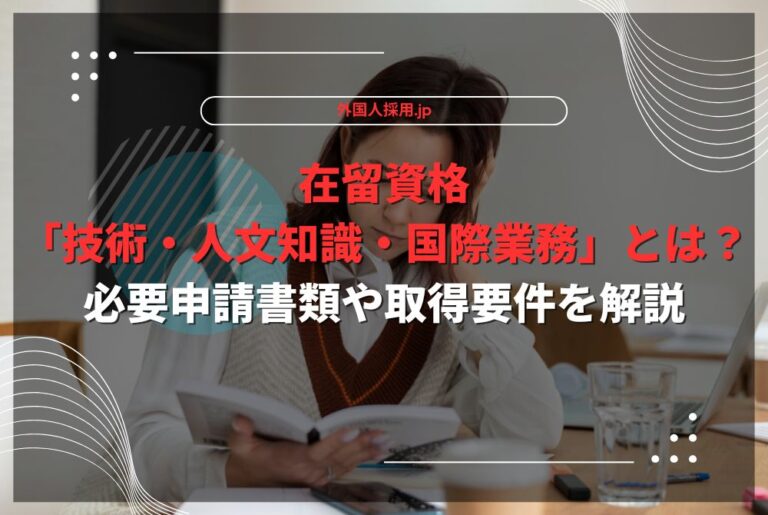外国人が日本企業で専門的な業務に従事する際に必要となる在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。
ITエンジニアや経理・法務、通訳・翻訳など幅広い職種に対応しており、企業の国際化を支える重要な制度でもあります。
本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要から取得に必要な要件、申請時の必要書類までわかりやすく解説します。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、日本で働く外国人に最も広く利用されている就労ビザの一つで、在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
理学・工学などの技術分野、法律・経済などの人文知識分野、そして通訳・翻訳や語学教育などの国際業務分野に関連する専門的業務に従事するために必要な在留資格です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校で身につけた専門知識やスキルを活かして働くことを前提としており、単純労働や業務内容と学歴・職歴に関連性がないケースでは認められません。
また「技術・人文知識・国際業務」は、継続的な就労が可能なため在留期間の延長や最終的には永住権取得への道筋にもなる、外国人が日本で長期的に暮らす上でも重要な在留資格です。
詳細な要件などは以下の出入国管理庁のページを参考にしてください。
出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
特定活動46号とは?「技術、人文知識、国際業務」との違いや取得要件を解説
高度外国人材とは?受け入れのメリットや高度人材ポイント制を解説
技術・人文知識・国際業務の就労可能な仕事

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、分野ごとに就労可能な仕事が異なります。
ここでは、それぞれの分野ごとに就労可能な仕事について解説します。
|
在留資格「技術」で就労可能な仕事
在留資格「技術」で就労可能な仕事の一例は以下の通りです。
| 職種 | 概要 | 求められる技能・知識 |
|---|---|---|
| システムエンジニア | 企業の業務システムやWebアプリケーションを設計・開発する | プログラミングやネットワーク構築などIT全般の知識 |
| 機械設計技術者 | 自動車・家電・産業機器などの製品に必要な部品・機構の設計を担当する技術職 | 機械力学、熱力学などの工学系の知識および製図のためのCADの知識 |
| CADオペレーター | 機械や建築の設計図面を作成・修正する専門職 | 担当する設計に関する専門的な知識と製図のためのCADの知識 |
| 建築設計士 | 住宅やビル、商業施設などの設計を行う | 構造設計、意匠設計、設備設計などの建築学系の知識 |
在留資格「技術」に該当する職種の場合は、機械工学、建築学などの理系分野に属する専門的な知識・技能が求められます。
在留資格「人文知識」で就労可能な仕事
在留資格「人文知識」で就労可能な仕事の一例は以下の通りです。
| 職種 | 概要 | 求められる技能・知識 |
|---|---|---|
| 経理 | 会社の収支管理や会計関連業務などを担当 | 簿記や会計原則 |
| 人事 | 採用・労務管理・教育研修などを担当 | 組織運営や労務法規に関する知識 |
| 法務 | 契約書や規約のチェックを行う法律に関する業務 | 法学系の知識 |
| 営業 | 自社製品やサービスを販売・提案する | ・大学や専門学校で専攻した科目に関連した取り扱う商材に関する知識
・理系でも専攻科目と商材が合致していれば従事可能 |
| コンサルタント | 経営課題に対して知識を基に改善提案を行う | コンサルを行う分野に関する専門知識 |
在留資格「人文知識」に該当する職種の場合は、法学、会計学などの文系分野に属する専門的な知識・技能が原則求められます。
ただ、営業・コンサルタントなど一部の職種では、専門知識と商材が合致していれば理系分野を履修した人材でも従事可能な場合があります。
在留資格「国際業務」で就労可能な仕事
在留資格「国際業務」で就労可能な仕事の一例は以下の通りです。
| 職種 | 概要 | 求められる技能・知識 |
|---|---|---|
| 通訳・翻訳 | 日本語と他言語を行き来させ、文章や会話の意味やニュアンスを正確に伝える | 翻訳する言語への深い造詣 |
| 語学教師 | 英会話スクールや企業研修などで、外国語を教える | 高度な言語運用能力 |
| デザイナー | 異文化や海外トレンドを取り入れたデザインを行う | インテリア・ファッションなどに対するデザインの知識 |
| 貿易事務 | 輸出入に関わる契約書作成、通関処理、海外企業との連絡調整などを行う | 英語および通関に関する知識 |
在留資格「国際業務」に該当する職種の場合は、必要となる語学に関する深い理解に加え、業務に必要な分野への専門的な知識が求められます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件
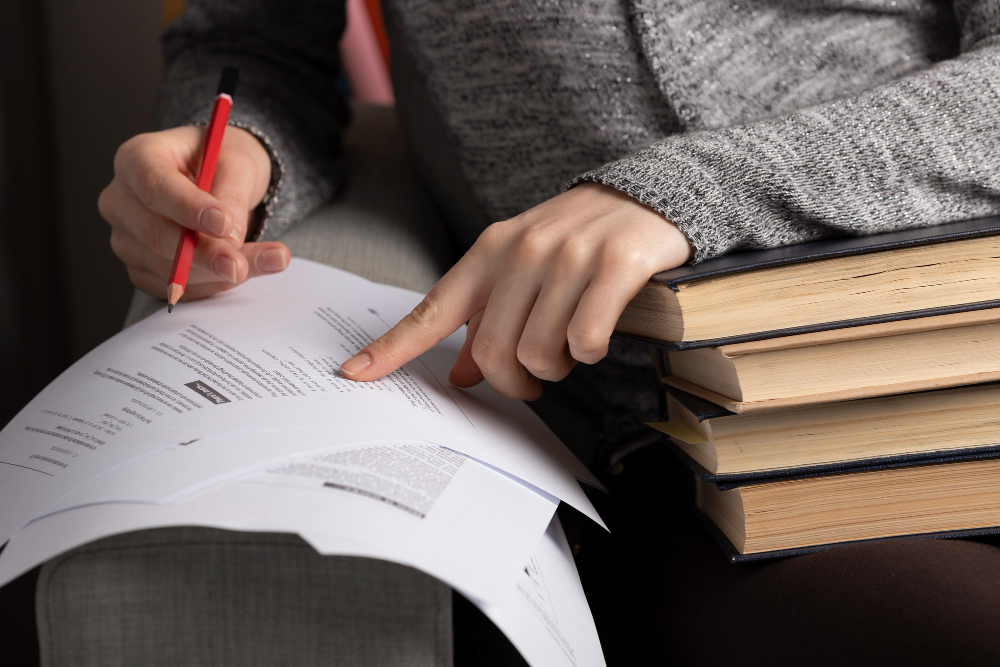
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件についても各項目ごとで内容が異なります。
ここでは、それぞれの項目ごとの取得要件について解説します。
|
在留資格「技術」の取得要件
在留資格「技術」の取得要件は以下の通りです。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 1. 理系の技術や知識を要する業務であること | 法令においては、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動」と明記されている |
| 2. 専門性のある業務であり、単純作業でないこと | 業務が単なるデータ入力・軽作業や販売員などではなく、専門的な判断力や高度な技術を要するものである必要がある |
| 3. 学歴または実務経験による裏付けがあること | 以下のいずれかを満たす必要がある
・大学・短大・専門学校(専門学校は日本のみ)などで、関連分野を専攻し卒業していること ・実務経験が10年以上あること(学歴を含めた関連科目専攻期間も含まれる) |
| 4. 専攻分野と職務内容に関連性があること | 専攻してきた分野と、実際に従事する職務内容の間に明確な関連性が求められる |
出典:出入国在留管理庁 資料
在留資格「人文知識」の取得要件
在留資格「人文知識」の取得要件は以下の通りです。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 1. 文系分野(法学・経済学・社会学など)に属する知識や技術を要する業務であること | 「人文知識」として認められる業務であれば、専攻分野や職務内容として文系の専門知識が活用できるものでなければならない |
| 2. 単純作業やルーティン業務ではなく、企画・分析・判断を要する業務であること | 専門性を必要としない単純労働は不可 |
| 3. 業務内容と学歴・専攻内容(または実務経験)に関連性があること | 以下のいずれかを満たす必要がある
・大学・短大・専門学校(専門学校は日本のみ)などで、関連分野を専攻し卒業していること ・実務経験が10年以上あること(学歴を含めた関連科目専攻期間も含まれる) |
| 4. 「マーケティング」と名がついていても、実態が販売・営業などであれば不可 | マーケティングと名乗っていても、 「企画・分析・戦略構築」などの文系的高度業務であることを証明できなければ認められない |
出典:出入国在留管理庁 資料
在留資格「国際業務」の取得要件
在留資格「国際業務」の取得要件は以下の通りです。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 1. 外国語や外国文化に基づいた感性・表現が求められる業務であること | 「国際業務」は、単なる語学力ではなく、母国の文化背景や感性が業務に反映されるような業務を指す |
| 2. 単に日本語ができる外国人に任せられる業務ではないこと | 販売スタッフや電話対応など、マニュアル化された業務では「国際業務」要件は満たせず、専門的な判断や母国文化に基づいた表現・提案力が必須 |
| 3. その人物の出身国・文化的背景だからこそ発揮できる視点や思考、表現力があること | 「外国文化を背景とした分析・提案・創作ができる」ことが、国際業務としての正当性を担保する |
出典:出入国在留管理庁 資料
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得方法

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得方法は、以下のシチュエーションによって異なります。
ここでは、上記のシチュエーションごとの取得方法について解説します。
|
海外から取得する場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を海外から取得する際のフローは以下の通りです。
| 取得の流れ | 概要 |
|---|---|
| 1.採用内定を出す | 日本の企業側が、外国人に対して採用の意思を示し、雇用契約を締結 |
| 2.企業側が「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行う | 日本の地方出入国在留管理局に対し、証明書の交付を申請する |
| 3.審査 | ・入管での審査が行われる
・所要期間は1~3ヶ月程度 |
| 4.在留資格認定証明書(COE)が交付される | 審査を通過した申請には、COEが交付され、企業または代理人を通じて本人へ送付される |
| 5.本人が現地の日本大使館・領事館で就労ビザを申請・取得 | 日本の大使館や領事館で査証(ビザ)申請を行う |
| 6.来日・入社 | ビザを取得したら、日本へ入国し、空港等でパスポート、ビザ、COEを提示して上陸審査を受ける |
海外から取得する場合は、日本側と海外側で実施しなければならない手続きがあるため、綿密なやりとりと確認が必要になります。
留学生の場合
留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する際のフローは以下の通りです。
| 取得の流れ | 概要 |
|---|---|
| 1.内定通知 → 雇用契約締結 | 企業側が内定を出し、雇用条件通知書などを正式に交付 |
| 2.「留学」から「技人国」への在留資格変更申請 | 内定後、必要書類を整えて本人が入管へ在留資格変更許可申請を実施 |
| 3.本人が出入国在留管理局に申請 | 申請は企業ではなく留学生本人が出入国在留管理局に出向いて行う |
| 4.審査 | 審査期間は通常1〜2ヶ月程度 |
| 5.許可が下り次第、勤務開始可能 | 審査が通れば新しい在留カードが交付され、その日から正式に就労が可能 |
留学生が取得する場合は、在留資格変更に必要な書類が留学生・企業側双方に多く求められるため、過不足のない準備が大切です。
日本国内で就労中の外国人が取得する場合
日本国内で就労中の外国人が取得する際のフローは以下の通りです。
| 取得の流れ | 概要 |
|---|---|
| 1.内定通知 → 転職意思の確認 | 新たな内定を受けて、転職する意思があることを明確にする |
| 2.在留資格はそのまま維持し転職可能 | ・転職後の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、在留資格の変更申請は不要
・転職後14日以内に「所属機関変更届」を提出する必要がある |
すでに就労中の外国人の場合、同じ技人国の範囲内での転職であれば必要な書類も少なくスムーズに進められます。
ただし、異なる在留資格へと変更になる場合は、新たに「在留資格変更許可申請」を本人が行う必要があるため、その点には注意が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請書類一覧

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、雇用する企業(所属機関)は カテゴリー1~4 のいずれかに分類され、 この分類が申請時の書類量や審査プロセスに大きく影響します。
カテゴリー一覧と分類基準は以下の通りです。
| カテゴリー | 分類基準 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、公共法人、独立行政法人、保険相互会社など、信頼性と継続性が高い機関 |
| カテゴリー2 | 売上・規模が大きな非上場企業 |
| カテゴリー3 | 中堅・中小企業(設立2年以上) |
| カテゴリー4 | 設立1年未満のベンチャー・スタートアップなど |
上記のカテゴリーのどこに所属しているかによって、提出すべき書類が異なります。
カテゴリーを踏まえた上での、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を新たに在留資格申請書を提出する際に必要な書類一覧は以下の通りです。
| 区分 | 要件・書類 |
|---|---|
| 全カテゴリー共通書類(カテゴリー1および2はこの項目の書類のみ) | ・在留資格申請書
・写真(縦4 cm×横3 cm、無帽・無背景、直近6ヶ月以内撮影) ・返信用封筒 ・カテゴリー要件を満たすことを証明する文書 ・専門士証明(該当者のみ) |
| カテゴリー3で追加される書類 | ・労働条件通知書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 ・広報やデザイナーなどに従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 ・登記事項証明書 ・勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 ・直近の年度の決算文書の写し |
| カテゴリー4で追加される書類 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする書類 |
なお、在留資格変更許可申請の場合は、在留資格申請書ではなく在留資格変更許可申請書を提出します。
さらに詳しい内容については出入国管理庁のページをご確認ください。
出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
技術・人文知識・国際業務ビザで転職する時に気をつけたいポイント

転職でスムーズに次の職場へ移るためには、特に以下の2点に気を付けるようにしましょう。
| 注意点 | 概要 |
|---|---|
| 所属機関の変更は14日以内に届け出る | 届出が遅れると20万円以下の罰金が課せられる可能性がある |
| 転職先の業務内容が在留資格の条件に合っているか確認する | ・転職先が技術・人文知識・国際業務に該当する専門的業務であることが必須条件
・学歴における専攻内容と一致していない職務への転職は不許可になるリスクが高く、最悪の場合、帰国を余儀なくされる可能性もある ・業務内容が変更になる場合は、在留資格変更許可申請が別途必要 |
上記の2点は安定的に日本で就労を続ける上で確実に遵守すべき項目であるため、特に注意を払いながら対応するようにしてください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のまとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、日本国内で外国人が専門性を活かして就労するための主要な在留資格の一つです。
技人国は、「技術」「人文知識」「国際業務」という3つのカテゴリーに大別されており、それぞれに応じて就ける職種や求められる学歴・実務経験が異なります。
例えば、技術分野ではITエンジニアや設計技術者などの理系職種が対象であり、人文知識ではマーケティングや経営企画といった文系業務、国際業務では語学や外国文化の感性を活かした業務が該当します。
また、企業側として押さえておきたいのは申請時に提出が求められる各種書類です。
企業の規模や形態によって「カテゴリー1~4」に分類され、審査の厳しさや必要書類の数も変わるため、あらかじめ自社がどのカテゴリーに該当するかの確認が大切です。
さらに、採用後の転職時には、業務内容が在留資格の要件に適合しているかを十分に確認し、転職後14日以内に「所属機関変更届」を提出するなど、法的な手続きも忘れてはなりません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人の専門性を日本社会で活かすための重要な仕組みです。制度の正しい理解と適切な対応を通じて、企業と外国人双方が安心して働ける環境づくりを目指しましょう。
本記事へのご質問・お問い合わせなどがありましたら、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。