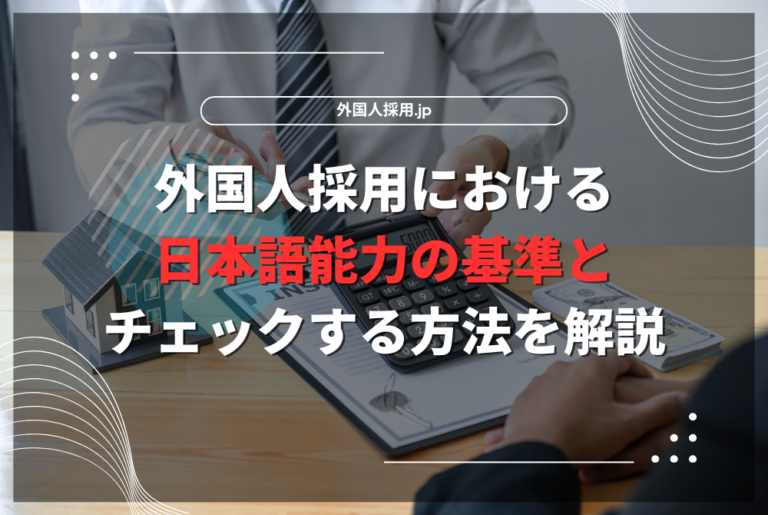「外国人を採用する際に何を基準に日本語能力を確認すればよいのだろう」と気になっている方は多いでしょう。外国人を積極的に採用すれば、少子高齢化の現代において若くて優秀な労働力の確保につながります。
しかし、外国人を採用するうえで壁となるのが言語の問題です。
本記事では、外国人採用における日本語能力の基準とチェックする方法を解説します。本記事を読めば、適切な日本語能力を習得した外国人のみの採用が実現できます。外国人の積極的な採用を検討している方は、本記事を参考にしてください。
外国人採用の推移

厚生労働省の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」によると、外国人労働者は2023年10月時点で2,048,675人と前年よりも225,950人増加しています。年々日本では外国人労働者が増加傾向にあるのです。
また、国籍別では、ベトナムが518,364人で最も多く、次に中国が397,918人、フィリピンが226,841人とアジア圏の外国人が特に多く働いています。
- 外国人採用について
- – 外国人採用を行っている背景
外国人採用を行っている背景
日本で積極的に外国人採用が行われている理由は、少子高齢化が進んで労働人口が減少傾向にあるためです。企業は労働力を求めており、外国人は日本で働きたいと思っているので、外国人労働者が増加しています。
外国人採用を推進していき、労働力不足の解消へ努めましょう。
外国人が日本で働きたい理由

なぜ、外国人はほかにも働ける国がある中で日本で働きたいと考えているのでしょうか。外国人が日本で働きたい具体的な理由として、以下の4つが挙げられます。
| 外国人が日本で働きたい具体的な理由 |
|---|
| 日本の文化やコンテンツが好き 日本の企業に対するイメージが良い 日本は治安が良くて人々のマナーが良い 保険や福利厚生が充実しているイメージがある |
日本はほかの国と比較して治安が良く、安心して働くことが可能です。外国人が日本で働きたい共通の項目は上記のとおりです。
しかし、アジア地域出身者やアメリカ・ヨーロッパ諸国出身者では日本で働きたい理由がそれぞれ異なる場合があります。外国人が日本で働きたい理由を理解したうえで、外国人人材の採用活動に動きましょう。
- 日本で働きたい理由とは
- – アジア地域出身者の場合
– アメリカやヨーロッパ諸国出身者の場合
アジア地域出身者の場合
アジア地域出身者は、幼少期から日本のアニメを見て生まれ育っている場合が多いため、自然と日本に興味を持つ人々が多い傾向にあります。ただ、アジア地域出身者が日本で働きたい真の理由は、以下の2つです。

就職しやすい
アジア地域出身者は、母国よりも給与が高いため、日本で働くことを選ぶ傾向にあります。例えば、2022年時点でのベトナムでの平均月収は約38,280円と日本よりかなり低いことが分かります。母国へ送金するために、日本へ働きに来ている外国人労働者は多いでしょう。
また、日本で働きに来る外国人労働者の母国は学歴重視な傾向にあるので、高学歴じゃないと就職が困難です。日本は学歴がなくても就職できる企業は数多く存在するので、就職のしやすさから日本で働く外国人も多くいます。
アメリカやヨーロッパ諸国出身者の場合
アメリカやヨーロッパ諸国出身者が日本で働きたいと思う理由は何でしょうか。アメリカやヨーロッパ諸国出身者が日本で働きたい理由として以下の2つを紹介します。

福祉制度や医療制度が整っている
アメリカやヨーロッパ諸国出身者の場合、キャリアアップを目的に日本へ働きに来る人材が多い傾向にあります。アメリカやヨーロッパの場合、転職回数が多くてもマイナスな印象をもたれないので、働いている会社よりも日本の企業に興味を持てば転職するのは極めて当たり前なことです。
したがって、自身のスキルアップを目指して日本へ働きに来る外国人労働者も多くいます。福祉制度や医療制度が整っている点も、アメリカやヨーロッパ諸国出身者が日本で働く理由です。
日本の医療制度の技術はほかの国よりもレベルが高いため、安心して働けます。自社にアメリカやヨーロッパ諸国出身者が働きに来る可能性があるため、日本で働きたい一般的な理由を把握しておきましょう。
外国人採用における日本語能力の基準

日本語能力試験には以下の5つのレベルが定められており、N1が一番難しく、N5が一番簡単に設定されています。日本語能力試験の認定の目安は以下のとおりです。
| レベル | 認定の目安 |
|---|---|
| N5 | ひらがなやカタカナ、漢字で書かれた文章を読んで理解できる 日常生活の場面でゆっくり話される短い会話の場合は、話の内容が理解できる |
| N4 | 基本的な語彙や監事を使用した文章を読んで理解できる 少しゆっくり話してくれれば、話の内容が理解できる |
| N3 | 日常的な話題に関して記載された文章を読んで理解できる 日常的な場面で自然に近いスピードで会話を聞けば、具体的な内容を理解できる |
| N2 | 一般的な文章を読み、話の流れや表現意図を理解できる まとまりのある会話を聞いて話の流れや登場人物の関係を理解できる |
| N1 | 抽象度が高い文章を読み、文章の構成や内容を理解できる 自然なスピードのまとまりのある会話を聞き、内容の論理構成を詳細に理解できる |
上記の表を参考にし、採用する外国人の日本語能力の基準を理解しましょう。
- 日本語能力に関すること
- – 日本語能力試験の種類
– 日本語能力を判断するときの注意すること
日本語能力試験の種類
日本語能力試験は6種類あります。それぞれの日本語能力試験の内容と費用は下記の表のとおりです。
| 試験名 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| JLPT | 課題遂行のためのコミュニケーション能力を測る試験 | 5,500円 |
| JFT-Basic | 実際の生活状況や職場で遭遇する可能性がある具体的な状況を想定した問題が出題される試験 | 7,000円 |
| J.TEST実用日本語検定 | 日本文化への理解や雑誌のニュース、グラフ問題など受験生の総合力を測定する試験 | 4,800円 |
| 日本語NAT-TEST | 「文字・語彙」「難解」「読解」など3つの分野の試験において総合的に能力が評価される試験 | 5,500円 |
| J-cert生活・職能日本語検定 | 筆記試験・インタビュー試験・論文テストのすべてに合格しなければいけない試験 | 4,000〜15,000円 |
| JSST日本語会話力テスト | 事前に録音された音声データを基に10問の問題が用意されているため、それぞれ45〜60秒の間に回答しなければいけない試験 | 4,500〜5,500円 |
外国人人材の日本語能力を適切に把握するためには、それぞれの試験内容を把握しなければいけません。ここで解説した内容を参考にし、日本語能力試験を理解してください。
JLPT
JLPTとは、国際教育支援機関と日本国際教育支援協会が共同で開始した日本語能力を認定する語学試験です。JLPTでは日本語の文字や文法の知識量に重きが置かれており、読み書き能力を重視しています。
JLPTのN1とN2に合格した場合、高度人材への出入国管理上の優遇制度に関するポイントが付与されます。高度人材への出入国管理上の優遇制度とは、永住許可要件の緩和や配偶者の就労など、さまざまなメリットが受けられる制度です。
N1に合格した場合は15ポイント、N2には10ポイント付与され、合計70ポイントを付与した場合のみ優遇措置が与えられます。また、JLPTの認定レベルが高いことを会社へ伝えると、高い評価を得て昇進につながる場合があります。合格率はN1が30%、N2・N3・N4が40%、N5が55%前後です。
JFT-Basic
JFT-Basicとは、就労を目的に来日する外国人が日常会話ができて生活に支障がないレベルの日本語能力があるかを判定するテストです。テストセンター内にあるパソコンを使用して受験するため、テストの結果がすぐ分かります。
JFT-Basicは「文字と語彙」「会話と表現」「難解」「読解」の4つに分類されており、コミュニケーション能力を重視しています。JFT-BasicはJLPTのN4レベルの難易度なので、難解な日本語の知識は必要ありません。合格点は250点中200点で、合格率は約40%です。
参照:国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の実施状況と受験者像ーCBT 予約時アンケートの分析ー
J.TEST実用日本語検定
J.TEST実用日本語検定とは、JLPTのN1よりも上のレベルまで測定できて就職活動でのアピールに活用できる試験です。J.TESTは読解と難解を重視しており、日本語の読み書き能力や会話表現の理解度を測定可能です。J.TESTは、以下の8つのレベルに日本語能力が設定されています。
| J.TEST実用日本語検定8つのレベル |
|---|
| 特A級(930〜1,000点) A級(900〜929点) 準A級(850〜899点) B級(800〜849点) 準B級(700〜799点) C級(600〜699点) D級(500〜700点) E級(350〜499点) F級(250〜350点) G級(180〜249点) |
A〜C級の場合は1,000満点で600点以上でかつ1つも0点の分野がなかった場合に認定証の発行がされます。D~E級では700点満点で350点以上で0点の分野がなかった場合の認定証発行が可能です。F〜G級では350点満点で180点以上で1つも0点の分野がなければ認定証の発行がされます。
また、J.TESTはレベルを跨いだ出題範囲が設定されています。例えば、JLPTの場合は、N3を受験すればN3の難易度の問題しか出題されません。しかし、D・E級レベルの場合は、N3とN4の両方のレベルの問題が幅広く出題されます。
したがって、J.TESTを受験する際は幅広い問題への対策や下のレベルへの復習が必要になって、さらに深く日本語を学習することが求められます。
日本語NAT-TEST
日本語NAT-TESTは、JLPTと同じ問題構成・評価基準で作成されている試験です。優しいレベルから順に5級・4級・3級・2級・1級の順番で構成されており、難易度はJLPTと同じです。そのため、JLPTの対策として受験する方が多い傾向にあります。
日本語NAT-TESTは各項目の得点率など細かい結果も開示され、受験者の得意と苦手が一目で理解できる試験です。
J-cert生活・職能日本語検定
J-cert生活・職能日本語検定とは、日本の文化や習慣を理解して日常生活を送るうえで必要なコミュニケーション能力を測定できる試験です。生活・職能日本語検定では、マスター級(C1)・上級〜中級(C2・B2・B1)、準中級〜入門級(A2.2・A2.1・A1)に難易度が分類されており、マスター級はJLPTのN1同様の難易度があります。
成績優秀者に対しては、海外や日本国内企業への就職サポートをしてもらえたり、日本に招待して貰えたりと、さまざまな特典が受けられます。
JSST日本語会話力テスト
JSST日本語会話力テストとは、電話で手軽に受験できる試験です。日本語会話力テストは実際に電話して受験者の日本語能力を図れるため、口頭運用能力が把握できます。
例えば「以前、海外へ旅行に行った時の話をしてください」と明確な答えのない問題が出題され、適切な回答をしなければいけません。日本語会話力テストは、以下の5つの評価基準を総合的にして運用能力を10段階で図れます。
| JSST日本語会話力テストの評価基準 |
|---|
| 総合的タスク(日本語を使用して何ができるのか) 発話の形(日本語の形を使いこなせているか) 正確さ(文法・発音・語彙・流暢さ) 内容(どんな内容に関して話せているのか) 待遇表現(敬語が適切に使用できているのか) |
実際に日本語会話力テストでは、多くの企業で外国人社員の採用に活用しています。実際のビジネス現場における日本語能力を図れるので、日本語会話力テストで評価が高い社員を採用すれば即戦力として働けるでしょう。
日本語能力を判断するときの注意すること
外国人社員を採用する際に日本語能力を判断するときは、以下の2つに注意してください。
能力試験の結果はあくまで1つの指標にする
採用する外国人の日本語能力を判断する際は、ポジションや業務内容によって要件を変更しましょう。例えば、営業職や接客業に従事する場合はコミュニケーション能力が求められるため、高い日本語能力が必要です。
しかし、工場業務や事務職では日本語運用能力が高くなくても、仕事に従事することは可能です。ポジションや業務内容によって採用する基準を変動させるとよいでしょう。また、能力試験の結果はあくまで1つの指標にすることを心がけてください。
例を挙げると、日本語会話能力で評価が高くて口頭運用能力が高かったとしても、日本語の読み書きが苦手な場合があります。実際に面接して日本語能力を把握したうえで、採用するべきか判断してください。
外国人採用における日本語能力のまとめ

外国人採用において日本語能力を図るための試験は6種類あり、試験によって測定できる日本語能力が異なります。例えば、JLPTでは日本語の文法や知識量に重きを置いていますが、日本語会話力テストでは口頭運用能力を重視しています。
どの日本語能力試験を基準にするかによって、採用する外国人の日本語能力は異なるでしょう。
本記事を参考にして日本語能力を測る基準を把握し、外国人採用に活用しましょう。