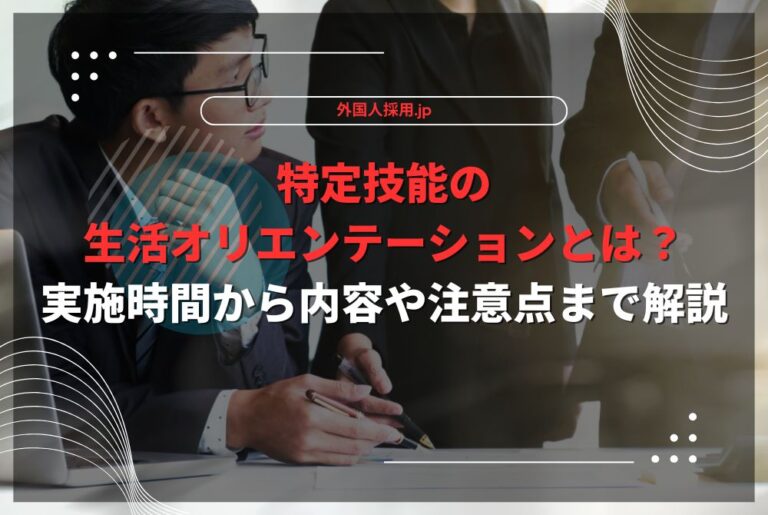特定技能1号の外国人材を受け入れる際に不可欠となるのが「生活オリエンテーション」です。
生活オリエンテーションは、特定技能制度に基づいて在留する外国人が日本で安心して暮らせるよう、生活ルールや制度を理解してもらうための重要な研修で、実施義務は受け入れ企業に課されています。
本記事では、生活オリエンテーションの概要から実務で気をつけるべきポイントまで、わかりやすく解説します。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能の生活オリエンテーションとは?

特定技能の在留資格で外国人を受け入れる際、生活オリエンテーションの実施は避けて通れません。
特に「特定技能1号」の受け入れにおいては、受入企業または登録支援機関が策定する「支援計画」の中で、義務的支援の一環として生活オリエンテーションの実施が義務付けられています。
生活オリエンテーションを含めた義務的支援として定められている10項目は以下の通りです。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の際)
- 定期的な面談・行政機関への通報
参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁
生活オリエンテーションの目的は、外国人が日本で安心して暮らし、働けるようにする点にあります。文化や制度の違いによるトラブルを未然に防ぎ、日本社会にスムーズに適応してもらえるような多角的なサポートが求められます。
実際の生活オリエンテーションの実施形式は、対面のみならずオンライン、動画視聴など柔軟な手法が選択可能です。ただし、実施の際には対象となる外国人が十分に理解できる言語で行う必要がある点には注意が必要です。
特定技能の生活オリエンテーションと事前ガイダンスの違い

義務的支援のなかには、生活オリエンテーションと混同されやすい「事前ガイダンス」の項目があります。生活オリエンテーションの実施の際には、事前ガイダンスとの目的や実施タイミングなどの違いを明確に理解した上で実施しなければなりません。
特定技能の生活オリエンテーションと事前ガイダンスの違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 事前ガイダンス | 生活オリエンテーション |
|---|---|---|
| 目的 | 日本で就労・生活を始める前に、労働条件・契約・入国手続などの基本事項を明らかにして、外国人の不安を減らし、誤解・トラブルを未然に防止する | 実際に日本で暮らし始めてからの日常生活に必要な情報を提供し、安全・安心に生活できるように支援する |
| 実施タイミング | 国外:雇用契約締結後、入国前
国内:在留資格変更前 |
入国後または在留資格変更許可後、できるだけ速やかに実施 |
| おもな内容 |
|
|
| 位置づけ | 支援計画における義務的支援の最初期の項目 | 事前ガイダンスの後、入国してから行う義務的支援項目の一つ |
上記の比較表で、特に理解しておくべきポイントの一つがそれぞれの実施の目的の違いです。
端的にまとめると以下のようになります。
- 事前ガイダンス:「これから日本で何をするか」を外国人と受入れ側で共通理解するための準備段階で、契約内容や手続き等、誤解がトラブルの原因となる部分を事前にクリアにしておくことで、入国後の問題発生を防ぐ
- 生活オリエンテーション:入国後実際に生活していくなかで「知っておくべきこと」「困りがちなこと」を具体的に教えることで、その人の生活の質を高め、日本で安定して暮らせるようにする目的がある
「事前ガイダンス」は入国前から気を付けるべきポイント、「生活オリエンテーション」は日常生活において気を付けるべきポイントについて重点的にレクチャーすると認識しておくと理解しやすいでしょう。
特定技能人材受け入れ時の「事前ガイダンス」とは?内容や実施時間を解説
特定技能外国人の住居確保ガイド|部屋の広さや責任の所在まで解説
特定技能の生活オリエンテーションの適切な実施時間

出入国在留管理庁が定めた「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」によれば、生活オリエンテーションは原則として8時間以上行わなければなりません。
8時間という基準は、特定技能外国人が日本の生活ルール・文化・公共制度など多岐にわたる情報を理解・定着させるために必要な最低限の時間として設定されています。
一方で、以下のような一部のケースでは、例外的に4時間以上の生活オリエンテーションでも認められる場合があります。
- 在留資格を「技能実習2号」または「留学生」から特定技能1号へ変更する場合
- 同一の受け入れ企業に継続して雇用される場合
- 生活環境(住居・地域等)に大きな変化がない場合
すでに日本での生活に慣れており、環境や業務内容がほぼ変わらない外国人に対しては、必要最低限の内容に絞った内容での実施が許容されています。ただ、特定技能1号外国人が転職して新たな受け入れ企業に所属することになった場合、生活オリエンテーションは再度実施しなければなりません。
生活オリエンテーションは、例外なくすべての特定技能1号外国人に対して実施しなければならない支援項目です。受け入れ企業や登録支援機関には法的な義務が課せられており、実施しない場合は指導対象となる場合もあります。
また、支援実績を報告する際には、生活オリエンテーションを「誰に・いつ・どのように・何時間実施したか」などの情報を明確に記録しておく必要もあります。
特定技能の生活オリエンテーションの実施内容

特定技能の生活オリエンテーションの実施内容は以下の通りです。
ここでは、下記の内容について解説します。
|
日本での基本的な生活知識の案内
特定技能の生活オリエンテーションでは、外国人が日本で安心して日常生活を送るために必要な「生活の基礎知識」の提供が重要です。
特に以下の4項目に関する案内は欠かさず行うようにしましょう。
| 項目 | 説明すべき具体的な内容 |
|---|---|
| 銀行口座の開設・ATMの利用 | 普通預金口座の開設方法、ATMでの入出金・振込・残高照会の操作方法や手数料、口座を解約するときの手続き など |
| 交通ルール | 左側通行、日本での歩行者・自転車・自動車のルール、道路標識の意味、公共交通機関の使い方、定期券の購入方法 など |
| ゴミの出し方・分別 | 住む地域の「燃えるゴミ」「資源ゴミ」「粗大ごみ」などの分別方法および収集日・出し場所を具体的に案内 |
| 買い物や日常マナー | スーパーやコンビニの利用方法、公共施設や住まいでのマナー、買い物時に会話で役立つ表現や支払い方法 など |
上記の内容を丁寧に伝えれば、生活トラブルを未然に防ぎ、職場や地域での定着率向上にもつながります。
行政手続きの方法についての説明
外国人が日本での生活を始める際には、住民登録・健康保険と年金の加入・マイナンバーの取得の3つの行政手続きを行う必要があり、これらについての説明を実施するのも生活オリエンテーション時には求められます。
住民登録・健康保険と年金の加入・マイナンバーの取得についての概要は以下の通りです。
| 手続き名 | 概要 | 実施タイミング | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 住民登録 | 日本での住所を市区町村に届け出て、住民票を作成する | 日本に入国し、住居が決まってから14日以内 | 在留カード、パスポート、賃貸契約書など |
| 健康保険と年金の加入 | 企業に雇用される場合、原則として厚生年金と健康保険に加入 | 雇用開始時 | 在留カード、住民票など |
| マイナンバーカードの取得 |
|
住民登録完了から数週間以内に通知到着 | 通知カードまたは個人番号通知書、在留カード、顔写真 |
実際の運用としては、口頭や書類のみのレクチャーだけではスムーズに手続きを進めるのが難しい場合があるため、可能であれば役所などに同行してサポートするとよいでしょう。
医療機関の利用方法と保険制度の解説
生活オリエンテーションでは、特定技能1号外国人が日本で病気やケガをしたときの医療機関の利用方法と保険制度を解説する必要があります。
おもな案内内容は以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 医療機関の探し方 |
|
| 保険の使い方 | 健康保険または国民健康保険が適用される場合、自己負担は3割になることを案内する |
| 診察の流れ | 受付~支払いまでを順序立てて解説する |
| 救急時の対応 |
|
医療機関の利用方法・保険制度・診察の流れ・緊急時対応などの情報は、日本で安心して暮らすために必要なため、細部まで丁寧に教えるようにしましょう。
困ったときの相談窓口の紹介
特定技能外国人が日本で働き・暮らすなかでは、思わぬトラブルや不安に直面する場合もあり、その際に相談できる窓口を事前に案内しておくのも必要な対応となります。
外国人が困ったときの相談窓口として活用できる機関は以下の通りです。
| 相談窓口 | おもな相談内容 |
|---|---|
| 出入国在留管理庁 | 在留資格、更新、在留期間、活動内容の制限など |
| 外国人在留支援センター | 生活・労働・法的トラブルなどの総合相談 |
| 労働基準監督署 | 賃金未払い、残業、休日、労働時間、解雇などの労働トラブル |
| 法テラス | 契約・住宅・労働問題・トラブル全般の法律相談 |
| 登録支援機関 | 生活上の困りごとや相談、役所の手続き支援 |
| 大使館・領事館 | パスポート更新、母国への連絡、トラブル時の保護など |
生活オリエンテーションの段階で、どこに・どんなときに相談すればよいかを明確に案内するのは、外国人の安心と信頼につながる重要なステップの一つといえます。
災害・犯罪への備えと対応方法
日本国内で起きる災害・犯罪の被災者・被害者になる可能性を考慮して、生活オリエンテーションではその際の対応方法を案内する必要があります。
災害・犯罪への備えと対応方法として案内すべき内容は以下の通りです。
| 項目 | 案内すべき内容 |
|---|---|
| 災害時の行動 |
|
| 避難所の確認 |
|
| 防犯の基本 |
|
| 緊急連絡先の活用方法 |
|
生活オリエンテーションでは、ただ情報を伝えるだけでなく、具体的な避難所確認や連絡先の共有、実践的な備えを促すと、外国人自身が主体的に安心できる環境を整えられます。
法令や労働に関する注意点の周知
外国人が日本で暮らす際は、国内法に対する理解をある程度進めておかないと、想定外のトラブルに巻き込まれるおそれがあるため、生活オリエンテーションでの周知が必要です。
法令や労働に関するおもな周知ポイントは以下の通りです。
| 項目 | 周知ポイント |
|---|---|
| 在留資格の基本ルール |
|
| 労働法の基本ルール | 労働基準法・最低賃金法など、日本の法律で守るべき労働条件 |
| 契約トラブルへの対応 | 雇用契約書の内容が実際の労働条件と異なる・契約書が不十分な場合の対応方法 |
| 人権相談窓口の活用方法 | 差別・ハラスメント・労働上の不当扱いなど、人権問題が生じた際の相談先 |
上記の項目のポイントを周知すれば、多くのトラブルを未然に防止できるでしょう。
特定技能の生活オリエンテーション実施時の4つの注意点

特定技能の生活オリエンテーション実施時に注意すべき点は以下の4つです。
ここでは、下記の注意点について解説します。
|
母国語に対応した資料を準備する
生活オリエンテーションは、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが原則とされています。
出入国在留管理庁の運用要領でも、「理解できる言語」での実施が明記されており、母国語での説明が困難な場合でも、最低限資料は母国語に対応させる必要があります。
特に、在留資格・保険制度・労働条件・災害対応など、誤解が命や就労に関わる分野では、パンフレット・スライド・Q&A・申請書見本などを母国語で整備する対応が必須です。
確認書を保管する
生活オリエンテーションを実施したあとは、外国人本人から署名をもらった「確認書」を作成・保管が義務付けられています。確認書は、支援計画に基づいて適切にオリエンテーションを実施した証拠として、企業や登録支援機関が管理すべき重要な書類です。
なお、この確認書は出入国在留管理庁への提出義務はありませんが、支援内容の適正性を証明するために保存しておく必要があります。
特に、トラブルや監査、在留資格更新時などに備えて、在留期間中は確実に保管するようにしましょう。
状況によって手続きに同行する
生活オリエンテーションでは、公的手続きが理解しづらい外国人に対し、必要に応じて窓口へ同行しサポートする対応が推奨されています。
特に、国民健康保険や国民年金の加入・離脱手続き、住民登録、在留資格変更などは書類が複雑で、日本語対応のみの場合も多いため、同行による補助が有効です。
同行は義務ではありませんが、トラブル防止や外国人の安心につながる重要な支援行為とされています。同行によるサポートを支援計画に盛り込んだ上で、必要な場面では柔軟に対応しましょう。
理解度によって定期的に実施する
生活オリエンテーションは一度で終わらせず、特定技能外国人の理解度に応じて繰り返し実施するとより知識の定着化が図れます。特に、制度や生活ルールは複雑なため、定期的に見直すことで知識の定着と誤解の防止につながります。
また、生活オリエンテーション実施時に理解度チェックを行い、不十分な部分は柔軟に補うとより効率的に実施可能です。
特定技能の生活オリエンテーションのまとめ

特定技能の生活オリエンテーションは、単なる案内ではなく、受け入れ企業または登録支援機関に課せられた義務的業務です。
特定技能1号外国人が日本で安心して生活を始め、長く定着できるように、制度や手続き、生活ルールをわかりやすく伝える施策が求められます。
実施にあたっては、母国語での資料提供や理解度に応じた繰り返し説明、必要に応じた手続きの同行など、きめ細やかな配慮が重要です。また、確認書の取得と保管も制度上必要な対応となっています。
そして、受け入れる企業側は制度の意図を正しく理解し、生活オリエンテーションの内容と適切な実施方法をしっかり把握した上で取り組む必要があります。
本記事を参考に特定技能の生活オリエンテーションをスムーズに進めていただければ幸いです。