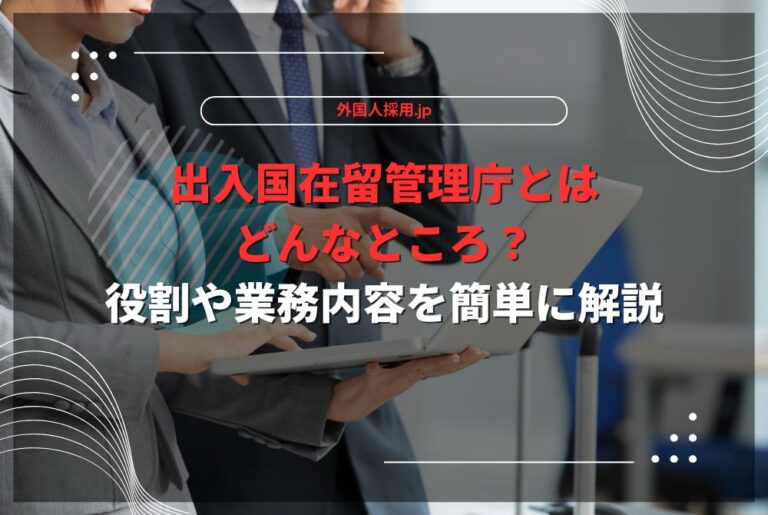外国人労働者の雇用を検討する中で「出入国在留管理庁」の役割がよくわからず、戸惑いを感じていませんか。手続きで必ず関わる重要な機関ですが、その業務内容は多岐にわたり、企業としてどう連携すべきか悩むことも多いかもしれません。
日本の外国人労働者の受け入れは、1950年の入国管理庁の設置から始まります。当時、入国管理庁は外務省の外局として設置され、その政策は主に在日韓国人や中国人への対応が中心でした。1960年代に入ると、産業界から人手不足を背景に単純労働者の受け入れ要請が出始めましたが、政府がこれに応じることはなく、その方針は1980年代前半まで続きました。
大きな転機が訪れたのは1988年です。この年に閣議決定された「第六次雇用対策基本計画」で、外国人労働者を「専門的・技術的労働者」と「単純労働者」に分け、前者は積極的に受け入れるという方針が初めて示されました。
この方針転換を機に、技能実習や高度専門職、そして近年では特定技能といったさまざまな就労系の在留資格が次々と創設されました。関連法規も、1951年の「出入国管理令」から、難民議定書への加入などを経て、1982年に現在の「出入国管理及び難民認定法」へと改められています。
こうした歴史的経緯を経て、現在では29種類の在留資格で就業が認められており、2021年10月末時点で約173万人の外国人労働者が日本で活躍しています。
この記事では、出入国在留管理庁と入国管理局との違いといった基本情報から、出入国審査、在留管理、外国人の生活支援、不法滞在者対策という具体的な役割までを総合的に解説します。
この記事を読めば、出入国在留管理庁の全体像を正しく理解し、コンプライアンスを遵守しながら外国人雇用を円滑に進めるための知識を得ることができます。
外国人人材紹介会社おすすめ比較15選!費用相場や選定ポイントも解説
出入国在留管理庁とは

出入国在留管理庁は、2019年4月1日に法務省の外局として新設されました。その背景には、日本の少子高齢化の深刻化と、それに伴う労働力不足を補うための外国人労働者の受け入れ拡大があります。
このような状況を受け、従来の出入国管理体制では業務量が大幅に増加し、新たな体制を構築する必要が生じたため、法務省の内部組織であった「入国管理局」を再編・格上げする形で設置されました。
出入国在留管理庁の主な役割は、以下の3点です。
- 厳格かつ円滑な出入国審査
- 外国人材の受け入れに関する判断
- 日本人と外国人の共生社会の実現
出入国在留管理庁と出入国在留管理局の違い

出入国在留管理庁と入国管理局との根本的な違いは、「外局」か「内局」かという点です。
内局とは、府省庁や外局の内部に設けられた組織のことで、独立性を持たず、大きな組織の中で実際の業務を行う「実行部隊」のようなものです。入国管理局は法務省の「内部部局」でした。そのため、トップは「局長」であり、組織の業務は主に上位機関である法務省との連携でした。
一方、外局とは、府省庁の下に置かれる独立性の高い組織・機関を指します。業務の特殊性や専門性から、府省庁とほぼ同等の地位を持つとされることもあります。2019年4月1日に発足した出入国在留管理庁は「外局」に格上げされ、外国人の出入国に関する司令塔としての機能を担うことになり、組織のトップも「長官」となりました。
この「外局」への移行に伴い、組織規模も大きく変わりました。出入国在留管理庁には長官や次長といった役職が新設され、出入国に関する取締りを行う「出入国管理部」や、外国人の生活を支援する「在留管理支援部」といった新しい部署も設けられています。
また、出入国在留管理庁は地方の出先機関として、全国各地に地方出入国在留管理局、支局、出張所を配置し、地域ごとの出入国審査や在留資格の手続きといった現場の業務を行っています。
出入国在留管理庁の4つの役割や業務内容

出入国在留管理庁は、日本人の安全な出入りと、日本を訪れる外国人や日本に在留する外国人の出入国・滞在を管理する組織です。一般的には「入管」と呼ばれています。その業務は多岐にわたり、主な役割は大きく4つに分けられます。
|
出入国審査や在留審査含む手続き
出入国在留管理庁の最も重要な役割の一つは、出入国や在留に関するさまざまな審査と手続きです。これらは外国人を雇用する企業にとっても必ず関わる業務となります。主な手続きは以下の通りです。
| 手続き名 | 手順 | 内容 |
|---|---|---|
| 出入国審査手続き |
|
|
| 在留審査手続き |
|
日本に在留する外国人の在留資格や活動内容、在留期間は定められており、その変更や更新の希望があった際に審査を行う |
| 在留管理制度に関する手続き |
|
|
| 特別永住者証明書の交付に関する手続き | 申請に基づき、交付手続きを行う | 「入管特例法」で定められた在留資格を持つ「特別永住者」の法的地位を証明するカードを交付 |
| 難民の認定に関する手続き |
|
|
これらの手続きは、日本の安全を確保し、適切な在留管理を実施するための、非常に重要な業務です。
外国人の快適な生活の確保
出入国在留管理庁は、日本に住む外国人がより快適に生活できるよう支援することも重要な業務の一つです。
その取り組みとして、「外国人生活支援ポータルサイト」を運営し、日本での生活や仕事の基本ルールをまとめた「生活・就労ガイドブック」を提供しています。「やさしい日本語」のほか、英語、中国語、ベトナム語など15の言語に対応しています。
また、外国人を支援する拠点として、「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」を設置しています。フレスクは、外国人を雇用したい企業への支援や、外国人からの相談に対応する総合的な窓口です。
東京出入国在留管理局をはじめとする複数の省庁や機関の窓口が一つのフロアに集まっており、どこに相談すればよいかわからないという問題を解決します。相談は無料で、匿名でも可能です。
参考:外国人在留支援センター(FRESC)|出入国在留管理庁
不法滞在者の調査
出入国在留管理庁は、不法滞在者の調査と摘発も重要な役割としています。不法滞在者とは、不正に入国・上陸した人や、許可された滞在期間を超えて滞在する「不法残留者」、許可された活動範囲を超えて収入を得る「不法就労者」などを指します。
特に、外国人を雇用する際には不法就労に注意が必要です。不法就労は、以下のように定義されています。
- 正規の在留資格を持たない外国人が、日本に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に滞在したりして行う、収入を伴う活動
- 正規の在留資格を持つ外国人でも、許可を得ずに、認められた在留資格以外の収入を伴う事業を運営したり、報酬を受け取ったりする活動
参考:不法就労防止について
また、企業が不法就労であることを知りながら外国人を雇用したり、不法就労をあっせんする行為は、「不法就労助長罪」という犯罪にあたり、罰則の対象となります。
参考:外国人の適正雇用について
問い合わせ対応
出入国在留管理庁には、外国人や企業の方々から、日々多くの問い合わせが寄せられています。これらの問い合わせに対応するため、各地方出入国在留管理局や支局には、「外国人在留総合インフォメーションセンター」という相談窓口が設けられています。
問い合わせの内容は多岐にわたり、例えば以下のようなものがあります。
- 企業からの外国人雇用に関する相談
- 外国人の入国・在留手続きに関する相談
- その他の各種手続きに関する相談
相談は電話とメールで受け付けています。連絡先は以下のとおりです。
| 電話番号:0570-013904
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp 電話対応時間:平日 午前8時30分~午後5時15分 |
また、対応言語は以下のとおりです。
| 電話:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー語
メール:日本語、英語 |
参考:外国人在留総合インフォメーションセンター等|出入国在留管理庁
出入国在留管理庁と企業の関係性

労働力不足が深刻化する日本において、外国人材の採用は多くの企業にとって重要な経営戦略となっています。その際、必ず関わることになるのが、出入国在留管理庁です。
外国人を雇用する企業にとって、出入国在留管理庁は非常に重要な協力機関と言えるでしょう。なぜなら、外国人を雇用する上で必要な在留資格の申請や変更、更新といった手続きは、全て出入国在留管理庁を通じて行う必要があるからです。
これらの手続きを適切に行うことは、法令を遵守する上で非常に重要です。万が一、手続きを怠ったり、在留資格で認められていない業務を外国人にさせた場合、企業側が「不法就労助長罪」という重い罪に問われる可能性もあります。
このような事態を避けて、法に触れることなく適切な雇用を進めるためには、出入国在留管理庁の規則を正しく理解し、連携することが不可欠です。企業は採用時に必ず在留カードを確認し、就労が可能かどうかを厳格にチェックする責任があります。
外国人労働者の社会保険加入は必要?雇用保険の手続きや注意点を解説
出入国在留管理庁のまとめ

この記事では、出入国在留管理庁について解説してきました。
出入国在留管理庁は、日本の少子高齢化と労働力不足を背景に、外国人材の受け入れを円滑に進めるため、2019年に法務省の外局として新設された機関です。その業務は、出入国・在留審査といった厳格な管理業務が中心ですが、それだけでなく、日本に在留する外国人の生活支援、不法滞在者の調査、各種問い合わせ対応まで多岐にわたります。
特に外国人を雇用する企業にとっては、在留資格の申請や更新など、すべての手続きを担う不可欠なパートナーです。
企業が不法就労助長罪といった法的なリスクを避け、適正な雇用を実現するためには、出入国在留管理庁の役割を正しく理解し、密に連携していくことが極めて重要です。