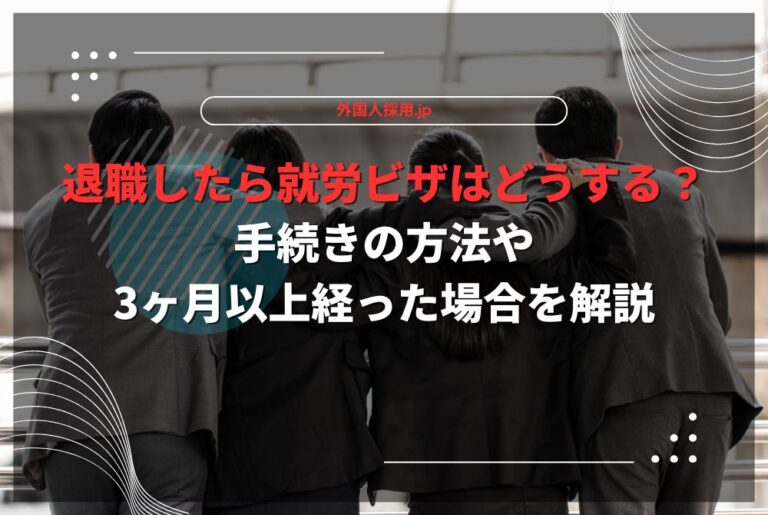日本で働く外国人は「就労ビザ(在留資格)」を取得しておく必要があります。就労ビザとは、日本国内で合法的に働くことを認める在留資格で、職種や業務内容によって種類が分かれているのが特徴です。
ただ、就労ビザで働く外国人材が退職した場合、「3ヶ月以上、就労活動を行わない状態」が続くと、在留資格の取り消し対象になる可能性がある点には注意が必要です。
本記事では、退職後に必要となる入管への届出や、転職時のビザ変更手続き、万が一3ヶ月以上経ってしまった場合のリスクと対応策について、具体的に解説します。
退職後の外国人の就労ビザの扱い

日本で就労ビザを持って働いていた外国人が会社を退職した後も、ただちに帰国しなければならないわけではありません。
ただし、いくつか守るべき条件があり、それが守れないとビザが取り消されたり滞在が難しくなる場合があります。
退職後の外国人の就労ビザの扱いにおけるポイントは以下の通りです。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 退職してもすぐに帰国の必要はない |
|
| 再就職は「3ヶ月以内」が条件 |
|
| 無職期間中はアルバイトも禁止 | 退職後に無職期間があっても、許可されていない仕事を始めることは原則としてできない |
まずは上記のポイントを押さえておくと、急な退職となっても慌てずに対処できるでしょう。
退職後3ヶ月以上経ってしまった場合の就労ビザの扱い

就労ビザで日本に滞在している外国人材が退職後に長期間無職のままでいると、就労ビザの維持が難しくなる可能性があります。就労ビザの維持の根拠は、入管法第22条の4の(6)に以下のように明記されています。
| (6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。 |
出典:在留資格の取消し(入管法第22条の4) | 出入国在留管理庁
ただ、上記にある通り無職であっても以下のような「正当な理由」があれば、ビザの取り消しを回避できる可能性があります。
- ハローワークでの求職登録履歴
- 応募企業との面接記録や不採用通知メール
- 就職エージェントとのやり取り履歴
- 病気や療養などで就労が困難だったことを示す医師の診断書 など
一方で、上記のような正当な理由を証明できるものが無く無職のまま3ヶ月以上経過してしまうと、就労ビザは取り消され、最悪の場合は「退去強制処分」の対象になります。
また、ビザが取り消された経歴があると、その後の日本への再入国が最長で5年間制限される可能性もあります。
就労ビザの取り消しを防ぐためには、可能な限り早めに転職先を見つけられるように活動し、3ヶ月以上かかりそうな場合でも継続的に続ける姿勢が大切です。
退職後に行うべき就労ビザの手続き

退職後に行うべき就労ビザの手続きは、本人と企業側でそれぞれ内容が異なります。
ここでは、本人・企業それぞれの手続きの内容について解説します。
|
本人が行うべき手続き
就労ビザを持っている外国人が会社を退職した場合、退職した日から14日以内に「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁に提出しなければなりません。
所属機関等に関する届出は、退職や転職などで「これまで所属していた活動機関または契約機関」から離れたことを入管に通知するために提出が義務付けられています。
また、所属機関等に関する届出は、「活動機関に関する届出」と「契約機関に関する届出」に分類されており、在留資格によって以下のような区分となっています。
| 区分 | 対象となる在留資格 |
|---|---|
| 活動機関に関する届出 | 教授/高度専門職1号ハ・2号ハ/経営・管理/法律・会計業務/医療/教育/企業内転勤/技能実習 |
| 契約機関に関する届出 | 高度専門職1号イ・ロ/高度専門職2号イ・ロ/研究/技術・人文知識・国際業務/介護/興行/技能/特定技能 |
所属機関等に関する届出の内容・提出方法は以下の通りです。
| 提出者:外国人本人が行う 提出方法:オンライン(電子届出システム)、窓口、郵送など 届出に記載するおもな事項:
|
また、万が一14日を過ぎても提出しなかった場合、20万円以下の罰金の可能性があるため速やかに対応するようにしましょう。
参考:所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A | 出入国在留管理庁
企業が行うべき手続き
外国人従業員が退職した際、企業は「中長期在留者の受入れに関する届出」の出入国在留管理庁への提出が推奨されています。
中長期在留者の受入れに関する届出は努力義務(任意)であり、提出しなかった場合の罰則はありませんが、企業としての適正な管理体制が問われる場面で不利に働く可能性があります。
中長期在留者の受入れに関する届出の概要は以下の通りです。
|
一方で、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」は義務となっており、これを怠ると30万円以下の罰金が科される場合があります。
外国人雇用状況の届出の概要は以下の通りです。
|
なお、このハローワークへの届出を行った場合、入管への「中長期在留者の受入れに関する届出」は省略可能です。
参考:中長期在留者の受入れに関する届出 | 出入国在留管理庁
就労ビザの審査期間はどのくらいかかる?在留期間や必要書類も解説
退職後帰国する場合の4つの注意点

外国人材が退職後帰国する場合の注意点はおもに以下の4つです。
ここでは、下記の注意点について解説します。
|
1.税金や社会保険の未納確認をする
日本で働いていた外国人が退職後に母国へ帰国する際には、税金や社会保険の未納がないかを必ず確認しておく必要があります。
退職時点で未納の住民税や所得税、または社会保険料(厚生年金・健康保険)がある場合、帰国後でも請求される可能性があります。
場合によっては、再入国時に問題となることや、ビザ申請などに悪影響を及ぼすケースもあるため、全ての支払い状況をクリアにしておくことが大切です。
納付状況の確認には、以下の書類を事前に入手・確認しておくと役立ちます。
- 源泉徴収票
- 社会保険の加入証明書や領収書
- ねんきん定期便や年金記録証明 など
万が一書類だけでは判断が難しい場合は、以下の窓口で直接確認すると確実に状況が確認できます。
- 税務署
- 市区町村役所
- 年金事務所
退職後にスムーズに帰国し、将来的なトラブルを避けるためにも、上記のいずれかの方法で把握するようにしましょう。
2.銀行預金口座の解約をする
日本での退職後に母国へ帰国する際は、使用していた銀行口座の取り扱いについても確認が必要です。
日本の銀行口座は帰国後も維持は可能ですが、利用しない場合は以下のようなリスクがあるため解約しておく方が安心です。
- 住所変更や本人確認情報が古いままだと、通知や重要書類が届かなくなる
- 一定期間利用がない場合、銀行によっては未利用口座管理手数料が発生する
- 残高が少ないと手数料で自動的に解約される場合がある
銀行口座の解約は、原則として銀行窓口での手続きが必要で、解約には以下のものが必要です。
- 通帳(ある場合)
- キャッシュカード
- 登録した印鑑(印鑑不要の銀行もあり)
- 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
放置による手数料やトラブルを防ぐためにも、必要書類を準備し、帰国前に銀行窓口で手続きを済ませるようにしましょう。
3. 賃貸契約の解約をする
外国人労働者が日本での就労を終えて帰国する際、住居として借りていた賃貸物件の解約手続きは必ず行う必要があります。解約の連絡が遅れると余計な家賃が発生したり、敷金が正しく精算されないなどのトラブルにつながる恐れがあるため注意が必要です。
賃貸契約では、解約する際には退去希望日の1ヶ月以上前までに通知を行う旨が契約書に定められているのが一般的です。また、実際の解約では、口頭の連絡だけでなく解約通知書を提出する必要があり、近年ではオンラインでの提出が可能な場合もあります。
そして、退去時には入居時と比べて部屋の状態がどう変化しているかを確認する「原状回復チェック」が行われます。退去の際には、管理会社と立ち会って部屋の状態を確認し、修繕内容や敷金精算の詳細を説明してもらうようにしましょう。
4. 水道光熱費・通信費の未納確認と解約をする
日本を退職して帰国する際には、水道・電気・ガスなどのライフラインや、インターネット・携帯電話などの通信契約の未納や解約忘れがないかを必ず確認しましょう。
公共料金や通信費の支払いを放置したまま帰国すると、後日督促状が届いたり、法的な請求に発展するリスクがあります。特に、支払い方法にクレジットカードを利用していた場合は、未払いがカード会社の信用情報機関に登録され、「延滞」扱いになる可能性もあります。
信用情報に傷がつくと、将来的に日本で再びクレジットカードを作ったり、賃貸契約を結んだりする際に不利になることもあるため、退職後はすべての請求状況を明確にしておくことが大切です。
退職後の就労ビザにおけるまとめ

外国人が日本で退職した後は、本人・企業ともに迅速な手続きが必要です。
特に就労ビザは「働くこと」が前提のため、無職のまま放置すると在留資格の取り消しリスクがあります。
退職後に本人側・企業側が行うべき対応は以下の通りです。
| 本人 | 退職した日から14日以内に「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁に提出 |
| 企業 |
|
就労ビザ保持者の退職後は、期限を守った行動と確実な手続きが非常に大切です。本人・企業の双方が正しく対応し、トラブルなく次のステップへ進めるように準備を進めましょう。