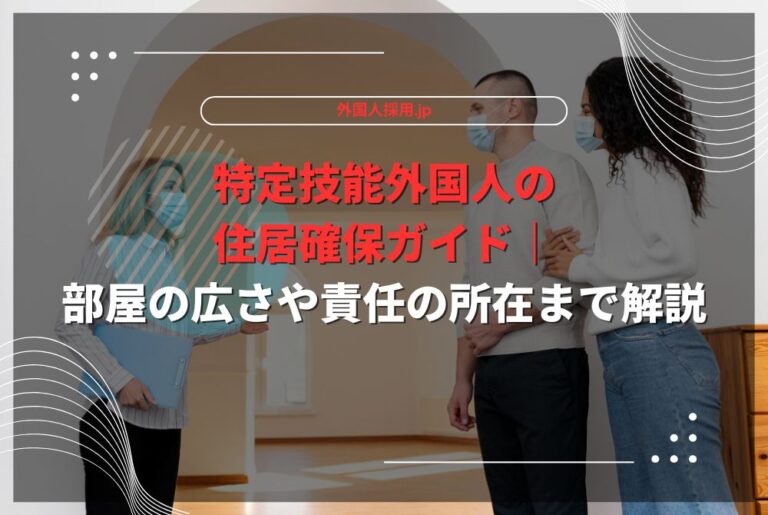特定技能外国人を受け入れる企業や支援団体にとって、住居の確保は重要なステップです。生活基盤の安定は、就労継続や定着率にも大きく影響するため、事前の準備と理解が不可欠です。
本記事では、部屋の広さや家賃相場といった基本情報から、契約時の責任の所在、保証人の要否、支援機関の役割までを幅広く解説します。また、企業が押さえておくべきポイントを具体的にご紹介します。
特定技能外国人人材紹介会社おすすめ10選!選び方や費用相場を解説
特定技能外国人の住居確保が求められる理由

企業・支援団体・自治体などに特定技能外国人の住居確保を求められる大きな理由の一つは、「外国籍の方が賃貸物件を借りるのが難しい」点にあります。
日本で外国籍の方が部屋を借りるのが難しい背景には、日本語の壁や文化の違い、不動産制度への不慣れさなどに起因した以下のような項目が影響しています。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 大家が外国人への賃貸を敬遠しがち | ・言語トラブルや文化的な誤解、あるいは帰国時の連絡不能リスクなどを懸念
・日本に知人や保証人がいないことが多く、契約に不可欠な連帯保証人を立てられない点も障壁となっている |
| 収入審査に通りにくい | 特に単身留学や「技術・人文知識・国際業務」ビザで初来日した方は、安定収入の提示が難しく、信用力不足と見なされやすい傾向がある |
| 日本語の読み書きが難しい | 専門用語が多い重要な契約内容が理解できず、契約そのものが破談になりかねない |
| 契約に必要な書類を準備できない | 日本の賃貸契約では、在留カードや収入証明、連帯保証人の情報など多くの書類が求められ、それを揃えるのが難しい |
| 礼金・敷金・更新料など日本独自の賃貸慣習 | 契約時・契約中に家賃以外で支払う費用の項目が多く、資金面で諦めざるを得ないケースもある |
一人で来日し、日本での保証体制に弱い外国人の場合は、上記の項目から住居探しが難航する可能性が非常に高いといえます。
そのため、企業・支援団体・自治体などが受け入れ体制を整備し、言語支援・保証人代行・文化適応の説明などを充実させる必要があります。
特定技能とは?技能実習との違いや1号・2号の特徴、採用方法を解説
特定技能外国人の住居確保の責任の所在

特定技能外国人の住居確保の責任の所在は、原則として雇用主である受入れ機関(企業)にあります。この住居確保は、出入国在留管理庁が定める制度上の義務として明確に位置づけられており、単なる努力義務ではありません。
住居確保に対して受入れ機関が果たすべき具体的な対応は以下の通りです。
- 住宅に関する情報を提供し、必要であれば物件見学の同行や契約手続きをサポート
- 賃貸契約時における家主とのやり取りを通訳したり、契約条件の調整を支援
- 入居後のトラブルを未然に防ぐため、生活ルールやマナーについて事前に説明
- 適切な家賃や部屋の条件を確認した上で、希望に合った住まいを紹介 など
また、受け入れ機関が住居確保以外に果たすべき義務は以下の通りです。
| 義務 | 概要 |
|---|---|
| 雇用契約の適切な履行 | 単に契約を結ぶだけでなく、契約内容に基づいた報酬の支払いや労働条件の遵守が求められる |
| 外国人への支援の実施 | ・住居確保以外にも通訳対応・生活ルールの説明など、生活基盤の整備を伴う支援を行う必要がある
・企業が支援を直接行うのが難しい場合には、登録支援機関に委託するのも認められている |
| 出入国在留管理庁への各種届出 | 特定技能外国人の雇用・住居・支援に関する情報は、出入国在留管理庁へ定期的に報告する義務がある |
上記の義務を怠った場合、受入れ企業は「改善命令」や「特定技能外国人の受入れ停止」の行政指導を受ける可能性があります。
特定技能制度は単なる労働力受入れではなく、外国人材の尊厳ある生活の実現が前提とされており、企業の責任を持った対応が円滑な受け入れと長期的な人材活用につながります。
1号特定技能外国人への具体的な支援方法

住宅確保に関する1号特定技能外国人への具体的な支援方法は以下の通りです。
ここでは、下記の支援方法について解説します。
|
寮・社宅を企業が提供
1号特定技能外国人の住居支援において、企業が自社所有の寮や社宅を活用するのは制度上定められた義務的支援の行使において問題ありません。
自社所有の寮や社宅を活用する場合は、持ち物件をそのまま貸与するため、賃貸契約や光熱費手続きが不要であり、日本語に不慣れな外国人でも安心して生活を始められます。
また、家賃の一部を本人に負担させるのも可能ですが、その金額設定には厳格なルールがあります。
企業が利益を上乗せすることは禁止されており、借上げ物件では実際の費用を人数で割った額以内、所有物件の場合も建築費や耐用年数などを踏まえ、合理的な金額でなくてはなりません。
自社所有の寮や社宅の活用は、企業側・1号特定技能外国人双方にとってメリットの大きい方法といえます。
企業が賃貸物件を借りて提供
企業が特定技能外国人のために民間の賃貸住宅を契約し、その住居を提供する方式は、住環境を整える現実的かつ柔軟な支援方法の一つです。
賃貸住宅を企業名義で借りる方法のメリットは、家賃滞納や契約違反などのリスクを企業側で管理・コントロールできる点にあります。
個人契約と異なり、トラブル発生時には企業が主体的に対応できるため、大家との信頼関係も築きやすく、安定した賃貸契約の維持につながります。
また、賃貸物件の場合も家賃の一部を外国人本人に負担させるのも可能ですが、その際は必ず事前の同意が必要です。さらに、家賃は実費相当であるのが前提で、企業が利益を上乗せするような設定は認められていません。
そして、住居の選定においては、外国人本人と相談の上で物件を決定するのが原則で、本人の希望や通勤利便性、宗教・食文化などを尊重しながら選ぶ必要があります。
企業が賃貸物件を借りて提供する方式は、管理負担を一部抱えることにはなりますが、安定性と柔軟性を両立できる支援策として、現場で広く活用されています。
本人が契約するのを企業がサポート
1号特定技能外国人が日本国内で一人暮らしを始めるケースでは、本人による賃貸契約を企業が支援するパターンも一般的です。本人が賃貸物件を契約する場合は、企業側は以下のような対応で支援する必要があります。
- 不動産仲介業者の紹介
- 物件情報の提供
- 物件の下見や契約手続きに同行 など
また、借りようとする賃貸物件で連帯保証人を立てる必要があるが本人が立てられない場合は、企業は保証人になるか、家賃債務保証会社の利用手配と共に、緊急連絡先としての役割を担う必要があります。
さらに、保証会社を利用する場合の保証料は企業側が全額負担する必要があり、外国人本人に支払わせることは認められていません。なお、出入国管理庁が公開している資料で詳細については解説されていますので、より詳しく知りたい方は参考にしてください。
特定技能1号から2号への移行方法を徹底解説!要件や試験内容も紹介
1号特定技能外国人の部屋の広さ

特定技能1号外国人の住居確保では、広さの面でも守るべき明確な基準があります。
まず、原則として一人あたり7.5㎡以上の居室が必要とされています。一人あたり7.5㎡以上の広さは居住用スペースすべてを含めた面積を対象とし、ロフト部分は含まれません。
また、ルームシェアをする場合でも、「居室全体の面積÷居住人数」が7.5㎡以上であれば問題ありません。一方で、技能実習生は4.5㎡以上の寝室を確保するのが条件となっており、その関係で以下の3つすべての条件を満たすケースでは、特定技能1号外国人でも一人当たり4.5㎡以上での住居の提供が可能です。
- 技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更した場合
- 同じ企業が引き続き受け入れ、本人が以前から居住していた住居を使用する場合
- 本人が引き続き以前の社宅などに住みたいと希望している場合
なお、上記の例外規定に該当して7.5㎡以下の住居であっても、寝室は4.5㎡以上でなければならないのは変わりません。企業が住居支援を行う際は、広さに関するルールも正確に把握し遵守すれば、安全で信頼ある受け入れ体制構築につながります。
1号特定技能外国人の住宅確保における注意点

1号特定技能外国人の住宅確保におけるおもな注意点は以下の通りです。
ここでは、下記の注意点について解説します。
|
企業は住居提供で利益を得てはならない
特定技能外国人の住居支援を行う企業には、制度の公正性を保ち、外国人労働者に対する不当な経済的負担を防ぐために「住居提供によって利益を得てはならない」という明確なルールが設けられています。
住居提供にはおもに自社所有の社宅・寮を提供するパターンと、法人名義で物件を借りて特定技能外国人を入居させるパターンの2種類があり、それぞれの場合で注意すべき点は以下の通りです。
| 方式 | 注意点 |
|---|---|
| 自社所有の社宅・寮を提供する | 家賃は「建設費や改築費、耐用年数、入居人数」などを基準にして、合理的に設定する |
| 法人名義で物件を借りて特定技能外国人を入居させる | ・家賃は「借上費用(管理費・共益費を含む)の総額を入居人数で割った金額以下」に設定しなければならない
・敷金・礼金・保証金・仲介手数料などの初期費用は、家賃額に含めてはならず、別途企業が負担するか、必要に応じて実費で明示的に処理する必要がある |
上記のルールに違反した場合、出入国在留管理庁などから是正指導や受け入れ停止命令といった行政処分を受けるおそれがあり、企業としての信頼や採用活動にも大きな影響を及ぼします。
特定技能制度の趣旨を理解し、住宅提供はあくまで外国人の生活支援の一環である点を前提としなければなりません。
詳細については以下の出入国管理庁の資料をご覧ください。
保証料金は企業が負担する
特定技能1号外国人に住居支援を行う際は、企業は保証料を含む契約に伴う費用について、外国人本人に負担を求めてはならない点にも注意が必要です。
企業が賃貸住宅を借り上げて提供するケースでは、契約の当事者が「法人」であるため、契約時に発生する敷金・礼金・保証料などの費用を外国人本人に請求できず、企業側が全額負担する必要があります。
一方、外国人本人が自ら賃貸契約を結ぶケースでは、原則として敷金・礼金・保証料などの初期費用は本人が負担するのが一般的ですが、企業側の任意での一部または全額の補助は可能です。
特に注意すべきは、どの契約であっても賃貸の保証に保証会社を利用する場合の保証料については必ず企業側が負担しなければならない点です。
保証料の支払い義務は制度的に明確に定められており、企業がその負担を外国人に転嫁するのは禁止されています。
自治体への届け出も支援の一部
特定技能1号外国人が新たに住居を確保した場合、その住所を90日以内に市区町村へ届け出ることが法律で義務付けられています。住所の届出は「住民基本台帳法」に基づくものであり、外国人であっても中長期在留者として日本に居住する以上、必ず行わなければなりません。
対象となるのは、入国後の初回届出だけでなく、引っ越しをした場合の住所変更も含まれます。住所の届出を怠った場合、最悪のケースでは在留資格が取り消される可能性があるため、非常に重要な手続きの一つです。
そのため、企業が行うべき支援の一環として、市区町村役所への同行支援を行うことが望ましいとされています。特に来日直後で日本語に不慣れな外国人にとっては、行政窓口でのやり取りは心理的なハードルが高く、企業が同行するだけでも大きな安心につながります。
また、住所の届出のような自治体への届出支援は、出入国在留管理庁が定める「1号特定技能外国人支援計画」における必須支援項目の一つでもあるため、制度上の義務としても求められている点を把握しておくのも大切です。
特定技能外国人への支援は「登録支援機関」に委託可能

特定技能1号外国人を受け入れる企業(受入れ機関)には、「義務的支援」と呼ばれる全10項目にわたる支援を行わなければなりません。
全10項目の支援内容は自社だけで対応するのも可能ですが、支援実務に精通した体制を備えている「登録支援機関」にまとめて委託するのも制度上認められています。
また、過去2年以内に中長期在留者(就労資格者)の受け入れ実績がない企業や、外国人の生活支援経験のある役員・職員がいない組織は、支援業務をすべて登録支援機関に委託することが義務づけられています。
【2025年最新】おすすめの登録支援機関比較ランキング12選!選定ポイントや費用相場を解説
特定技能外国人の住居のまとめ

特定技能1号外国人の受け入れにあたっては、住居の確保・契約・支援に関する対応が重要です。
住まいは外国人が日本で安心して働き、生活を始めるための基盤であり、適切な対応がなされていない場合、定着率の低下や行政指導のリスクに直結します。
本記事では、住居面での支援内容として、部屋の広さに関する法的基準、企業による住居提供の方法、家賃や保証料の取扱い、役所への住所届出の支援義務、そして登録支援機関への委託制度までを包括的に解説しました。
住居確保の際には、企業が住居提供で不当な利益を得てはならない点や、保証料を外国人に負担させてはいけない点、自治体への届出を怠ることで在留資格が取り消される可能性がある点など、制度上の重要な注意事項を見落とさないようにする必要があります。
本記事を参考に、企業としての受け入れ体制を整備し、外国人材との信頼関係を築ける健全な雇用環境づくりにお役立てください。
ご質問・お問い合わせは以下のお問い合わせフォームで受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。