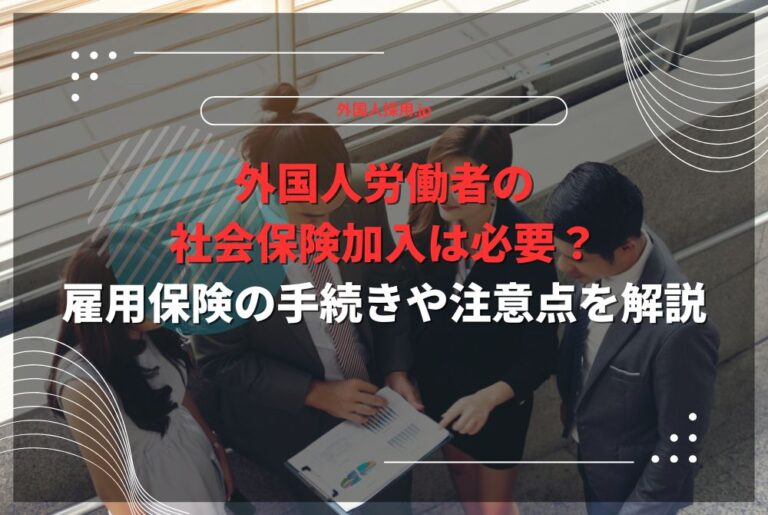外国人労働者を雇用する企業にとって、社会保険や雇用保険への加入義務は重要な確認事項です。対象者にあるにもかかわらず社会保険加入の手続きを怠った場合は、企業側が行政指導や罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
また、2025年5月には一部の適用要件が見直され、以下のように段階的に短時間労働者にも社会保険加入が義務付けられるケースが拡大することが決まっています。
- 短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず加入
- いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃
- 常時5人以上の者を使用する全業種の事業所が適用対象に変更
上記の要件に該当する外国人材は新たに社会保険の加入の対象となっているため、確認・対応が必要です。
本記事では、社会保険・雇用保険の基礎知識から、外国人雇用時における具体的な手続き、注意点までをわかりやすく解説します。
外国人労働者も社会保険の加入義務がある

就労可能な在留資格を持つ外国人材を採用する場合、条件を満たしていれば日本人と同じく社会保険への加入義務があります。
外国人材の社会保険加入に関するポイントは以下の通りです。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 原則として就労する外国人は社会保険に加入が必要 | 適用事業所で「常時使用される者」が働いていれば、国籍に関係なく被保険者になる |
| 就労には適切な在留資格(就労ビザ)が必須 | 「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能実習」「特定技能」等の在留資格を持っていれば就労可 |
| 「留学」「家族滞在」などの資格では原則就労不可で、特別な許可が必要 | 「資格外活動許可」があれば一定条件下でアルバイト可能 |
| 「永住者」や「日本人の配偶者等」は就労制限なし | 就労制限がないため、社会保険加入の対象となる |
| アルバイトでも労働条件によっては加入対象 | 正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働くアルバイト・パートは、被保険者になる |
| 外国人留学生のアルバイトは労働時間に制限あり |
|
出典:外国人従業員を雇用したときの手続き|日本年金機構
出典:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省
出典:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 政府広報オンライン
外国人労働者の雇用保険加入手続き

雇用保険とは、労働者が失業した場合などに一定の給付を行い、生活や再就職を支援する国の制度です。
外国人労働者であっても、日本で適法に就労しており、所定の条件を満たしていれば原則として雇用保険にも加入する義務があります。
雇用保険のおもな給付内容と加入条件は以下の通りです。
| 給付内容 |
|
| 加入条件 |
|
外国人労働者が加入条件を満たしている場合、企業側は速やかに以下の手続きを行う必要があります。
- 被保険者資格取得届をハローワークへ提出
- 在留カードなどの在留資格を確認
- 雇用保険料の控除および事業主の保険料負担の実施
また、以下のようなケースでは、雇用保険に加入しない・できない可能性があります。
- 週20時間未満の勤務
- 雇用期間が31日未満の短期契約
- 学生(ただし、夜間・定時制・通信制、休学中などは例外となる場合もあり)
外国人労働者であっても、就労可能な在留資格を持ち、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、日本人と同様に雇用保険への加入義務が発生します。
失業や育児休業、スキルアップの場面で給付を受けられる重要な制度であるため、企業は対象者の在留資格や労働条件を正確に確認し、確実に手続きを行うようにしましょう。
外国人採用でのハローワークの利用方法とは?届出から手続きの内容を解説
外国人労働者とその他の社会保険

外国人材が条件を満たした際に加入する社会保険の内訳は以下の通りです。
ここでは、下記の保険について解説します。
|
健康保険
健康保険は、民間企業や法人などに雇われている従業員及びその扶養家族を対象に、病気・けが・出産などの医療リスクを軽減するための制度です。
医療費の自己負担割合軽減、出産手当金、傷病手当金などの給付があり、外国人労働者にも原則として適用されます。外国人労働者が「健康保険」に加入するには、雇用先が「強制適用事業所」か「任意適用事業所」のどちらなのかがまずポイントで、強制適用事業所の場合は加入が義務となります。
強制適用事業所と任意適用事業所の認定条件は以下の通りです。
| 区分 | 認定条件 |
|---|---|
| 強制適用事業所 |
|
| 任意適用事業所 | 強制適用事業所の要件に該当しない事業所 |
出典:適用事業所とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
任意適用事業所の場合は、従業員の希望や事業主の申請で、健康保険の適用を受けることができるようになるケースもあります。
また、健康保険に加入すべき従業員の要件は、外国人・日本人を問わず、以下のような条件により判断されます。
| 条件 | 概要 |
|---|---|
| 常用の雇用形態 | 役員・代表者なども含まれる |
| 所定労働時間・所定日数が正社員の4分の3以上 | アルバイト・パートでも、所定労働時間・日数が正社員の約75%以上であれば対象 |
| その他の要件 | 以下の要件をすべて満たすと対象になる場合がある
|
上記の事業所・従業員の要件がすべて該当しない場合は、国民健康保険への加入が求められます。
外国人の国民健康保険加入条件は以下の通りです。
- 在留期間が3か月を超える
- 「特別永住者」「一時庇護許可者」などの特定の在留資格を保有している
- ほかの健康保険に加入していない
- 居住地の市区町村に住民登録がある
健康保険は、外国人労働者にも適用される重要な制度で、「強制適用事業所・任意適用事業所」の区分、「被用者としての勤務条件」など複数の要件を満たすと加入義務が発生します。また、勤務先の健康保険に入れない場合などは、国民健康保険への加入も検討すべきです。
企業・外国人双方で制度を正しく理解し、適切に手続きをするようにしましょう。
年金保険
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国籍を問わず全員が年金制度に加入する義務があります。外国人労働者も在留資格を持ち、日本で働く場合は必ず年金保険に加入しなければなりません。
年金制度にはおもに「国民年金」と「厚生年金保険」があり、働き方によって加入先や保険料の負担の内容が以下のように異なります。
| 区分 | 対象 | 保険料の負担 |
|---|---|---|
| 国民年金 | 個人事業主やフリーランス、厚生年金に加入していない20歳〜60歳未満の人 | 全額自己負担 |
| 厚生年金保険 | 会社員やパートなど、雇用されている労働者 | 労働者と会社が折半 |
また、外国人労働者が日本で年金に加入した後に帰国する場合、一定の条件を満たせば「脱退一時金」を請求できます。
脱退一時金の請求を行うために満たす必要のあるおもな要件は以下の通りです。
- 日本国籍を持っていないこと
- 国民年金または厚生年金の加入期間が6か月以上あること
- 資格喪失から2年以内に請求すること
- 老齢年金の受給資格期間(通常10年以上)を満たしていないこと
ただし、一時金を受け取るとその期間は将来の年金受給資格に算入されなくなる点には注意が必要です。さらに、外国人労働者でも、日本での年金加入期間が通算で10年以上あれば、将来「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」を受給できる可能性があります。
外国人労働者を受け入れる企業は、年金保険の仕組みや手続きを正しく理解し、適切に対応することが求められます。
労災保険
労災保険は、雇用形態や国籍・在留資格を問わず従業員を一人でも雇っている事業所は加入しなければなりません。
労災保険に加入していない場合、以下のようなリスク・罰則を受ける可能性があります。
- 業務災害や通勤災害に対する補償が全額事業所負担となる
- 未加入が発覚した期間の保険料を遡って支払う必要があり、さらに延滞金や追徴金が課されるケースもある
- 労働基準監督署などからの命令への違反、虚偽報告や申告義務の不履行などの場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則が科される
- 社会的信用の低下を招く など
労災保険に関するリスクを避けるために必要な対策例は以下の通りです。
- 労働者を雇用したら必ず労災保険の適用・加入手続を行う
- 社員・労働者へ労災保険に関する情報提供・サポートを実施する
- 安全衛生教育の実施、作業指示の明確化、機器の安全対策、言語対応などを通じて事故リスクを下げる
- 災害発生時には、遅滞なく労働基準監督署に「労働者死傷病報告」などを提出する
労災保険の加入は法令で強く義務付けられており、特に外国人労働者を雇う場合には、加入漏れや手続き不備が後々トラブルになりやすい部分でもあります。
万が一の事故やケガに備え、雇い入れた時点で確実に加入するように心がけましょう。
外国人労働者の社会保険における3つの注意点

外国人労働者の社会保険における3つの注意点は以下の通りです。
ここでは、下記の注意点について解説します。
|
在留カードを必ず確認する
外国人労働者を雇用する際は、在留カードの確認が必須です。
社会保険や雇用保険に適切に加入させるには、在留カード内の以下の2点を確認するようにしましょう。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 就労可能かどうか | 「在留資格」欄や「就労制限の有無」を確認し、就労可能なビザを保有しているかを確認する |
| 資格外活動許可の有無 | 就労不可の在留資格でも、裏面に「資格外活動許可」があればアルバイトなどが可能 |
確認を怠ると、不法就労や保険加入の誤りにつながるリスクがあるため、雇用前に必ず在留カードの原本を確認し、記録を残す必要があります。
社会保障協定出身者かどうかを確認する
外国人を雇用する際は、出身国が日本と社会保障協定を結んでいるかを必ず確認しましょう。
協定国出身者は、日本と母国の年金加入期間を通算できるため、老後に年金を受け取れる可能性があるため、脱退一時金を請求しなくても将来年金を受け取れるケースがあります。
また、脱退一時金を請求すると通算の対象外になる場合があるため、本人の意思確認と制度の理解が重要です。採用時に協定対象国かをチェックし、必要に応じて本人に説明すると、外国人材も安心して勤務できます。
家族を扶養に入れるには条件あることを把握する
社会保険に加入している従業員が家族を被扶養者(扶養家族)として認めてもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被保険者により生計を維持されている
- 日本国内に住所(住民票)がある
ただし、例えば留学生として海外に住んでいたり、被保険者の海外赴任に同行している場合は、日本に住んでいなくても被扶養者として認定される場合があります。
外国人労働者の社会保険におけるまとめ

外国人労働者を雇用する企業は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険への加入義務があるのを理解しておく必要があります。
国籍を問わず、所定の労働条件を満たせば日本人と同様に保険制度の対象となります。また、雇用保険については加入条件を満たさない場合でも、ハローワークへの届出が必要です。
そして、企業側がトラブルを未然に防ぐためには、以下の注意点も改めて把握しておきましょう。
- 在留カードの確認
- 社会保障協定の有無
- 扶養家族の認定条件
- 労災保険の適用漏れ防止 など
上記の項目の確認を行い、適切な社会保険加入と手続きを進めれば、企業としての法令遵守はもちろん、外国人労働者の安心・安定した就労環境にもつながります。
今後さらに増加が見込まれる外国人労働者への対応として、万全な体制づくりを心がけてください。