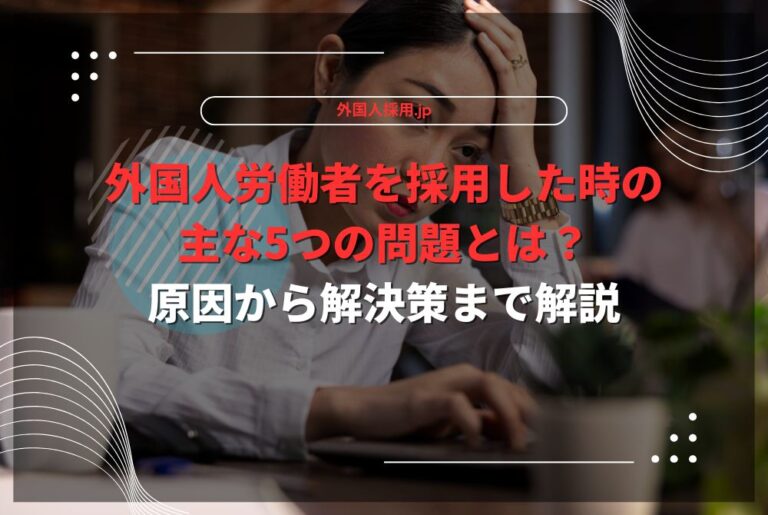日本企業にとって、外国人労働者の採用は人手不足解消の有力な手段ですが、実際にはさまざまな課題に直面するケースが少なくありません。
言語や文化の違い、ビザ管理の複雑さ、社会保険や労務対応の不備など、適切に対処しなければトラブルに発展するリスクもあります。
本記事では、外国人採用における代表的な5つの問題点とその原因、そして企業として取るべき具体的な解決策までをわかりやすく解説します。
日本の外国人労働者の現状

日本で働く外国人労働者の現状として特徴的なのは以下の2点です。
ここでは、下記の特徴について解説します。
|
外国人労働者は増加している
外国人労働者は近年増加傾向にあります。厚生労働省が公表した「外国人雇用状況の届出状況(令和6年10月末時点)」によれば、事業主からの届出ベースでの外国人労働者数は2,302,587人に達し、前年比で253,912人の増加、対前年増加率は12.4%と、届出義務化された平成19年以降過去最多を更新しました。
また、外国人を雇用する事業所数も342,087ヶ所と、前年度から3,312ヶ所増加し、こちらも過去最高水準を記録しています。対前年増加率は7.3%で、前年度の6.7%を上回っています。
在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」(技術・人文知識・国際業務など)が718,812人となり、前年比で20.6%の伸びを示し、届出制度導入以降で初めて最も多い在留資格区分となりました。
厚生労働省のデータは、日本国内で外国人労働者への依存度がますます高まっているのを示しており、単なる「補助的な労働力」ではなく、労働市場の一角を占めつつある存在になっている現状が読み取れます。
出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)|厚生労働省
ベトナム、中国国籍の外国人労働者の割合が多い
「外国人雇用状況の届出状況(令和6年10月末時点)」によれば、国籍別の外国人労働者の割合は以下のようになっています。
| 国籍 | 人数 | 全体における構成比 |
|---|---|---|
| ベトナム | 570,708人 | 24.8% |
| 中国(香港・マカオ含む) | 408,805人 | 17.8% |
| フィリピン | 245,565人 | 10.7% |
| その他 | 1,077,509人 | 46.7% |
※「その他」にはネパール、インドネシア、ミャンマー、ブラジルなど複数国籍が含まれます。
国籍別で比較した場合、ベトナム・中国勢だけで構成比42.6%に達しているのが最大の特徴です。これまでは中国勢が最多を占めてきた時期もありましたが、近年ではベトナムがその座を奪取し、以降トップを維持する傾向が続いています。
現状における偏重傾向は、国別政策・文化的適応・言語対応の負荷を企業に強いる可能性が高く、外国人採用を進める際には上位国籍の動向を注視しつつ、その他国とのバランスも考える必要があります。
【2025年最新】外国人労働者国別ランキング!日本における割合や推移も解説
外国人労働者採用における日本の考え

外国人労働者採用においては、未だに以下のように捉えているケースが散見されます。
下記の捉え方は就労ビザや関係する法律などへの理解が及んでいない点があるために起きています。そこで、ここでは下記の点について実態はどうなのかを解説します。
|
安く雇用できると考える人もいる
外国人労働者の採用について、「日本人よりも安く雇用できる」というイメージを持つ企業担当者も少なくありません。しかし、安く雇用できるイメージは誤解を生みやすく、採用後のトラブルや離職リスクを高める原因にもなります。
外国人労働者に対して賃金が安い印象を持つ背景には、以下のような要因が考えられます。
- 統計上の賃金差がある
- 技能実習や特定技能制度を利用する外国人は、単純労働や軽作業に従事するケースが多く、その分賃金が抑えられる傾向にある
- 日本語に不慣れな外国人労働者は、自ら待遇交渉を行いづらく、結果的に低待遇に甘んじてしまうケースがある
実際に、上記の背景により企業側が外国人を「安価な労働力」として扱うと、以下のような問題を引き起こす可能性があるため是正すべきです。
- 最低賃金を下回る給与や、未払い残業代などが発生すると、重大な法令違反になる
- 正当な評価がされないことで外国人労働者のやる気が削がれ、離職につながる
- 差別的・搾取的な扱いが報道やSNSなどで拡散され、企業イメージが悪化する
そもそも大前提として、外国人だからといって日本人よりも安く雇えることはありません。
外国人労働者の賃金が相対的に低くなる背景は存在するものの、それを理由に待遇を抑えることは法令違反や離職リスクを招く可能性があります。
企業は固定観念にとらわれず、外国人も一人の貴重な人材として適切な処遇と評価を行うことが、持続的な人材確保につながります。
技能実習制度を人手不足解消のためと考える人もいる
企業や地方自治体のなかには、深刻な人手不足を背景に、技能実習制度を「安価な労働力を確保する仕組み」として捉えるケースがあります。
技能実習制度は1993年に本格導入された制度で、その設立当初の目的は「開発途上国への技術移転を通じた国際協力」であり、人手不足の解消が目的ではありません。
しかし、近年の日本国内での慢性的な人手不足を背景に、技能実習制度を「労働力補填」の手段と見なす方向に制度運用がシフトしている点が批判の的となっています。
技能実習制度が「人手不足対応」のために使われているとみなされる背景には、以下のような問題・矛盾が影響しています。
| 問題 | 概要 |
|---|---|
| 低賃金・残業代未払い | 実習生が最低賃金を下回る待遇、残業代の未払いなどを受けるケースがある |
| 長時間労働・過重労働 | 長時間労働が常態化している受け入れ先があることが判明している※ |
| 転職禁止 | 実習生は通常、受け入れ企業から他企業へ転職できず、不適切な待遇を受けても逃げ場がない |
| 帰国後の勤務実態 | 多くの実習生が帰国後、実習時の技能とは無関係な職に就く実態があり、制度本来の「技術移転」の実効性が疑問視されている |
上記の問題が積み重なった結果、制度が形骸化し「外国人労働力を安く導入する手段」として機能してしまうようになった点が国内外からの批判の的となっています。
そのため、日本政府は技能実習制度を発展的に解消し、2027年を目途に施行する「育成就労制度」を新設する法改正を行いました。育成就労制度では、従来の「実習」という枠組みから脱却し、人材育成と長期就労の両立を図ることが目指されています。
法改正により制度設計を刷新して、労働力補填的な誤用を制限し、外国人材を尊重する受入体制へと転換しようする流れがある点はしっかりと押さえておきましょう。
外国人労働者採用時の主な5つの問題

外国人労働者採用時に問題となりやすい事柄はおもに以下の5点です。
ここでは、下記の問題点について解説します。
|
不法就労させてしまうこと
外国人労働者の場合、労働基準法とは別に「出入国管理及び難民認定法」の対象にもなっており、企業側は別途この法律も遵守する必要があります。
外国人労働者を採用後、故意か否かに関わらず不法就労に該当する状態で働かせてしまうと、出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)第七十三条の二に抵触します。
| 第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者 |
たとえ「知らなかった」と主張しても、採用前の在留資格・在留期間・活動範囲等の確認を怠っていれば、不法就労助長罪が成立し得るという点を強く意識しなければなりません。
企業・事業主が外国人を雇う際に不法就労状態にしてしまいやすい典型的なケース例は以下の通りです。
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 在留資格が就労を認めない資格の者を働かせる | 短期滞在、研修、家族滞在などで来日した者を、就労を認められない形で労働に従事させる |
| 在留資格の有効期間を超えて働かせる |
|
| 許可された就労範囲を超えて働かせる |
|
| 偽造・他人名義の在留カードを利用する | 偽造カード、不正な在留カードを提示され、それをそのまま信じて雇用する |
| 非正規契約・委託契約を装って就労させる | 業務委託契約形式で、実質的には労働者と同じ働きをさせる |
| 複数アルバイトによる時間超過 | A社で週20時間、B社で週15時間働かせ、合計で法定時間を超過させる |
特に在留資格の確認や勤務時間の管理などに不手際があると、入管法違反となる可能性が高まるため慎重な対応が求められます。
意思の疎通が取れないこと
外国人労働者を導入した企業がしばしば直面する難しさの一つが、コミュニケーションのすれ違いです。相互理解のズレは、単なる言葉の問題にとどまらず、業務指示・報告・連絡・確認といった日々の業務運営全体に影響を及ぼします。
内閣府報告書「企業の外国人雇用に関する分析」では、外国人材とのコミュニケーションが容易な企業ほど、外国人材の定着率が高くなる傾向が認められると分析されています。
また、報告書内では企業は外国人材との関係構築・活用を進める際に「言語・意思疎通」を一つの主要な制約要因と認識しているとの結果が出ており、具体的には以下のような課題を挙げています。
- 業務指示・報連相(報告・連絡・相談)において、指示の意図が正しく伝わらない
- 専門・技術用語、業界慣行・社内ルールなどが外国人に理解しづらい
- 日本語能力の差異・習熟度のばらつき
「企業の外国人雇用に関する分析」で指摘されているような上記の課題を抱えている企業で起きやすい問題は以下の通りです。
- ミス・手戻りの頻発
- 労働災害のリスクが高まる
- ストレスの蓄積・摩擦による職場の雰囲気の悪化
- 定着率低下・離職増加 など
意思疎通が円滑に行えない状態は、多くの問題に波及するため早急な対処が必要となります。
互いの文化に対する理解不足
外国人労働者を採用する企業にとって、文化や宗教の違いを十分に理解せずに接するのは、職場トラブルや離職リスクにつながる大きな要因です。
特に以下のような宗教的背景や生活習慣の違いは、見えにくい部分で摩擦を生みやすいため、注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 食文化の違い | 宗教上、豚肉やアルコールを口にできない人がいる |
| 宗教行為 | 特定の時間に祈りを行う必要がある |
| 服装や外見に関する規律 | ヒジャブや帽子を着用する宗教的義務がある |
| 祝日・休日の認識の違い | 母国の祝日に休暇を取りたいという希望がある |
上記の違いは、「非常識」ではなく「文化の違い」によって起きている可能性が高く、正しい理解と事前の共有が欠かせません。
不適切な給与設定
外国人労働者の採用において、日本人と同じ仕事内容であるにもかかわらず、不当に低い賃金で雇用するケースが一部で見られますが、これはれっきとした法令違反です。
まず、労働基準法第3条では以下のように「国籍を理由とする差別」を禁じています。
| 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
上記の条項により、日本人と同様の業務をしているのであれば、原則として同等の給与を支払う義務があります。また、最低賃金法も日本人・外国人を問わず適用され、「同一労働同一賃金」の考え方も、雇用形態にかかわらず公正な処遇を求めるものであり、外国人労働者にも当然にその趣旨が及ぶものです。
「外国人」だけを根拠にした給与設定は不適切なものとなるため、関連する法令を意識した設定が求められます。
労働環境が整っていないこと
外国人労働者の採用が進む中で、長時間労働や危険作業、安全配慮の欠如など、労働環境が不十分な状態で働かせてしまうケースが問題視されています。
日本人と同様、外国人労働者にも労働基準法や安全衛生法が適用されますが、制度への理解不足や管理体制の未整備が原因で、法令違反や重大事故に繋がる例が後を絶ちません。
企業の現場で見られる「不適切な労働環境」の例は以下の通りです。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 長時間残業の強要 | 技能実習生に対して、1日10時間以上の労働や、休日返上の連勤を強いる |
| 危険な作業への配置 | 高所作業や重機操作を、十分な指導もなく任せてしまう |
| 熱中症・健康リスクの放置 | 真夏の屋外作業に空調服や水分補給の制度が整っていない |
| 残業代・手当の未払い | 残業時間の記録がなく、労働時間分の賃金が支払われない |
外国人労働者は、日本人と比較しさまざまな要素から不適切な労働環境に対し指摘するのが難しい側面もあり、上記のような環境が常態化しやすい傾向があります。
企業側が常日頃から適切な労働環境を提供できるように配慮する姿勢が大切です。
外国人労働者採用で問題が起きる原因

外国人労働者の受け入れには多くのメリットがある一方で、現場でトラブルが発生するケースも少なくありません。
外国人労働者採用で問題が起きる背景には、おもに以下の3つの原因が複雑に絡み合っているといえます。
| 原因 | 概要 | 発生しやすい問題 |
|---|---|---|
| 差別意識が消えていない | 「外国人だから」という無意識の偏見や先入観、あるいは明示的な差別観念が残っている |
|
| 相互理解が十分でない | 文化・宗教・言語・価値観などの違いを理解・配慮しきれていない |
|
| 法律への理解不足 | 事業主も労働者も、外国人労働に適用される法規制・義務を十分に把握していない |
|
上記の原因の解説は以下の通りです。
差別意識が消えていない
|
相互理解が十分でない
|
法律への理解不足
|
ここで取り上げた原因の解決策については、次項にて詳しく解説します。
外国人労働者採用における問題への解決策

外国人労働者採用における問題への解決のためには、以下の点を意識する必要があります。
ここでは、下記の項目について解説します。
|
国籍ごとの文化的習慣を理解する
外国人労働者とのトラブルを未然に防ぎ、良好な職場環境を築くためには、国籍ごとの文化的背景や価値観を理解しようとする姿勢が不可欠です。
ただ単に「働いてもらう」のではなく、「その人の文化を尊重する」という意識が、信頼関係の構築と離職率の低下につながります。
外国人労働者との円滑な関係構築のためには、以下のような取り組みが効果的です。
- 事前に国籍や宗教ごとの文化を調べる
- 本人と「価値観」について対話する
- 職場全体で文化共有・意識づけを行う
国籍や文化は、人の価値観や行動に強く影響を与えます。外国人労働者との信頼関係を築くには、「文化を尊重する」姿勢が最も効果的な方法です。
一方的な同化を求めるのではなく、違いを理解し、互いに歩み寄る姿勢が、多様性のある職場の実現につながります。
法律を理解し順守する
外国人労働者を適切に採用・管理するうえで、法律の理解と遵守は最も基本かつ重要なステップです。
不法就労をさせない・させられない体制を整えることで、企業は刑事責任・行政処分・社会的信用の失墜などのリスクを回避できます。
不法就労リスクをゼロに近づけるために押さえるべきおもな法令には出入国管理及び難民認定法(入管法)と労働基準法の2つがあり、それぞれで特に関係の深いものは以下の通りです。
【出入国管理及び難民認定法(入管法)】
| 条項 | 概要 | 企業に課される罰則 |
|---|---|---|
| 第73条の2 | 不法就労を助長した者に対して適用される規定 | 不法就労者を雇用/あっせんした者に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその併科 |
| 第74条の4 | 集団密航者を不法就労させた場合など、さらに重い処罰規定 | 5年以下の懲役または300万円以下の罰金(営利目的なら1年以上10年以下・1,000万円以下の罰金) |
| 第74条の8 | 退去強制を免れさせるために不法入国者・不法上陸者をかくまう行為 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(営利目的なら5年以下・500万円以下) |
出典:不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。
【労働基準法】
| 条項 | 条文(一部抜粋) |
|---|---|
| 第32条 |
|
| 第36条 | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
| 第34条 |
|
| 第24条 | 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 |
上記の法令は、日本人労働者・外国人労働者を問わず適用される「普遍的な労働法規」であり、企業が外国人を採用する際も、これらの遵守が前提条件となります。
受入れ体制を整える
外国人労働者の採用では、採用後の受け入れの準備が不十分だと、早期離職やトラブルの原因になります。
受入れ体制を整えるためのポイントは以下の3つです。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| マニュアルの整備 | 写真・図解入りで、多言語ややさしい日本語に対応。作業手順を明確に伝える |
| 教育制度の構築 | 安全衛生・業務OJT・先輩社員のフォローなど、段階的な研修を実施 |
| 言語支援の提供 | 日本語教材や翻訳ツール、通訳者の配置により、意思疎通のミスを防止 |
上記のマニュアル・研修・言語支援の3点を中心に受入れ体制を整えれば、企業と外国人労働者の双方にとって安心できる職場環境を構築できるでしょう。
外国労働者採用における問題のまとめ

外国人労働者の採用は、日本社会にとって重要な人材確保の手段ですが、その一方で、労働条件・文化理解・法令順守などさまざまな課題も抱えています。
ただ、外国人労働者の採用に関する課題は、企業の以下の取り組みによって解消されます。
- 法令遵守を徹底する
- 不平等な労働条件を是正する
- 言語や文化の違いに配慮する
- 受入れ体制を充実させる
外国人労働者の受け入れは、単に人手を補う施策ではなく、企業が「多様性と共生」に取り組む姿勢を問われる機会です。法令を守り、文化を理解し、教育と支援の体制を整えれば、採用後のトラブルを防ぎ、長期的な雇用と信頼関係の構築につなげられるでしょう。
本記事を参考に外国人労働者の採用を円滑に進めていただければ幸いです。