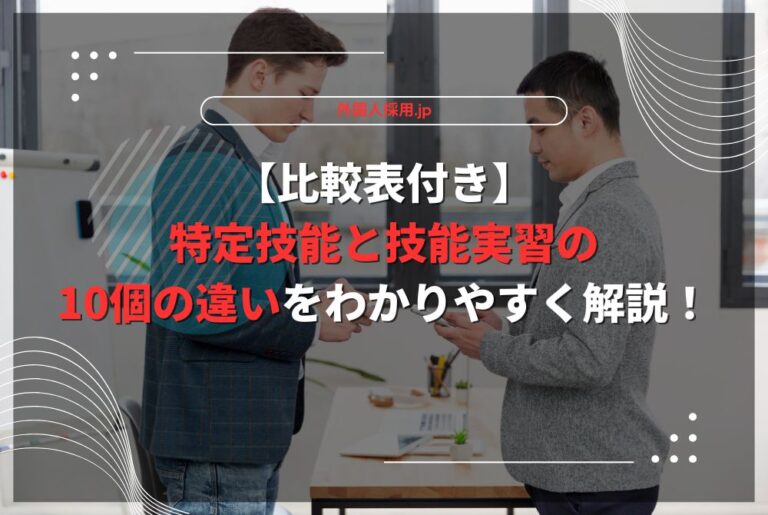外国人人材の受け入れ制度として「特定技能」と「技能実習」は混同されがちですが、実は制度の目的や対象、就労内容などに大きな違いがあります。
本記事では、これから外国人材の採用を検討する企業担当者の方や、人材受け入れ制度を見直したい方に向けて、両制度の違いを10項目に分けて徹底解説します。比較表も交えて、制度の本質や現場での影響までわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
【図解付き】特定技能と技能実習、10の違いをわかりやすく比較

特定技能と技能実習は、似た制度名ながらそもそもの目的から大きく異なる仕組みです。「特定技能」は国内の人手不足に対応するため即戦力を求め、「技能実習」は日本で技術を学んでもらい、母国に技術を持ち帰ってもらう国際協力が根底にあります。
以下にその違いを10項目で表にまとめました。
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足を補うための労働力確保制度 | 技術を母国に持ち帰るための国際貢献制度 |
| 携われる仕事 | 単純労働もOK | 単純労働はNG |
| 対象職種 | 限られた分野(16分野) | 91職種 |
| 必要スキル | 事前に一定の技能が必要 | 入国時のスキル不要(介護は別) |
| 試験 | 技能試験+日本語試験あり | 介護以外は試験なし |
| 転職の可否 | 同じ職種なら転職可 | 原則不可 |
| 在留期間 | 1号:最長5年/2号:無期限(一部分野のみ) | 最大5年(3号まで) |
| 家族帯同 | 2号は帯同可(配偶者・子) | 帯同不可 |
| 人数制限 | 分野によって制限あり(介護・建設など) | 企業規模に応じて厳しく制限 |
| 関係団体 | 企業と本人+支援機関(任意) | 複数の団体が関与(監理団体など) |
特定技能や技能実習制度についてさらに詳しく知りたい方は、以下の公式資料も参考にしてください。
特定技能制度(法務省 出入国在留管理庁):特定技能制度 | 出入国在留管理庁
1. 制度の目的
特定技能は「国内の即戦力確保」、技能実習は「海外への技術移転」がおもな目的であり、制度設計の思想そのものが異なっています。特定技能制度は、日本国内の人手不足を補うために2019年に創設された制度で、即戦力として外国人を受け入れるのが目的です。特に介護、外食、建設などの分野では人手不足が深刻化しており、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、実際の労働力として活躍することが求められています。
一方、技能実習制度は1993年に導入された制度で、日本の企業などで技能・技術・知識を修得し、それを母国に持ち帰って活かしてもらうのが目的です。
制度上は「労働力の補填」を目的としておらず、あくまで「人材育成」の枠組みとして設計されています。
2. 携われる仕事
特定技能と技能実習では、携われる仕事の内容において明確な差があります。特定技能は、日本で深刻な人手不足が続く介護・外食・建設などの分野で、単純労働を含む実務全般に従事可能です。
2019年の制度創設にあたり、製造ラインや接客業など、専門性を問わない業務も担えるよう法改正されています。
技能実習は、技能・技術・知識を習得することが制度の目的であるため、単純労働は禁止されており、工場でのライン作業や倉庫内での仕分け作業などの肉体労働には従事できません。特定技能は「人材確保」、技能実習は「技術習得」といった制度理念の違いから、携われる仕事にも違いがあります。
3. 対象職種
特定技能は16に絞られた重要産業をカバーしながら柔軟な就労を認める一方で、技能実習は90以上の専門職種・精緻な技能作業に特化しており、制度運用の枠組みもかなり異なります。
特定技能では、日本国内の深刻な人手不足が続く16の特定産業分野が対象です。2024年4月の改正で、新たに鉄道、林業、木材産業、自動車運送業などが加わりました。
一方、技能実習制度では、2025年時点で91職種・168作業が対象とされ、農業、漁業、建設、製造など多岐にわたる専門的技能の習得が可能です。
4. 必要スキル
必要スキルに関しては、特定技能と技能実習では求められる基準や前提知識が大きく異なります。特定技能では、入国前に相当程度の専門知識や経験が必須です。1号・2号ともに、実際に従事する産業分野での実務能力が問われ、技能試験と日本語試験の合格が求められます。
一方で、技能実習は「技能習得が目的」なので、入国時点では特定の技能や日本語能力は不要です。介護を除く分野では試験などもなく、入国前の講習を通じて基礎的な知識を学び、現場で経験を重ねながら技能を身につけていきます。
特定技能は即戦力として初めから基準を満たす人材を受け入れるのに対し、技能実習は育成過程として日本で学ぶことに重点を置いているのが大きな違いです。
5. 試験
特定技能と技能実習では、求められる試験内容・タイミング・レベルでそれぞれ違いがあります。特定技能では、入国・就労前に日本語能力試験と就労分野ごとの技能評価試験に合格する必要があります。また、技能実習2号を良好に修了している場合は、特定技能1号への移行が可能です。
一方、技能実習制度は「習得」が主眼であるため、試験の義務は分野ごと・号数ごとに異なります。介護分野では、介護技能実習評価試験が各号(1号から3号)ごとに義務付けられていますが、ほかの分野ではそもそも試験制度が必須ではない場合もあります。
6. 転職の可否
特定技能と技能実習における「転職の可否」については、制度の根本的な目的の違いが明確に表れています。特定技能では、一定の条件を満たせば同じ分野内での転職が可能で、例えば外食業で働いている外国人が、別の飲食企業に移ることは制度上認められています。
特定技能は労働力不足を背景とした即戦力人材の受け入れを目的としているため、労働者の流動性を一定程度確保することが重視されているのがおもな理由です。ただし、転職時の条件や行政手続きの煩雑さから、企業側・本人側いずれにとってもハードルがある点には注意が必要です。
一方、技能実習では原則として転職は認められていません。技能実習制度は「特定の企業で技能を修得すること」が目的のため、実習先の企業を離れて他社に移ることは制度趣旨に反します。そのため、基本的には受け入れ企業が変更できない仕組みとなっています。
ただし、例外的に「実習先の倒産やパワハラ・セクハラ等の人権侵害があった場合」や「実習計画に沿った正当な手続きを踏んだうえでの移籍(2号から3号への移行時など)」では、転籍が認められる場合もあります。
7. 在留期間
在留期間については、特定技能と技能実習で以下のように細分化された制度となっています。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習(1号~3号) |
|---|---|---|---|
| 更新間隔 | 4・6・12ヶ月ごと | 6・12・36ヶ月ごと | 1・2号で定期的 |
| 在留上限 | 通算5年まで | 上限なし(実質無期限) | 最長5年まで |
| 永住可能性 | × | 〇 | × |
上記の表の内容をまとめると以下の通りとなります。
- 特定技能1号は最大5年の在留で、おもに期間雇用を想定
- 特定技能2号は在留上限なし、家族帯同も可能で、永住も視野に入る長期的制度
- 技能実習はあくまで「技能移転」を前提とした最長5年の在留で、帰国前提の制度構造
特定技能2号以外は在留期間に限りがあるため、その点を踏まえて確認する必要があります。
就労ビザの審査期間はどのくらいかかる?在留期間や必要書類も解説
8. 家族帯同
特定技能と技能実習における「家族帯同」については、制度の根幹に関わる非常に重要な違いがあります。特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。例外的に、すでに家族が中長期在留資格(留学・家族滞在など)を持って日本に滞在しており、その状態で特定技能1号に移行した場合のみ、「特定活動(告示外)」として配偶者・子が日本に残れるケースはあります。
また、特定技能2号になると家族帯同が制度上認められます。配偶者と子どもは「家族滞在」の在留資格で同行でき、滞在期間も本人の在留に合わせて延長可能です。
一方で、技能実習制度では原則、家族帯同は一切認められません。技能実習は「本人が技能を習得し、母国に持ち帰る」ことを目的としており、5年間の在留期間中でも家族呼び寄せは不可です。
9. 人数制限
特定技能と技能実習においては、「人数制限」の取り扱いに明確な違いがあります。特定技能では、基本的に企業単位での人数制限は設けられていません。ただし、介護・建設など一部の分野においては、受け入れ人数に上限が設定されています。
一方、技能実習制度は、企業の規模に応じた厳格な人数制限が存在します。受け入れ可能な実習生の数は「常勤職員の人数」に応じて定められており、例えば常勤職員が30人以下の企業では技能実習1号生は3人までといった上限があります。
仮に、2号・3号へ移行した場合は、制度上その分の枠が拡大されるものの、依然として明確な上限の元で運用される点には注意が必要です。
特定技能は比較的柔軟に人材を確保しやすい制度である一方、技能実習は制度の趣旨からも「丁寧な育成」に重きを置いているため、受け入れ人数も厳しく制限されているのが特徴です。
10. 関係団体
特定技能と技能実習における「関係団体」の違いは、制度の運用体制や支援の仕組みに直結しており、受け入れ企業にとっても重要な要素です。特定技能では、外国人労働者を受け入れる企業(所属機関)は、外国人本人への支援を行う必要があります。外国人本人への支援は、企業が自ら行うことも可能ですが、多くの場合は「登録支援機関」と呼ばれる外部団体に委託します。
登録支援機関は法務省に登録された法人で、外国人の生活支援や各種手続きの代行、定期面談、日本語学習の促進、相談対応などの支援業務を担う機関です。
一方、技能実習制度では、企業単独で外国人を受け入れる「企業単独型」と、商工会議所や中小企業の協同組合などの非営利法人が中心となって運営される「監理団体型」の2つの受け入れ形態があります。
主流なのは監理団体型で、監理団体は技能実習生の受け入れに際して以下の業務・手続きを一貫して監理します。
- 申請手続き
- 計画作成
- 入国前講習
- 生活支援
- 監査・指導
- トラブル対応
- 帰国支援 など
特定技能では「登録支援機関」が任意で柔軟に活用できるのに対し、技能実習では「監理団体」が制度運営の基盤として機能している点が大きな違いです。
技能実習から特定技能への移行方法

企業担当者の中には、「せっかく技術を丁寧に教えた実習生が、実習期間終了とともに帰国してしまうのが惜しい」と感じる方も少なくありません。実習を通じて信頼関係が築かれ、「今後も自社で働いてほしい」と考えるケースも多いでしょう。
そのような雇用を継続したい企業に注目されているのが、「技能実習から特定技能への移行」という選択肢です。
技能実習から特定技能への移行は、実習生が引き続き日本で就労できる正当な方法であり、企業側にとっても即戦力となる人材を継続して雇用できるメリットがあります。技能実習から特定技能へ移行するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、技能実習2号を2年10カ月以上、良好に修了していなければなりません。また、移行できるのは同一の職種・分野に限られるため、例えば「建設」から「介護」といった異分野への変更は原則できません。実際の手続きは、在留期限の前に地方出入国在留管理局へ必要書類を提出するだけで完了します。
提出書類は「在留資格変更許可申請書」とその添付書類(在留カードや写真、技能実習修了証明書など)です。なお、技能実習制度は2027年をもって廃止され、代わりに「育成就労制度」という新しい制度が導入される予定です。
新制度では、より柔軟な転職やキャリアアップが可能になる一方で、現行の移行制度とは仕組みが変わる可能性があるため、早めの対応が求められます。
移行方法についての詳細は以下の資料も参考にしてください。
特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合) | 出入国在留管理庁
企業は技能実習と特定技能どちらの求職者を選ぶべきか

企業が外国人労働者を採用する際は、「どの在留資格の人材が自社の業務に合うか?」を基準に選ぶ必要があります。
特定技能と技能実習の業務の幅と適応性に関する比較表は以下の通りです。
| 観点 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 業務の幅 | 幅広く、関連作業も可 | 非常に限定的 |
| 単純労働 | 〇 | 原則× |
| コミュニケーション | 日本語能力基準があるため、現場指示が通りやすい | 日本語能力の要件がない(介護以外)であるため 指導負荷が高い可能性がある |
| 柔軟性 | 転職や業務変更が可能で、受け入れ調整しやすい | 基本的に受入先企業固定 |
特定技能は即戦力が求められる現場に適しており、16分野で単純労働含む幅広い業務に携われる制度です。業務内容も「主たる業務+関連業務」の範囲内であれば柔軟に対応でき、繁閑期の応援や派遣形式での採用も可能です。
一方で、技能実習は目的が「技術移転」であるため、職種は多いものの、業務内容はきめ細かく管理されています。双方の特性を考慮すれば、現業支援や生産性向上を優先したいなら特定技能、技術伝承・人材育成を重視するなら技能実習を選ぶのが得策です。
技能実習廃止による新制度【育成就労制度】に関して

1993年から施行された技能実習制度は当初「国際貢献・技術移転」を目的としていましたが、運用の現実は「低賃金労働」「長時間労働」「転職不可」などの問題が多く、実態と理念の乖離が深刻化していました。技能実習制度が抱えていた課題を解決するために制定されたのが「育成就労制度」です。
育成就労制度は、従来の実習制度が持つ技術習得の側面に加え、日本での長期就労を前提にした設計で、2027年の施行が予定されています。
育成就労制度と技能実習制度とのおもな違いは以下の通りです。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 技術移転を通じた国際貢献 | 技術育成+人材確保 |
| 在留期間 | 最長5年(号数で区分) | 原則3年 |
| 転籍 | 原則不可 | 本人希望かつ同一業種で可能 |
| キャリアパス | 帰国が前提 | 特定技能へ移行できる仕組みあり |
なお、育成就労制度の詳細は厚生労働省の資料にも掲載されていますので、より詳しく知りたい方は参考にしてください。
育成就労制度への移行は、技能を身につけさせながら日本で長期就労させたい企業、そして外国人のキャリアアップを支援したい組織にとって、非常に期待される新制度です。導入準備期間にしっかり体制を整え、次世代の外国人材活用に備えることが求められています。
特定技能と技能実習の違いのまとめ
特定技能と技能実習は、制度の目的・在留期間・業務範囲・転職可否・家族帯同・関係団体など、あらゆる面で大きく異なります。
企業が採用活動を進める際に最も重要なのは、「自社の業務に、どの在留資格が合っているか」を見極めることです特に経営者・人事責任者の方にとっては、コストや支援体制、雇用の柔軟性なども含めた判断が必要です。
例えば、現場で即戦力が必要で、長期的に働いてもらいたいと考えるならば、特定技能人材の活用が有効です。
一方で、特定の技能をしっかり教育し、計画的に育成したい企業、あるいは国際貢献の要素を重視したい企業であれば、技能実習制度(もしくは今後の育成就労制度)の活用が適しています。適切な制度を選択し、現場と企業双方にとって満足度の高い雇用を実現するために、ぜひ本記事の内容をご参考ください。
ご不明な点や導入に関するご相談があれば、下のコメント欄よりお気軽にご連絡ください。